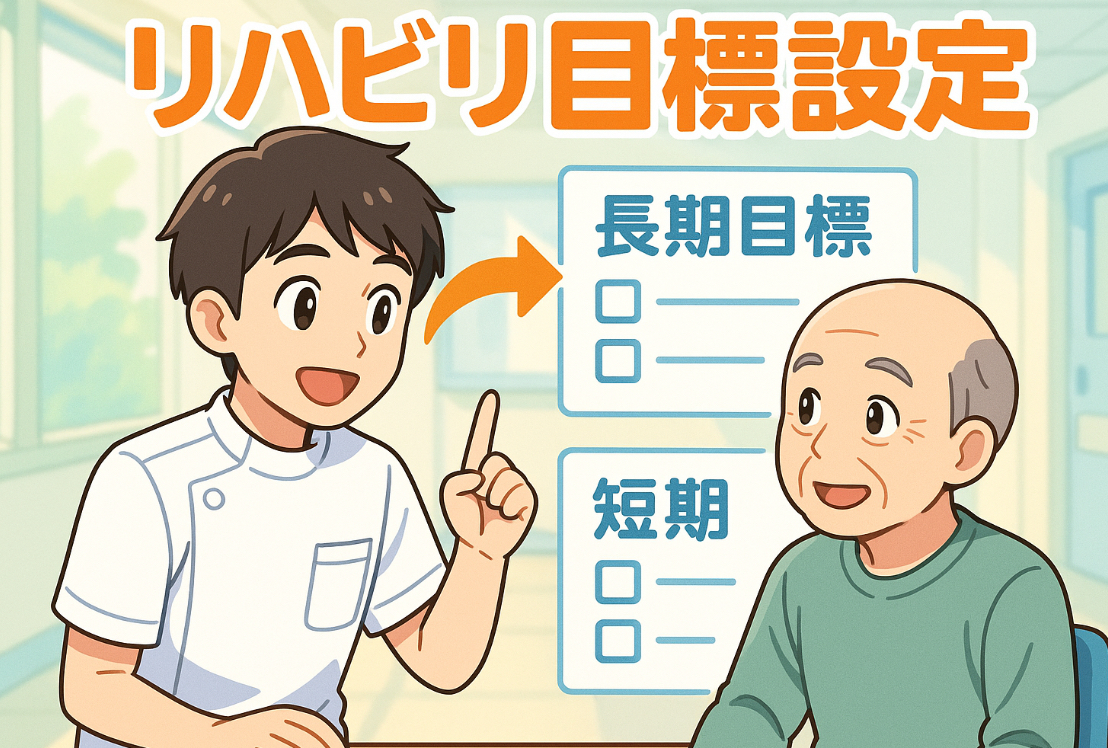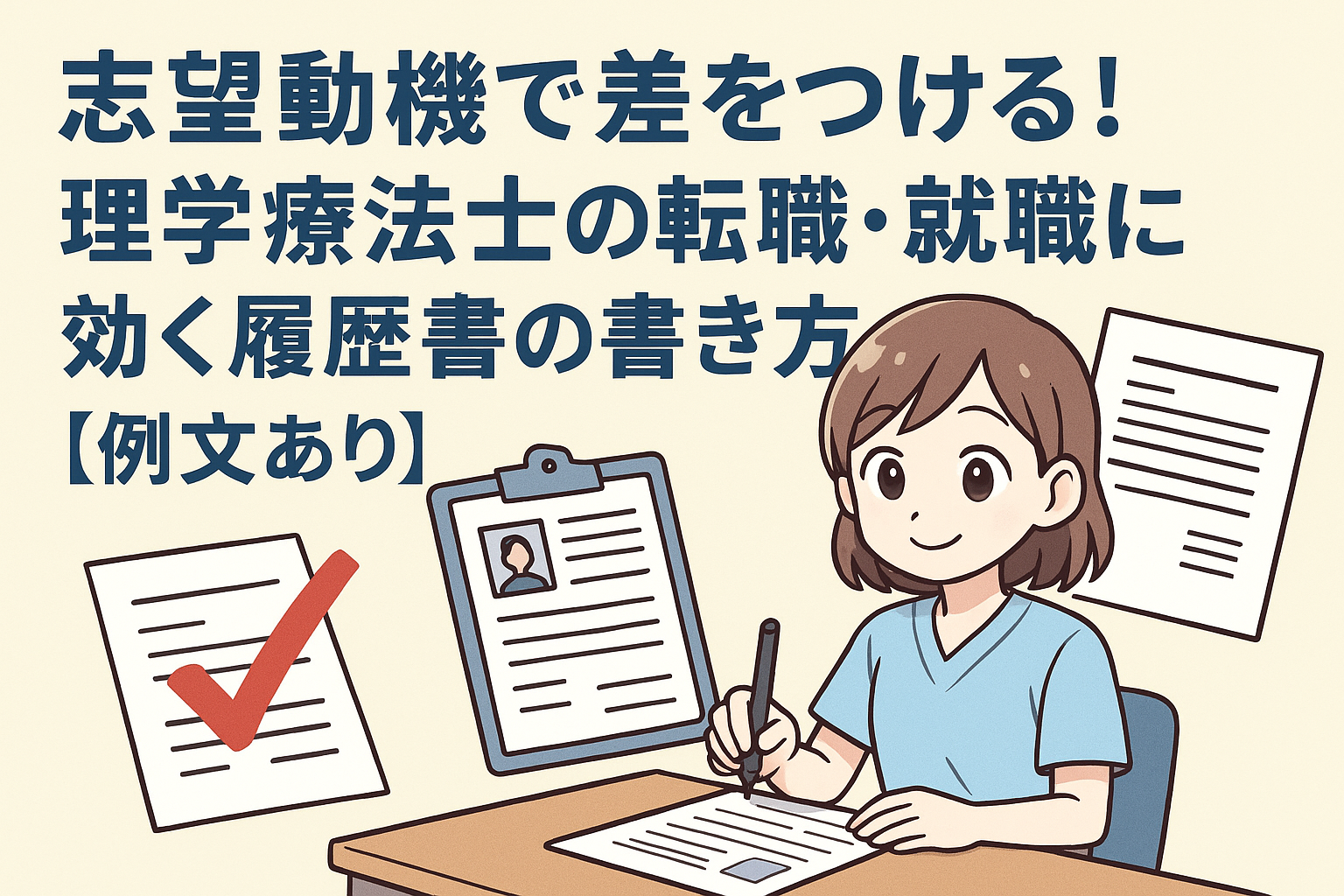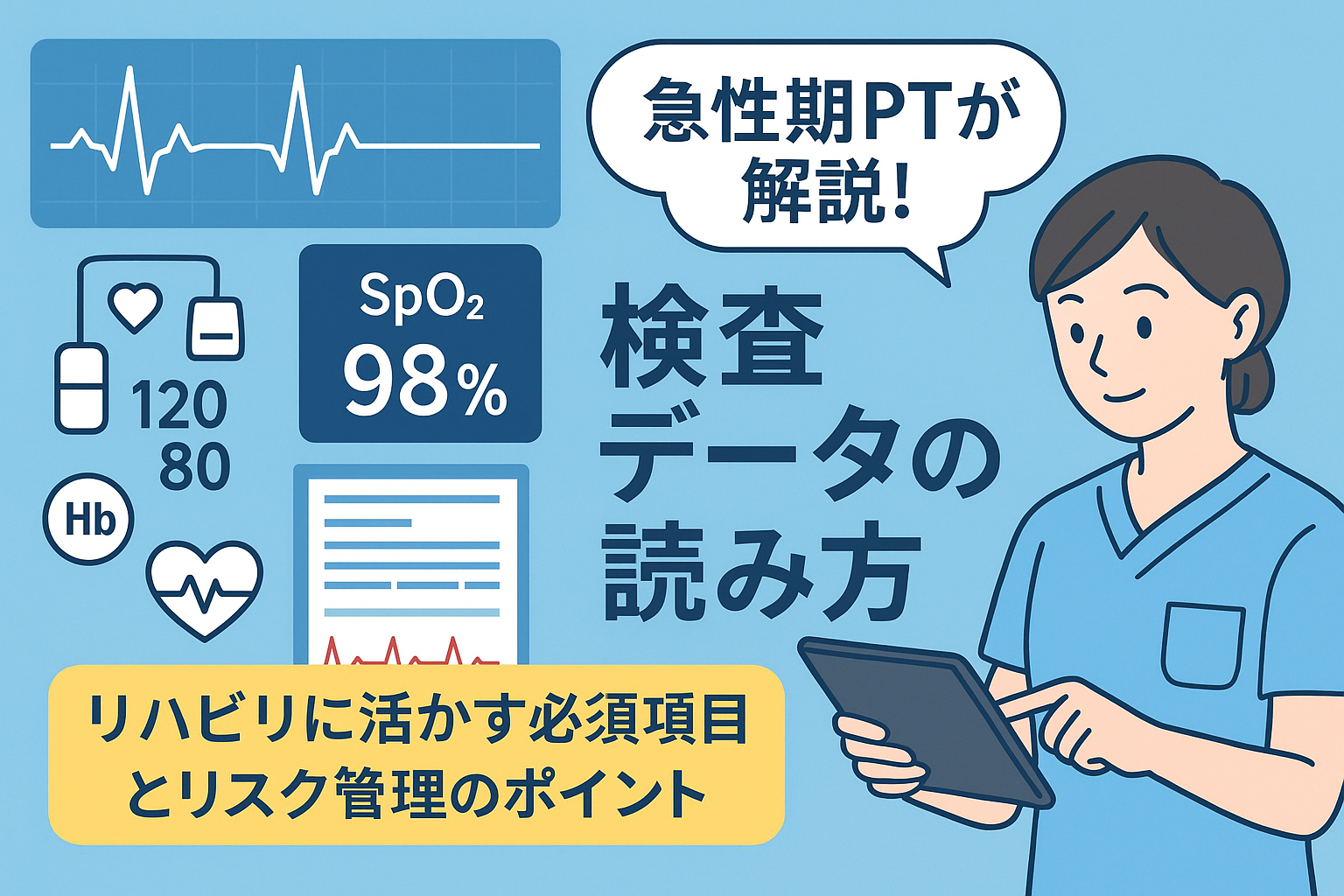はじめに
「リハビリの目標、どうやって立てればいいんだろう…」
「先輩に『この患者さんの目標は?』と聞かれて、いつも固まってしまう…」
理学療法の学生さんや新人さんにとって、「目標設定」は臨床で最初にぶつかる大きな壁ですよね。評価をして問題点は見えてきても、それをどうやって具体的な目標に落とし込めばいいのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、リハビリにおける目標設定の「キホンのキ」を解説します!
- なぜ目標設定が重要なのか?
- 長期目標(LTG)と短期目標(STG)の役割と違い
- 「良い目標」と「悪い目標」の具体例
この記事が、目標設定の考え方がスッキリ整理され、明日からの臨床実習や業務に自信を持って臨めるようになる一助となれば幸いです。
患者さんと一緒に、最高のゴールを目指すための第一歩を踏み出しましょう!
なぜリハビリに「目標設定」が必要不可欠なのか?

そもそも、なぜ私たちはこんなに時間をかけて目標設定をするのでしょうか?
それは、リハビリにおける目標が「患者さんと一緒に山を登るための地図」の役割を果たすからです。
もし地図がなければ、どの山(ゴール)に登るのか、どのルート(計画)で行くのか、今どのくらい進んでいるのか(進捗)が分からず、遭難してしまいますよね。
リハビリの目標には、以下の3つの重要な役割があります。
- リハビリの方向性を決める「コンパス」:どこに向かって進むのかを明確にします。
- モチベーションの「ガソリン」:患者さんとセラピストが「何のために頑張るのか」を共有し、意欲を高めます。
- チーム医療の「共通言語」:医師や看護師など、多職種が同じゴールに向かって連携するための土台となります。
この「地図」を正しく描くために、まずは長期目標と短期目標について理解を深めましょう。
\臨床理学Labでは?/
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

長期目標(LTG)とは?|リハビリの最終ゴール(山頂)
長期目標(Long-Term Goal: LTG)とは、その名の通り、リハビリ期間を通して達成を目指す最終的な到達点です。いわば、山登りにおける**「山頂」**にあたります。
長期目標の役割
- リハビリ全体のゴールを指し示す
- 患者さんの「こうなりたい」という希望を形にする
- 退院後の生活を見据えた大きな目標
長期目標を立てる時の考え方
最も重要なのは、ICF(国際生活機能分類)でいう「参加」や「活動」の視点です。
「膝の可動域が〇度改善する」といった身体機能の改善(心身機能)も大切ですが、それだけでは不十分です。その改善した身体機能を使って、患者さんが**「どんな生活を送りたいのか」「何をしたいのか」**という視点で設定することが何よりも大切です。
主役はあくまで患者さん。私たちが「これをすべき」と決めるのではなく、「退院したら、まず何をしたいですか?」「どんなことができるようになったら嬉しいですかと問いかけ、患者さんの本当のニーズを引き出しましょう。
具体例で比較!良いLTG vs 悪いLTG
【悪い例 ❌】
- 大腿四頭筋の筋力をMMT4レベルまで改善する。
- (→ これだけでは、その筋力で何がしたいのか不明確)
- 歩行を安定させる。
- (→ 抽象的で、ゴールが見えない)
【良い例 ✅】
- 杖歩行にて、自宅から徒歩15分のスーパーまで買い物に行き、安全に帰宅できる。(退院時)
- (→ 具体的な生活場面がイメージできる)
- 日中は介助なく、一人で自宅のトイレに行き、ズボンの着脱ができる。(3ヶ月後)
- (→ 生活の自立度が明確)
短期目標(STG)とは?|ゴールへの中間地点(チェックポイント)
短期目標(Short-Term Goal: STG)とは、長期目標という「山頂」にたどり着くために設定する、中間的なチェックポイントです。山登りでいう「〇合目の休憩所」のようなものです。
短期目標の役割
- 長期目標を達成可能な小さなステップに分解する
- 日々のリハビリ内容の具体的な根拠となる
- 進捗を確認し、計画を見直すための指標となる
- 患者さんの小さな成功体験となり、モチベーションを維持する
短期目標を立てる時の考え方
短期目標で最も意識すべきなのが、有名な**「SMART(スマート)の原則」**です。
- Specific:具体的か?
- Measurable:測定可能か?
- Achievable:達成可能か?
- Relevant:長期目標と関連しているか?
- Time-bound:期限が明確か?
誰が見ても「できたか、できなかったか」を客観的に判断できるよう、「いつまでに」「誰が(どんな介助で)」「何を」「どれくらい」できるかを明確に記述することが、STG作成の鍵となります。
※SMART原則を使った詳しい目標の立て方は、別の記事で徹底解説します!
具体例で比較!良いSTG vs 悪いSTG
【長期目標】
杖歩行にて、自宅から徒歩5分のスーパーまで買い物に行き、安全に帰宅できる。
【悪い例 ❌】
- 歩行練習を頑張る。
- (→ 具体性・測定可能性がない)
- 筋力をつける。
- (→ 長期目標との関連性が薄く、測定も曖昧)
【良い例 ✅】
- 理学療法士の監視下、T字杖を使用して病棟廊下を50m連続で歩行できる。(2週間後)
- (→ SMARTが明確。長期目標達成に必要な歩行能力の一部)
- 手すりを使用し、介助なく模擬階段を5段昇降できる。(1週間後)
- (→ スーパーの入り口の段差などを想定した、具体的な目標)

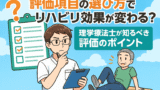
まとめ:最高の地図を手に、患者さんと共にゴールを目指そう
今回は、理学療法士の目標設定の基本である「長期目標」と「短期目標」について解説しました。
- 長期目標(LTG)は、患者さんの希望を元にした「最終ゴール(山頂)」。
- 短期目標(STG)は、ゴールまでの道のりを具体化した「チェックポイント(〇合目)」。
- 長期目標から逆算して、達成可能な短期目標を設定することが重要。
目標設定は、慣れるまでは難しく感じるかもしれません。しかし、これは患者さんの未来を描く、非常にクリエイティブでやりがいのある仕事です。
まずはこの基本をマスターし、自信を持って患者さんと向き合ってみてください。焦らず一歩ずつ、あなたと患者さんだけの最高の「地図」を作っていきましょう!