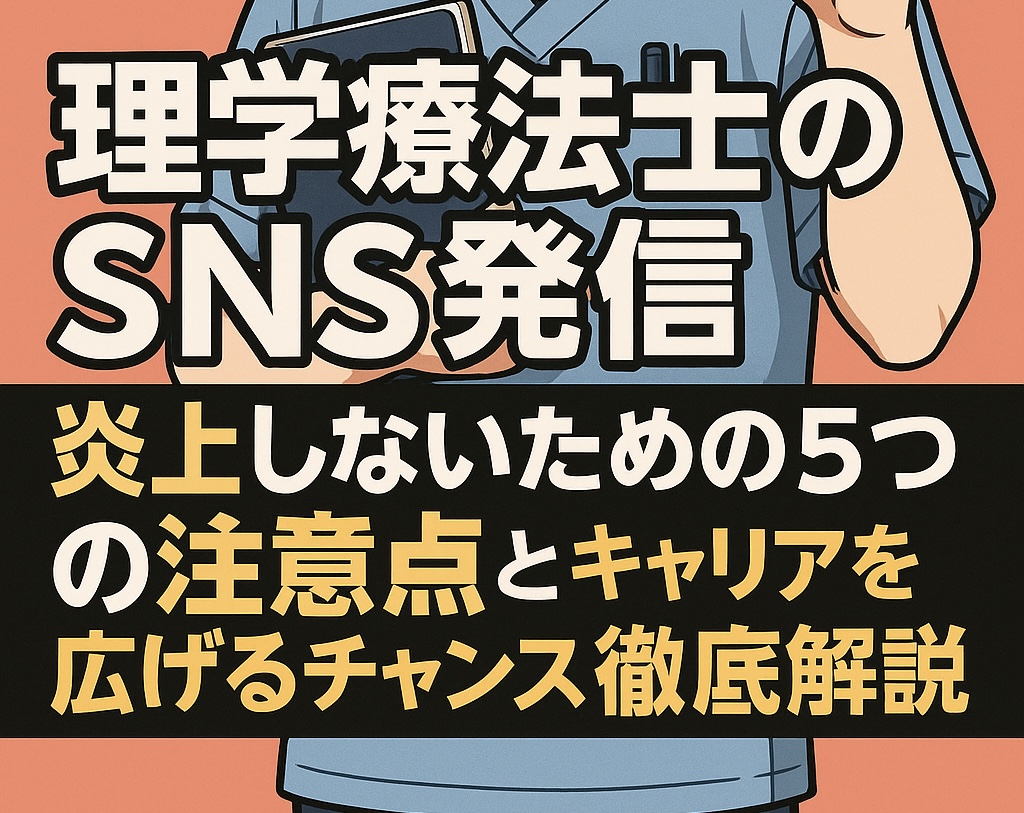はじめに
「自分の知識や経験を、もっと多くの人に役立てたい」
「理学療法士としてのキャリアの可能性を広げたい」
SNSで活躍する理学療法士(PT)が増える中、あなたもこんな風に考えたことはありませんか?
しかし同時に、
「個人情報はどこまで出していいの?」
「患者さんの話はNGだよね…?」
「炎上したらどうしよう…」
といった不安から、一歩を踏み出せないでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、SNS発信に挑戦したい理学療法士の皆さんが、リスクを避けながらチャンスを掴むための具体的な方法についてお話しします。
この記事から、SNS発信における不安が解消され、あなたの専門性を社会に還元し、キャリアを切り拓くための第一歩を踏み出せるヒントを得れるきっかけとなれば幸いです。
かくゆう私もまだまだ、未熟者ですので頑張って学んでいきたいと思っております。
\臨床理学Labで一緒に成長しませんか?/
「なぜこの痛みが起きたのか?どんな治療が効果的なのか?」
「どんな視点で評価すればよかったのか?」
「論文をどんな風に臨床に活かせばいいのか?」
そんな問いに一緒に向き合いながら、臨床で役立つ“推論の引き出し”を増やしていく場を、メンバーシップ限定コンテンツとしてご用意しています。※有料記事が読み放題
🔸 メンバー限定で読める「評価→推論→介入→再考察」付きの深掘り症例ノート
🔸 痛みや治療の考え方に特化した臨床推論の解説
🔸 コメント・質問歓迎のクローズドな学びの空間

なぜ今、理学療法士がSNSで発信するのか?4つのチャンス
まず、なぜ多くの理学療法士がSNS発信を始めているのでしょうか。そこには、これからの時代を生き抜くための大きなチャンスが隠されてると思っています。
チャンス1:専門知識を社会に広く還元できる
あなたの理学療法士としての知識は、病院や施設の中だけで必要とされているわけではありません。
腰痛や肩こりに悩む会社員、子どもの姿勢が気になる親御さん、スポーツのパフォーマンスを上げたい学生など、あなたの専門知識を求めている人は世の中にたくさんいます。
SNSは、そうした「未来の患者さん」や「健康に関心のある人々」に、予防医学やセルフケアの知識を届ける強力なツールです。
チャンス2:セルフブランディングとキャリアアップ
「腰痛治療の専門家」「産前産後ケアのプロ」など、特定分野の第一人者として認知されることで、あなたの市場価値は大きく高まります。
SNSでの継続的な発信は、あなたの名刺代わりとなり、以下のようなキャリアアップに繋がる可能性があります。
- セミナーや研修会の講師依頼
- 書籍やWebメディアでの執筆依頼
- 他業種の専門家との共同プロジェクト
- より条件の良い職場への転職やヘッドハンティング
チャンス3:新たな収益源の確保(副業)
専門家としての信頼を築くことができれば、SNSは新たな収益源にもなり得ます。
- オンラインサロンの運営: 専門知識を月額制で提供
- 有料コンテンツの販売: 自作のエクササイズ動画やPDF教材の販売
- アフィリエイト: おすすめのセルフケアグッズなどを紹介
- オンラインでの自費整体・コンディショニング
これらは、理学療法士としての知見を活かした、価値の高い副業と言えるでしょう。今後さらに増加していくと思いますよね。
チャンス4:同業者との質の高いネットワーク構築
SNSは、全国、ときには世界の理学療法士と繋がれるプラットフォームです。情報交換をしたり、勉強会を共同で開催したりと、切磋琢磨できる仲間を見つけることで、自身のスキルアップにも繋がります。

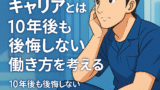
【最重要】炎上・トラブルを回避!理学療法士が守るべき5つの注意点
大きな可能性がある一方で、SNSにはリスクも伴います。特に医療専門職である私たちは、一般の方以上に慎重になるべきです。以下の5つの注意点を必ず守りましょう。
注意点1:守秘義務の徹底【個人情報は鉄壁ガード】
これは基本中の基本です。理学療法士及び作業療法士法第15条の2で定められている通り、我々には守秘義務があります。
- 絶対にNGな例
- 「今日担当した〇〇さん(芸能人、スポーツ選手など)のリハビリが…」
- 患者さんの年齢、疾患名、個人が特定できるエピソードの投稿
- 病院内や患者さんが写り込んでいる写真・動画の無許可での投稿
「少しぼかせば大丈夫だろう」という安易な考えが、個人情報の漏洩に繋がります。担当ケースの話は、学会発表や論文など、適切な手続きを踏んだ場で発表するようにしましょう。
注意点2:医療広告ガイドラインの遵守【誇大・虚偽表現はNG】
理学療法士の活動は、厳密には医業ではないため、医療広告ガイドラインの直接的な対象ではないと解釈されることもあります。しかし、国民に誤解を与えるような表現は、専門家としての信頼を失う原因になります。ガイドラインの精神を尊重し、誠実な情報発信を心がけましょう。
- 注意すべき表現の例
- ビフォーアフター写真: 施術効果を過度に期待させる可能性あり。使用は慎重に。
- 誇大表現: 「絶対に治る」「たった1回で痛みが消える」
- 他院との比較: 「〇〇整体院より効果的」
- 未承認の治療法: 科学的根拠の乏しい手技を、効果が保証されているかのように紹介する
注意点3:科学的根拠(EBM)に基づいた発信【個人的見解には注意】
あなたの発信する情報は、多くの人にとって「専門家からのアドバイス」として受け取られます。個人的な経験則や不確かな情報を、事実であるかのように発信するのは非常に危険です。
- 発信のポイント
- 情報の根拠となる論文や公的機関のガイドラインを示す
- 個人的な見解の場合は「これは私個人の意見ですが…」と明確に断る
- 断定的な表現を避け、「~という報告があります」「~の可能性があります」といった客観的な表現を心がける
注意点4:所属組織のルール(就業規則)の確認
副業やSNS活動について、勤務先がどのようなルールを定めているか必ず確認しましょう。許可なく活動を始めると、後々トラブルに発展する可能性があります。事前に上司や人事部に相談し、許可を得ておくと安心です。
注意点5:炎上リスクへの備えと誠実な対応
どれだけ気をつけていても、批判的なコメントや誤解に基づく指摘を受ける可能性はゼロではありません。
- もしもの時の心構え
- 感情的に反論しない
- 明らかな間違いは、素直に認めて謝罪・訂正する
- 悪質な誹謗中傷は、冷静に無視またはブロック・通報する
- 一人で抱え込まず、信頼できる同僚や友人に相談する
プラットフォーム別!SNS活用法の具体例
どのSNSを使うかによって、効果的な発信方法は異なります。あなたの目的や得意なことに合わせて選びましょう。
| SNS | 特徴 | 発信内容の例 |
| X (Twitter) | ・速報性、拡散力が高い・140字で手軽に発信・専門家同士の交流が活発 | ・最新論文やニュースの紹介・考察・日々の臨床での気づき(守秘義務厳守)・セミナーや勉強会の告知 |
| ・写真や動画(リール)がメイン・ビジュアルで直感的に伝えられる・女性や若年層ユーザーが多い | ・1分でできるストレッチやエクササイズの動画・図解でわかる「良い姿勢の作り方」・健康的な食事やライフスタイルの紹介 | |
| YouTube | ・長尺動画で詳しく解説できる・情報がストックされやすい・ファンを育成しやすい | ・「腰痛改善」などテーマ別の徹底解説動画・リハビリの考え方や評価方法の解説・理学療法士を目指す学生向けのキャリア相談 |
| ブログ | ・体系的な知識をまとめられる・SEO対策で検索流入が見込める・信頼性、専門性を示しやすい | ・疾患別のリハビリテーション解説・専門分野の知識をまとめた記事・SNS発信のまとめと深掘り |
まとめ:注意点を守り、理学療法士としての新たな一歩を
SNSは、正しく使えば理学療法士にとって非常に強力な武器となります。あなたの持つ専門知識は、院内だけでなく、社会全体にとって価値のある資産です。
最後に、SNS発信を成功させるための大切な心構えを3つお伝えします。
- 専門分野を絞る: 「〇〇の専門家」として認知されることが近道です。
- ターゲットを明確にする: 「誰に」「何を」伝えたいのかを具体的に考えましょう。
- 継続する: すぐに結果は出ません。まずは週に1回の投稿など、小さな目標から始めてみましょう。
今回解説した5つの注意点を必ず守り、誠実な情報発信を心がけてください。そうすれば、炎上などのリスクを最小限に抑え、あなたのキャリアを豊かにする大きなチャンスを掴むことに繋がるのではないでしょうか。