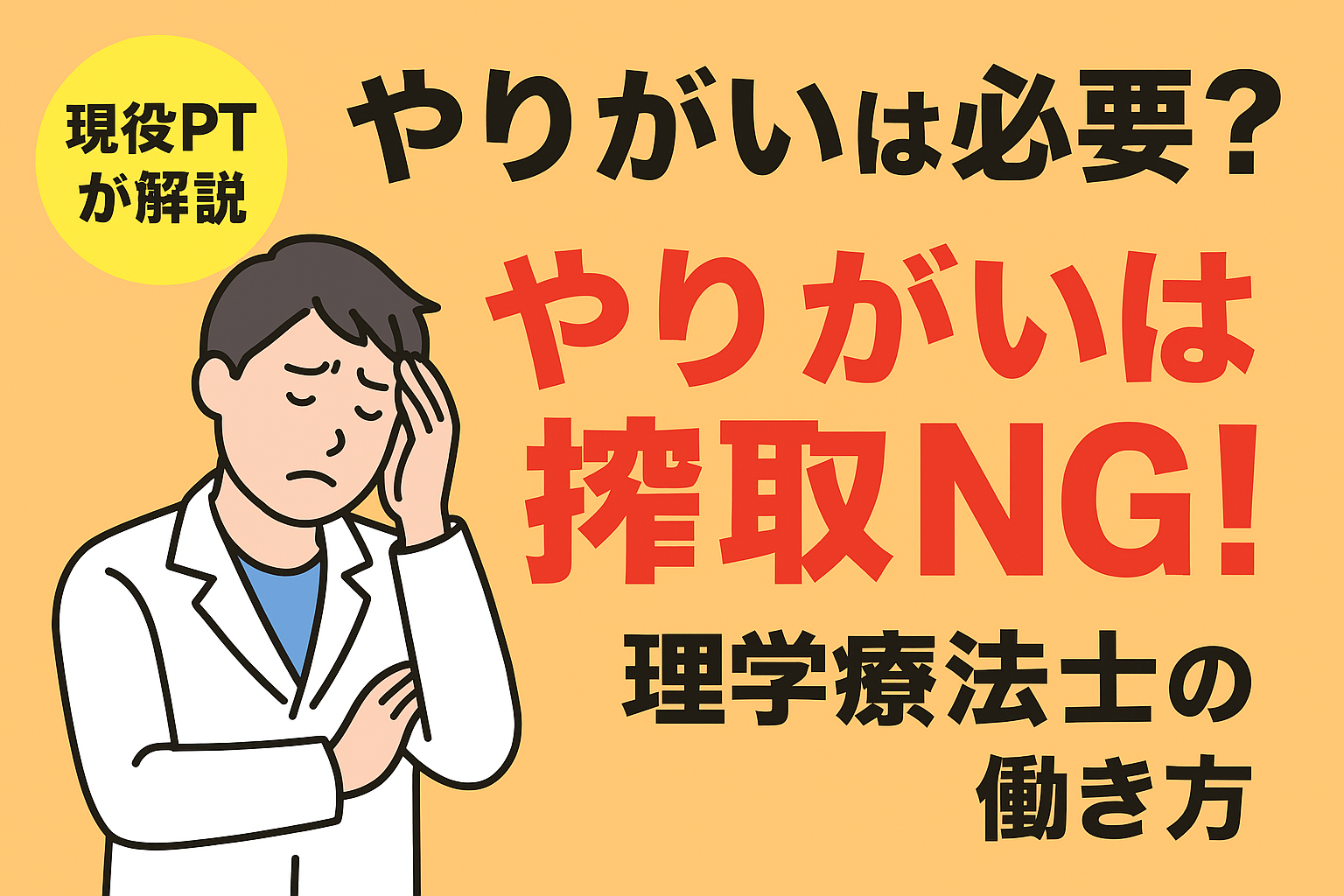理学療法士の仕事、やりがいって本当に必要?
患者さんの笑顔や「ありがとう」の言葉を支えに頑張っている一方で、「仕事は生活のため」「やりがいを求めると疲れるだけ」という声も聞こえてきます。
給料は上がらないのに責任は重い。理想と現実のギャップに悩み、「もう辞めたい…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
僕自身、「やりがいがすべて!」と信じて働いてきましたが、現場の厳しい現実に直面し、心が折れそうになった経験があります。
この記事では、僕が現場で見てきた「やりがい不要派」のリアルな声と、僕自身が「やりがい搾取」に陥らず、自分の心を守りながらモチベーションを保つために見つけ出した「やりがいとの上手な付き合い方」を、実体験を交えてお伝えします。
この記事が、自分なりの「やりがい」とのバランスを見つけるヒントが得られるきっかけとなれば幸いです。
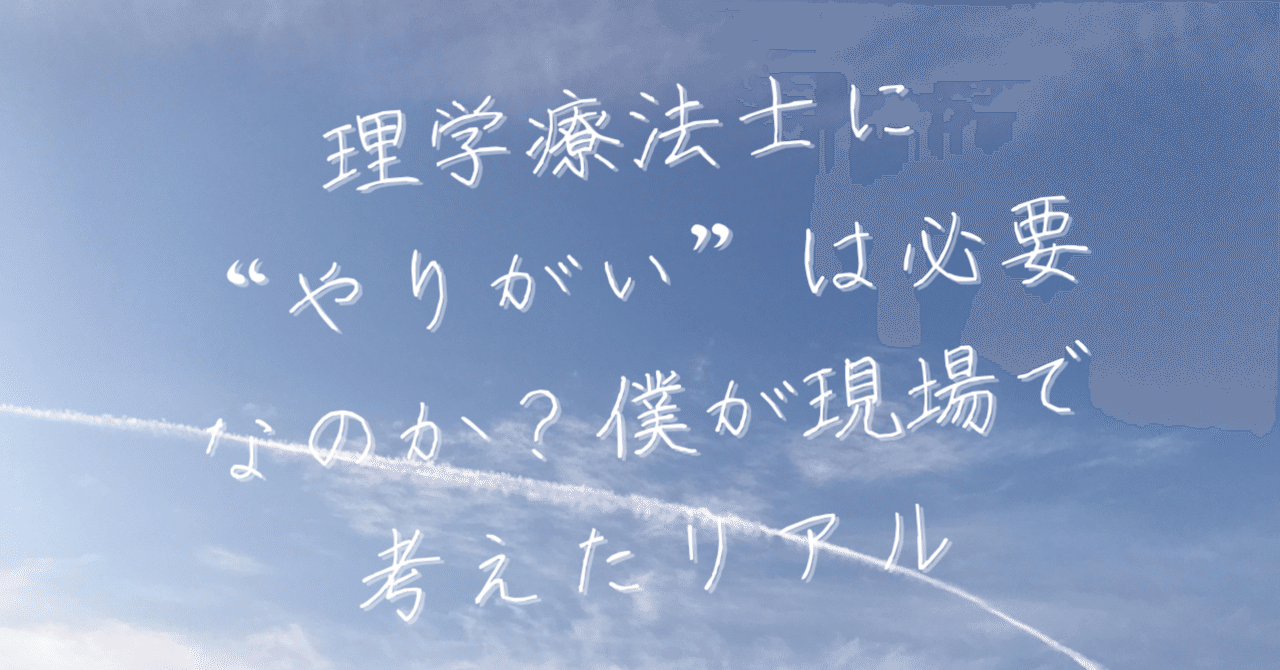
理学療法士が「やりがいは不要」と感じる3つのリアルな理由
僕の職場にも「やりがいなんていらない」というスタンスのセラピストは少なくありません。彼らは決してやる気がないわけではなく、むしろ真面目に働いてきたからこそ、そう考えるようになった人が多いのです。
理由1:報われない努力と上がらない給料
ある同僚は、こう漏らしていました。
「患者さんのために一生懸命やっても、給料は変わらないし、正当に評価もされない。だったら、淡々と仕事をこなして定時で帰る方が賢いよ。」
この言葉の裏には、努力が報われないことへの虚しさがあります。理学療法士の給与体系は年功序列が根強く、個人の頑張りが直接収入に結びつきにくいのが現実です。
理由2:「やりがい搾取」と燃え尽きへの恐怖
「やりがい」という言葉を都合よく利用され、低賃金・長時間労働を強いられる**「やりがい搾取」**。この問題に疲弊しているセラピストは後を絶ちません。
別の先輩はこう言います。
「やりがいを求めると、自分を犠牲にしがち。休日返上で勉強会に行ったり、サービス残業で患者さんに付き合ったり…そうやって燃え尽きて辞めていった仲間を何人も見てきたからね。」
「やりがい=自己犠牲」という構図に陥りやすい業界だからこそ、防衛本能として「やりがいとは距離を置く」という選択をする人がいるのです。
理由3:ワークライフバランスを重視する価値観の変化
「仕事は生活のための手段。人生を充実させるには、プライベートを全力で楽しむべき」
SNSでもよく見かけるこの価値観は、理学療法士の世界でも広がっています。業界特有の構造的な問題(人員不足、時間に追われる業務など)も相まって、「仕事にすべてを捧げる」という働き方に疑問を持つ人が増えているのです。
【体験談】僕が「やりがいなんてどうでもいい」と思った瞬間
やりがいを大切にしてきた僕でさえ、すべてを投げ出したくなった瞬間があります。
それは、単位数を稼ぐためだけのリハビリを強制された時でした。
担当していたのは、重度の認知症があり、リハビリへの強い拒否を示す患者さん。
本当は無理強いしたくない。でも、組織からは「単位を取れ」という強いプレッシャーがかかる。
「今日の単位をどう埋めるか」
それしか考えられなくなった僕は、心を殺して患者さんの部屋へ向かいました。
「○○さん、少しだけ一緒に動きましょう」
しかし、返ってきたのは拒絶の言葉と、手を振り払われる仕草。
その日の目標単位は未達成。上司に報告すると、冷たい言葉が返ってきました。
「それは説明の仕方が悪いからじゃないの?」
心が、ポキッと折れる音がしました。
「何のためにやってるんだろう?」
「こんな思いをしてまで、やりがいなんて追い求める意味あるの?」
あの瞬間、僕は「ただ単位をこなすだけの作業でいい」と本気で思いました。患者さんの笑顔も成長も、どうでもよくなってしまった自分が、本当に嫌でした。

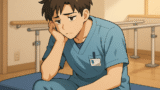
やりがいゼロで働いてみて気づいたこと
感情を殺し、仕事を“作業”としてこなす日々。すると、心と体に異変が起き始めました。
- ストレスの増加: 患者さんに拒否されるたびに心がすり減る。
- 慢性的な疲労感: 同じ業務なのに、帰宅するとぐったりして何もできない。
精神的な支えである「やりがい」がなくなると、仕事のストレスがダイレクトに心身を蝕むのだと痛感しました。このままでは壊れてしまう。そう感じた僕は、必死に現状を変えるための行動を起こしました。
- 院外の研修会に参加する
外の世界には、同じ仕事なのに、驚くほど生き生きと働くセラピストがたくさんいました。彼らの姿に「自分もまだやれることがある」と大きな刺激をもらいました。 - 自分で小さな目標を立てる
「今日、患者さんの表情を一回でも笑顔にできたらOK」
「今週、このアプローチを一つ試してみる」
誰かに評価されるためではなく、自分のための小さな成功体験を積み重ねることで、少しずつ仕事の楽しさを取り戻していきました。
この経験から学んだのは、**「他人は変えられない。でも、自分の考え方と行動は変えられる」**という、シンプルな真実でした。
燃え尽きない!僕が実践する「やりがいの育て方」3つのコツ
今、僕は「理学療法士にやりがいは必要だ」と自信を持って言えます。ただし、それは盲目的に追い求めるのではなく、自分自身でコントロールし、“育てる”という感覚です。
僕が燃え尽きずにやりがいと付き合うために実践している3つのことを紹介します。
コツ1:やりがいを「自己成長」と捉える
この仕事の醍醐味は、一人ひとりの患者さんと向き合う中で、常に新しい課題解決が求められる点です。壁にぶつかり、学び、乗り越える。そのプロセス自体が、自分を成長させてくれます。
「患者さんのため」はもちろんですが、**「自分の成長のため」**という視点を持つと、努力の方向性が明確になります。
コツ2:やりがいのハードルを下げる
「歩けるようにする」といった大きな目標だけでなく、日々の小さな成功に目を向けてみましょう。
- 患者さんが笑顔を見せてくれた
- 少しだけ可動域が広がった
- 挨拶を返してくれた
こうした**「小さなやりがい」**を見つけるクセをつけることで、日々の業務が達成感に満ちたものに変わっていきます。
コツ3:「自分にできること」と「できないこと」を切り分ける
病院の体制や上司の考え方など、自分一人の力では変えられないこともあります。そこにエネルギーを注いで悩むのはやめましょう。
変えられないことは受け流し、**「自分自身の知識・技術・関わり方」**という、コントロール可能な領域に集中する。この切り替えができるようになってから、心がとても楽になりました。
まとめ:理学療法士の「やりがい」は自分で見つけ、育てるもの
最後に、この記事の要点をまとめます。
- 「やりがい不要論」の背景:低賃金、やりがい搾取、燃え尽きなど、業界の構造的な問題がある。
- やりがいゼロの危険性:精神的な支えを失い、心身の不調につながるリスクがある。
- 燃え尽きないための工夫:
- 自己成長と捉え、自分のために学ぶ。
- 小さな成功体験に目を向け、達成感を得る。
- 変えられないことで悩まず、自分に集中する。
やりがいは、誰かに与えられるものではなく、自分で見つけ、育んでいくものです。
もし今、あなたが仕事に疲れ、やりがいを見失っているなら、一度立ち止まって「自分にとってのやりがいとは何か?」を考えてみてください。
その答えが、明日からの臨床を少しだけ明るく照らしてくれるかもしれません。
【ご案内】
もしこの記事を読んで、「もっと現場のリアルな話を聞きたい」「臨床での考え方を深めたい」と感じた方は、僕が運営しているnoteメンバーシップもぜひ覗いてみてください。
メンバーシップ限定で、
- 現場で実際にあったケーススタディの詳細
- 日々の臨床ですぐに役立つ思考法や工夫
- 専門知識をさらに深めるための解説記事
などを配信しています。
あなたの臨床のヒントが、きっと見つかるはずです。ご参加をお待ちしています。