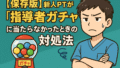理学療法士向けに運動失調(Ataxia)の基礎を解説。麻痺との違い、小脳性・感覚性の見分け方、指鼻指試験などの評価、リハビリの考え方を網羅。明日からの臨床に活かせる知識が身につきます。
はじめに
こんにちは!
新人や若手のセラピストの皆さん、こんな悩みを抱えていませんか?
- 患者さんの動きがぎこちない…。これって麻痺?それとも運動失調?
- 先輩から「この患者さん、ataxia(アタキシア)あるね」と言われたけど、具体的にどう評価・リハビリすればいいんだろう?
- 運動失調って種類が多くて、何から勉強したらいいか分からない…
分かります。私も新人時代、動きの「ぎこちなさ」の正体が分からず、アプローチに悩んだ経験があります。
この記事では、そんな新人セラピストの皆さんが明日からの臨床で自信を持って運動失調の患者さんに向き合えるように、基礎知識から評価、リハビリの考え方までを分かりやすく解説します。
\臨床推論を一緒に鍛えていきませんか?/
「なぜこの痛みが起きたのか?」
「どんな視点で評価すればよかったのか?」
「もしあなたが担当していたら、どう考えたか?」
そんな問いに一緒に向き合いながら、
臨床で役立つ“推論の引き出し”を増やしていく場を、メンバーシップ限定コンテンツとしてご用意しています。
🔸 メンバー限定で読める「評価→推論→介入→再考察」付きの深掘り症例ノート
🔸 痛みに特化したリハ評価のフレームワーク解説
🔸 コメント・質問歓迎のクローズドな学びの空間

そもそも運動失調(Ataxia)とは?まず麻痺との違いを理解しよう
まず一番大事なポイントです。運動失調とは、**「筋力低下(麻痺)が主な原因ではないのに、動きの力加減やタイミング、複数の関節の協調がうまくいかず、動作がぎこちなくなる状態」**を指します。
運動を家に例えるなら、
- 司令塔(大脳): 「コップを取れ」と命令する人
- 実行部隊(筋肉): 命令通りに動く手足
- 調整役(小脳など): 司令塔と実行部隊の間で、力の入れ具合やスピードを微調整する人
運動失調は、この「調整役」がうまく機能しなくなった状態です。司令塔からの命令も、実行部隊の筋力も問題ないのに、微調整ができないために動きがスムーズにいかないのです。

麻痺との違いを表にまとめると、臨床での見え方がクリアになります。
| 項目 | 筋力低下(麻痺) | 運動失調(Ataxia) |
| 主な原因 | 錐体路(運動神経)の障害 | 小脳、深部感覚路、前庭などの障害 |
| 力の入り方 | 弱い、入らない | 力は入るが、調整ができない |
| 動きの特徴 | だらりとしている、動かせない | ぎこちない、震える、行き過ぎる(測定障害) |
| 代表的な評価 | 徒手筋力テスト(MMT) | 指鼻指試験、踵膝試験など |
患者さんの動きを観察する際は、「力が入らないのか?」それとも「力は入るけど、調整がヘタなのか?」という視点を持つことが、最初のステップです。
【原因別】3つの運動失調と見分け方のポイント
運動失調は、原因となる障害部位によって、主に3つのタイプに分けられます。それぞれの特徴を知ることが、的確なアプローチの鍵となります。
1. 小脳性失調:最も代表的な失調
小脳は「運動の学習と調節」を担う、まさに調整役の中心です。ここが障害されると、運動のプログラムそのものにエラーが生じます。
- 特徴的な症状
- 測定障害(Dysmetria): 目標物に対して手が届かなかったり、行き過ぎたりする。
- 変換運動障害(Adiadochokinesis): 手のひらを素早く返したりする、反対の動きへの切り替えが苦手。
- 共同運動障害(Asynergy): 複数の関節を滑らかに連動させられない(例:リーチで肩と肘がバラバラに動く)。
- 企図振戦(Intention Tremor): 目標物に近づくにつれて、震えが大きくなる。
2. 感覚性(脊髄性)失調:目からの情報が頼り
脊髄の後索などを通り、脳に伝わる**「深部感覚(位置覚や振動覚)」**が障害されることで起こります。自分の手足が今どこにあるか、という情報が乏しいため、動きの調整が難しくなります。
- 特徴的な症状
- ロンベルグ徴候 陽性: 目を開けていると立てるが、目を閉じると途端にふらつきが強くなる。
- 不足した深部感覚を視覚で代償しているため、歩くときに足元をじっと見て歩く。
- 暗い場所や、足場の悪い場所で特に不安定になる。
3. 前庭性失調:めまいとふらつきが特徴
耳の奥にある、体のバランスを司る「前庭」や、それに関連する神経の障害で起こります。
- 特徴的な症状
- **回転性のめまい(ぐるぐる回る感じ)や眼振(眼球の揺れ)**を伴うことが多い。
- 特定の頭の位置や、頭を動かしたときにふらつきが悪化する。
- まっすぐ歩けない(偏倚歩行)。
明日から使える!運動失調の評価方法
評価の目的は、単に「失調あり/なし」を判断することではありません。「どのようなエラーが、どの場面で起きるのか」を質的に分析し、原因を推測してリハビリに繋げることが重要です。
基本的な協調性テスト
- 指鼻指試験(Finger-Nose-Finger test): 患者さんの鼻と検者の指を交互に触ってもらいます。測定障害や企図振戦の有無を観察しましょう。
- 踵膝試験(Heel-Knee-Shin test): 仰向けで、片方の踵を反対側の膝に当て、すねの上をまっすぐ足首まで滑らせてもらいます。下肢の協調性を評価します。
- 手回内・回外試験: 膝の上などで、手のひらを素早くリズミカルに返してもらいます。変換運動障害の評価に有用です。
【重要】ロンベルグ試験で感覚性失調を見抜く
ロンベルグ試験は、小脳性と感覚性の失調を鑑別する上で非常に重要です。
- 足をそろえて立ち、まずは目を開けたまま姿勢を保持してもらいます。
- 次に、転倒しないよう安全を確保した上で、目を閉じてもらいます。
【解釈】
- 開眼・閉眼ともに不安定 → 小脳性失調の可能性が高い
- 開眼では安定、閉眼で著しく不安定になる → 感覚性失調の可能性が高い(ロンベルグ徴候 陽性)
この違いを理解しておくだけで、アプローチの方向性が大きく変わります。
【理学療法士向け】運動失調のリハビリ・アプローチの考え方
運動失調に対するリハビリに「これをすれば治る」という特効薬はありません。だからこそ、原因に応じたアプローチの「考え方」が大切になります。
小脳性失調へのアプローチ:「反復による運動学習」と「代償」
運動プログラムのエラーが原因なので、正しい運動を繰り返し、再学習を促すことが基本です。
- 視覚フィードバックの活用: 鏡の前でリーチ動作を練習し、動きのズレを自分で見て修正する。
- 動作の分節化: 「立つ→歩く」という複雑な動作を、「お辞儀する」「お尻を上げる」「片足を出す」のように単純な要素に分解して練習する。
- 重りの利用(ウェイト): 手首や足首に重りを巻くことで、固有感覚入力を増やし、振戦を抑制する効果が期待できます。ただし、筋疲労を起こしやすいため、使用は慎重に判断します。
感覚性失調へのアプローチ:「他の感覚による代償」
足りない深部感覚を、他の感覚(特に視覚)で補う戦略が中心となります。
- 視覚代償の徹底: 歩行時に自分の足元や目標物をしっかり見るように指導する。生活空間を明るくする。
- 足底感覚の活用: 裸足や薄い靴下で歩く練習をし、足の裏からの情報を最大限に活用する。
- 安全な環境下でのバランス練習: 平行棒内などで、あえて不安定な課題に挑戦し、利用可能な感覚情報を統合する能力を高める。
また、どちらのタイプでも、手すりの設置や歩行補助具(重りのついた杖や四輪歩行器など)の選定、滑りにくい履物の提案といった環境調整は、理学療法士の重要な役割です。
まとめ:運動失調の患者さんに向き合う新人セラピストへ
今回は、運動失調の基礎について解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。
- 運動失調は「筋力」ではなく「調整」の問題。まずは麻痺と区別しよう。
- 原因は主に「小脳性」「感覚性」「前庭性」。ロンベルグ徴候が鑑別のヒント。
- 評価では「どんなエラーか」を質的に観察し、原因を推測しよう。
- リハビリは原因に応じて「運動学習」と「代償」のアプローチを考えよう。
運動失調のリハビリは根気がいりますが、患者さんの「できた!」が増えたときの喜びは格別です。焦らず、まずは一人の患者さんをじっくり評価することから始めてみてください。分からないこと、悩むことは、あなたが成長している証拠です。一人で抱え込まず、ぜひ先輩にも相談してみてくださいね。
この記事が、あなたの臨床の一助となれば幸いです。