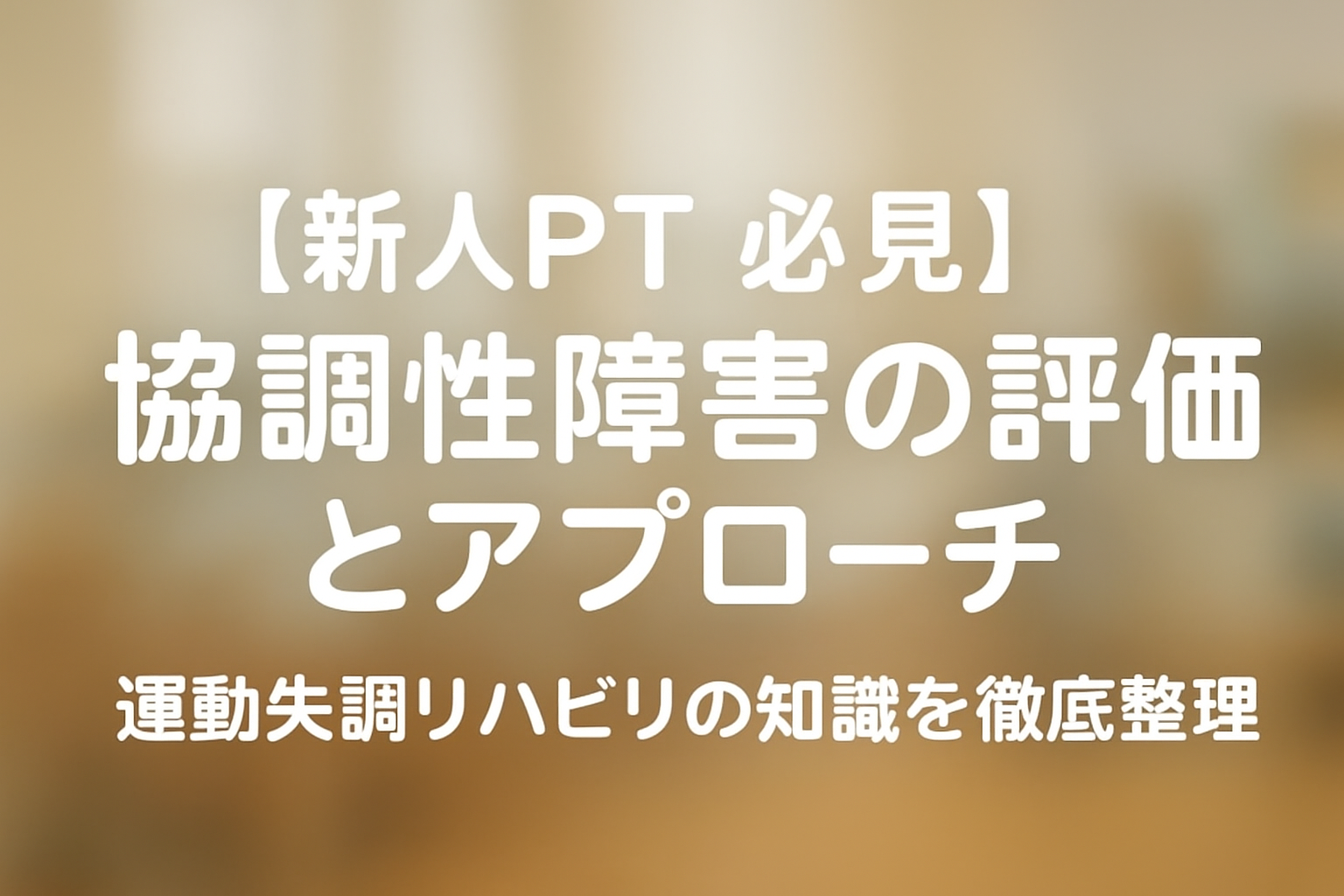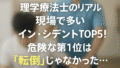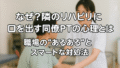その「動きにくさ」、正しく評価できていますか?
「明日から小脳梗塞の患者さんを担当することになったけど、何から評価すればいいんだろう…」
「運動失調(Ataxia)って教科書で習ったけど、臨床でどう活かせばいいか分からない…」
新人・若手理学療法士の皆さん、こんな悩みを抱えていませんか?
患者さんの「何となく動きがぎこちない」「よく物を落とす」といった訴えの裏には、協調性障害という明確な機能障害が隠れています。これを正しく理解し、的確に評価・アプローチすることが、患者さんのADL(日常生活動作)を改善する鍵となります。
この記事では、協調性障害の基本的な知識の復習から、明日からの臨床ですぐに使える評価フロー、そして具体的な理学療法アプローチまでを、ステップ・バイ・ステップで徹底解説します。
知識の再整理】協調性障害とは?運動失調(Ataxia)を深く理解する
まず、基本をおさらいしましょう。協調性障害とは、「複数の筋活動を時間的・空間的にまとめあげ、スムーズで目的に合った運動を行う能力の障害」です。
この中心的な役割を担うのが「小脳」。
小脳は、運動の力加減やタイミングを調整する「運動の司令塔」のような存在です。この小脳や、関連する神経路がダメージを受けることで、協調性障害、特に運動失調(Ataxia)と呼ばれる状態が引き起こされます。
臨床で出会う運動失調は、原因によって大きく4つに分類されます。鑑別がアプローチの第一歩です。
- ① 小脳性運動失調: 最も代表的。小脳そのものの損傷(脳梗塞、脊髄小脳変性症など)で生じます。
- ② 感覚性運動失調: 脊髄後索など深部感覚の経路が障害され、手足の位置情報が脳に伝わらないために生じます。視覚で動きを代償しようとするのが特徴です(開眼で改善、閉眼で増悪:ロンベルグ徴候陽性)。
- ③ 前庭性運動失調: 内耳や前庭神経の障害で生じ、めまいを伴うふらつきが特徴です。
- ④ 大脳性失調:運動の企画・プログラミングの障害
この記事では、特に遭遇する機会の多い「小脳性運動失調」を中心に解説を進めます。
これだけは押さえたい!協調性障害の主要な症状(カルテ記載にも使える専門用語)
患者さんの動きを的確に表現するために、以下の専門用語と現象を一致させましょう。
- 測定障害 (Dysmetria): 運動の距離や大きさを誤る。「コップに手を伸ばしたら、行き過ぎて倒してしまった」など。
- 反復拮抗運動不能障害 (Dysdiadochokinesia): 手の回内・回外のような素早い反復運動ができない。動きがぎこちなく、リズムが乱れます。
- 共同収縮不能障害 (Asynergia): 複数の関節を滑らかに動かせない。そのため、関節を一つずつ動かすような分解運動が見られます。
- 企図振戦 (Intention Tremor): 目標物に近づくにつれて、手や指の震えが大きくなる。静止時には震えは見られません。
- 時間測定障害 (Dystonia): 運動の開始や終了のタイミングがずれる。
- 構音障害 (Dysarthria): 呂律が回らず、発話が不明瞭になる。爆発性言語(発語が途切れ途切れで、爆発するようになる)が特徴的。
- 筋緊張低下 (Hypotonia): 筋肉のハリが低下し、関節がぐらぐらした印象を受けます。
これらの症状が、歩行(酩酊様歩行)、食事、更衣、書字など、あらゆるADLに影響を及ぼします。
原因となる代表的疾患と理学療法士が知るべき特徴
協調性障害は、様々な疾患の結果として現れます。疾患の特性を理解することが、予後予測やゴール設定に不可欠です。
- 脳血管障害: 小脳梗塞や小脳出血が代表。急性期からの関わりが多く、回復過程に合わせたアプローチが求められます。
- 脊髄小脳変性症 (SCD): 進行性の疾患。機能回復だけでなく、残存機能を活かすための代償的アプローチや環境設定、福祉用具の提案も重要になります。
- 多発性硬化症 (MS): 再発・寛解を繰り返すのが特徴。易疲労性も顕著なため、過度な運動負荷を避け、エネルギー消費を抑えた効率的な動作の指導が求められます。
- 頭部外傷、脳腫瘍: 損傷部位によって多様な症状を呈するため、高次脳機能障害など他の機能障害との関連も考慮した評価が必要です。
【臨床実践編】明日から使える!協調性障害の評価フロー
「さて、何から始めよう?」もう迷う必要はありません。このフローに沿って評価を進めましょう。
Step 1:情報収集と問診
- カルテ情報: 診断名、画像所見(特に小脳のどの部位か)、既往歴を確認。
- 本人・家族からの聴取: 「生活の中で、具体的に何に一番困っていますか?」という問いから始め、食事、整容、更衣、書字などの場面での困難さを具体的に聞き出します。
Step 2:定性的評価(ベッドサイドでの神経学的検査)
まずは、道具を使わずに患者さんの動きの質を観察します。
- 上肢の評価:
- 指鼻指試験 (Finger-Nose-Finger Test): 患者の鼻と検者の指を交互に触ってもらう。測定障害、企図振戦の有無を評価。
- 手回内・回外試験: 変換運動障害の評価。
- 下肢の評価:
- 踵膝試験 (Heel-to-Shin Test): 仰向けで、片方のかかとを反対側の膝から脛に沿ってまっすぐ滑らせる。下肢の協調性を評価。
- 観察のポイント: 動きの速度、正確性、滑らかさ、リズム。そして、視覚による代償がないかを確認します。
Step 3:定量的評価(客観的指標で変化を追う)
評価は客観性が命。変化を数値で捉えるために、標準化された評価バッテリーを活用します。
- SARA (Scale for the Assessment and Rating of Ataxia):
- 運動失調の重症度評価で最も広く使われる評価法の一つ。歩行、立位、坐位、言語障害など8項目(40点満点)で構成され、簡便で臨床応用しやすいのが特徴です。まずはこれをマスターしましょう。
- ICARS (International Cooperative Ataxia Rating Scale):
- SARAより詳細な19項目(100点満点)の評価。より詳細な分析が必要な場合や研究などで用いられます。
Step 4:機能評価(ADLとの関連付け)
神経学的所見が、実際の生活にどう影響しているかを分析します。
- バランス評価:
- BBS (Berg Balance Scale): 動的・静的バランスの総合的な評価。
- TUG (Timed Up & Go test): 複合的な動作能力の評価。
- 失調症の患者さんは支持基底面を広く取り、体幹の動揺が大きいなど、特徴的な戦略をとるため、その質的な側面も観察します。
- 歩行分析:
- 歩隔(両足の幅)の拡大、歩幅の不整、足の運びの乱れといった「酩酊様歩行」の特徴を観察。10m歩行テストなどで速度も測定します。
- ADL評価:
- 実際に食事やボタンかけなどの動作を観察し、どの症状(例:企図振戦)が、どの動作(例:箸で豆をつまむ)を困難にしているのかを直接的に結びつけます。
理論とエビデンスに基づく理学療法アプローチ
評価で明らかになった問題点に対し、具体的なアプローチを組み立てます。
① 運動制御の再学習(Frenkel体操の原理応用)
協調性障害リハビリの古典的かつ基本となるアプローチです。
- 目的: 視覚や聴覚フィードバックを最大限に活用し、深部感覚の乱れを代償。ゆっくり、大きく、正確な運動を反復することで、正しい運動プログラムを脳に再学習させます。
- 具体例:
- 臥位: 踵をベッドから離さず、目標(印など)の上を滑らせる。
- 坐位: 床に描いた線に沿って足を動かす。
- 立位: 床の足跡マークに合わせて歩く。
② PNF (固有受容性神経筋促通法)
体幹や近位関節の安定性を高めることは、四肢のコントロールに不可欠です。
- 目的: 体性感覚入力を増やし、筋の協調的な収縮を促通します。
- 具体例:
- リズミックスタビリゼーション: 坐位や四つ這い位で体幹に多方向から抵抗を加え、安定性を高める。
- コンビネーションオブアイソトニックス: 一連の運動の中で、求心性・遠心性・等尺性収縮を組み合わせ、滑らかな運動パターンを学習させる。
③ 重錘負荷 (Weighting) と抵抗運動
企図振戦や測定障害が強い場合に有効なことがあります。
- 目的: 手首や足首に重錘(ウエイト)を巻いたり、セラバンドで抵抗を加えたりすることで、固有受容感覚の入力を増やし、運動の制御を助けます。
- 注意点: 筋疲労を起こしやすく、患者さんによっては逆効果になることも。重さや時間は慎重に設定し、効果を確認しながら進めます。
④ バランストレーニング
転倒予防と歩行の安定化に直結します。
- 目的: 様々な環境下で姿勢を維持・制御する能力を高めます。
- 具体例:
- 支持基底面を徐々に狭くする(開脚立位→閉脚立位→継ぎ足立位)。
- 不安定な支持面(バランスディスク、クッション)上での立位保持。
- 視覚情報を遮断(閉眼)したり、頭部を動かしたりしながらの立位保持。
⑤ 日常生活動作(ADL)訓練と環境設定
リハビリ室での訓練を、実際の生活に繋げます。
- 課題指向型訓練: 「ボタンを留める」「字を書く」など、患者さんが困っている具体的な動作そのものを反復練習します。
- 代償的アプローチ:
- 自助具の活用: 太柄のスプーン、ボタンエイド、重さのあるペンなど。
- 環境設定: 手すりの設置、滑りにくい床材への変更など。
- 進行性の疾患では、この視点が特に重要になります。
まとめ:学び続け、患者さんと共に歩む
協調性障害のリハビリテーションは、一朝一夕に結果が出るものではなく、セラピストにも患者さんにも根気が必要です。しかし、この記事で紹介した知識と技術を駆使すれば、必ず患者さんの生活に変化をもたらすことができます。
【本記事のポイント】
- 協調性障害は現象を正しく理解し、体系的な評価(特にSARA)を行うことが第一歩。
- 原因疾患の特性を理解し、予後を予測した上でゴール設定を行う。
- アプローチは多岐にわたるが、評価結果に基づき、根拠を持って選択・組み合わせることが重要。
今日の学びを、ぜひ明日からの臨床で実践してみてください。そして、評価とアプローチを繰り返し、試行錯誤しながら、目の前の患者さんにとっての最適なリハビリテーションを見つけ出してください。あなたの成長が、患者さんの「できた!」に繋がっています。
お知らせ
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!