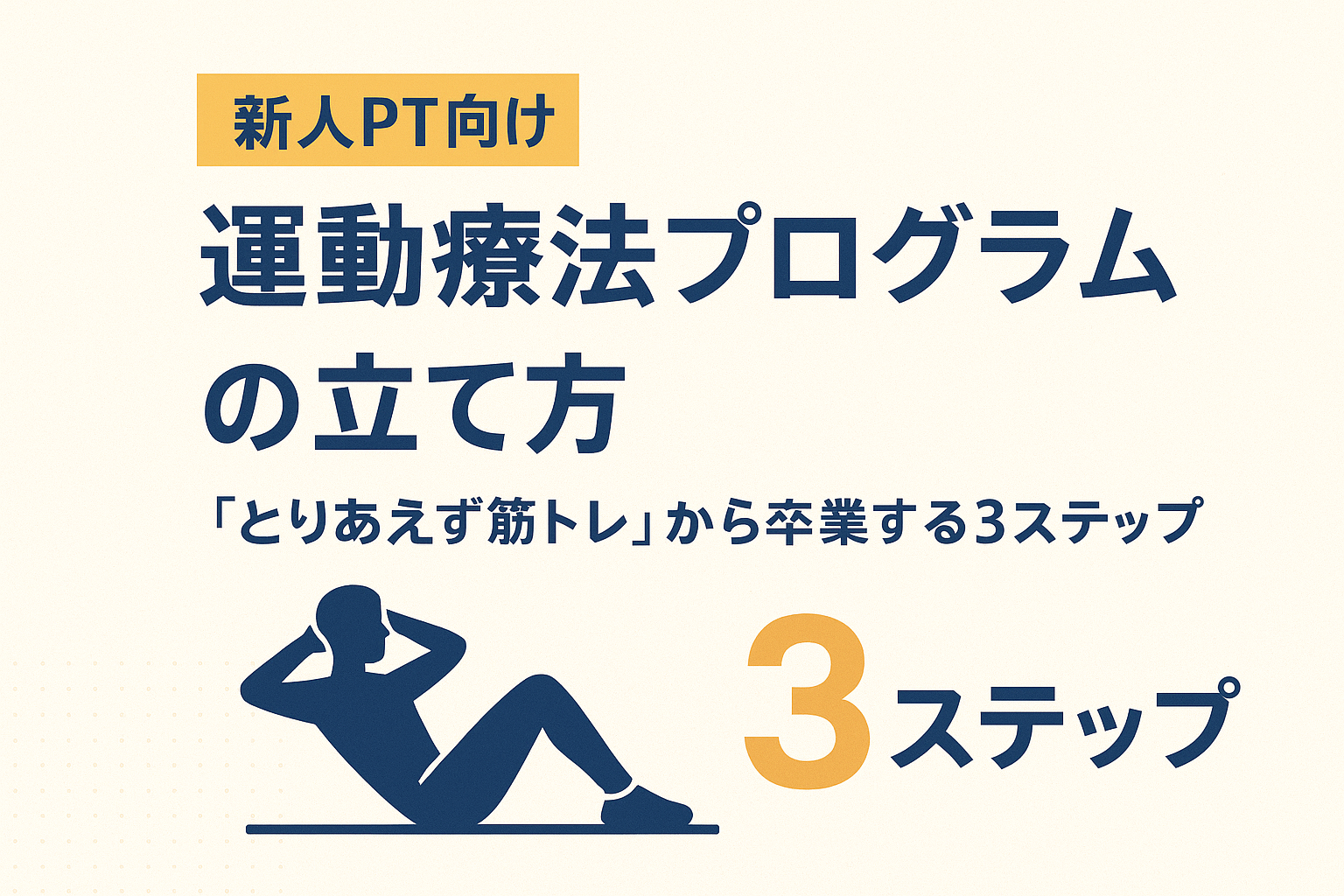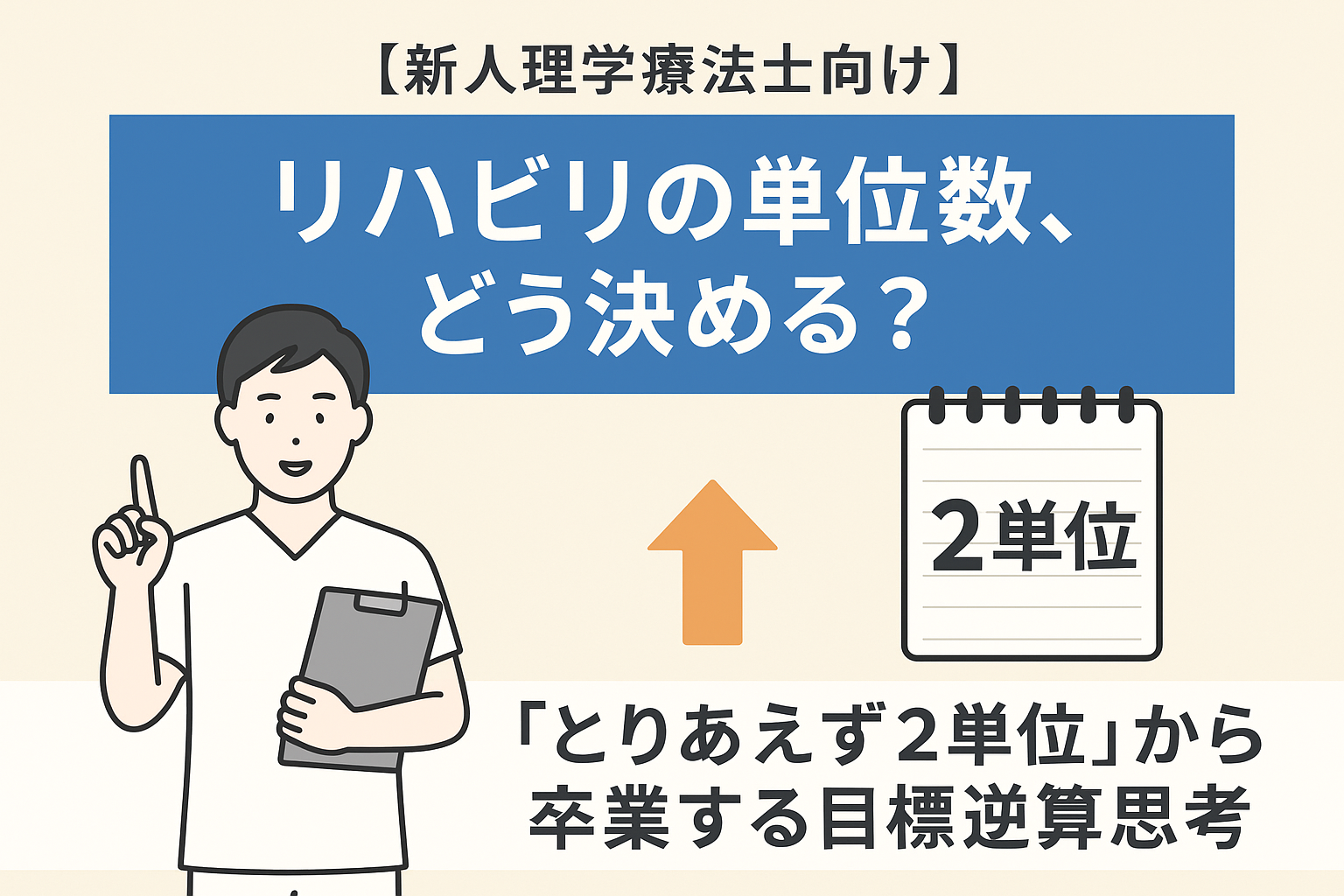なぜその運動してるんですか?
「〇〇さんの筋力低下が目立つから、とりあえず大腿四頭筋の筋トレを10回3セットで…」
臨床に出たばかりの理学療法士(PT)の皆さん。
毎日、こんな風に運動療法プログラムを組んでいませんか?
先輩から「なんでその筋トレが必要なの?」「その負荷設定の根拠は?」と聞かれ、言葉に詰まってしまった経験、一度はあるかもしれません。
僕も新人時代、評価と治療がうまく繋がらず、「とりあえず」でメニューを組んでしまい、自信を持てずにいた経験があります。
しかし、ある「思考のフレームワーク」を身につけてから、患者さん一人ひとりに合わせた、根拠ある運動療法プログラムを自信を持って作成できるようになったのです。
この記事では、評価結果から根拠を持って運動療法プログラムを組み立てるための3つのステップを、具体的なケースを交えながら分かりやすく解説します。
「なんとなくのリハビリ」から卒業し、患者さんの変化を最大化できるセラピストを目指しましょう!
【臨床理学Labについて】
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります。

なぜ「とりあえずの筋トレ」ではダメなのか?
まず、なぜ僕たちが「とりあえず」から卒業しなければならないのか。それは、「とりあえずの筋トレ」がもたらす弊害があるからです。
- 効果が出にくい:筋力低下の真の原因にアプローチできていない可能性があります。
- 患者さんの信頼を損なう:「いつも同じ運動だな…」と患者さんのモチベーションが低下し、リハビリへの参加意欲を下げてしまいます。
- 専門性が発揮できない:理学療法士としての評価・分析能力が活かせず、誰にでもできる運動指導になってしまいます。
僕たちの役割は、単に「運動させること」ではありません。評価に基づき、患者さんの目標達成への最短ルートをデザインすることが必要です。
【完全ガイド】根拠ある運動療法プログラムを立てる3ステップ
ここからが本題です。リハビリのプログラム作成に迷ったら、この3つのステップで思考を整理してみてください。
STEP 1:【原因分析】なぜ、その筋肉は弱いのか?を評価する
「筋力が弱い=鍛える」という短絡的な思考から一歩踏み込み、「なぜ筋力低下が起きているのか?」という原因を探ることが最初のステップです。
筋力低下の原因は、大きく3つに分類できます。
- 廃用性:長期間使わなかったことによる筋萎縮や筋力低下です。(例:長期臥床、ギプス固定後)
- 神経原性:脳卒中後の麻痺など、神経系のダメージによって筋肉へ命令がうまく伝わらない状態です。
- 疼痛性:関節の痛みなどによって、脳が意図的に筋出力を抑制している状態です。(例:変形性膝関節症、術後)
【評価のヒント】MMTの「質」を見よう
MMT(徒手筋力テスト)で 数値を測るだけでなく、力の入り方=質を観察しましょう。「Grade4」という結果でも、その中身は全く違います。
- 最後まで抵抗できるけど震える → 持久性の問題?(廃用性)
- 最初は力が入るが途中で抜ける → 痛みが原因?(疼痛性)
- そもそも収縮がほとんど入らない → 神経系の問題?(神経原性)
このように原因を仮説立てることで、アプローチ方法の選択肢が変わってきます。
STEP 2:【ターゲット選定】どの筋肉を、”なんのために”鍛えるのか?
次に、数ある筋肉の中から、どの筋肉を優先的に鍛えるべきか「ターゲット」を絞り込みます。
その鍵は「ADL(日常生活活動)からの逆算」です。
【思考プロセス】
- 患者さんの目標(Goal)を確認する
- 例:「一人でトイレまで歩いて行きたい」
- 目標に必要なADLを分解する
- 例:「ベッドからの起き上がり」「立ち上がり」「歩行」
- 各ADLに必要な「キーマッスル」を特定する
- 立ち上がり:大殿筋(お尻)、大腿四頭筋(太もも前)、前脛骨筋(すね)
- 歩行(立脚中期):中殿筋(お尻の横)、大腿四頭筋、下腿三頭筋(ふくらはぎ)
STEP1の評価で弱かった筋肉と、このキーマッスルが一致した筋肉こそが、最優先でアプローチすべきターゲットです。これにより、「立ち上がりのために、大腿四頭筋を鍛えます」と、目的と手段を明確に説明できるようになります。
STEP 3:【処方箋の作成】どんな方法(負荷・回数・頻度)で鍛えるのか?
ターゲットが決まったら、いよいよ具体的なプログラム、いわば「処方箋」を作成します。
ここで重要になるのが、運動療法の原則に基づいた負荷設定です。
- 過負荷の原則:筋肉を成長させるには、日常レベルより「少しキツい」と感じる負荷が必要。
- 特異性の原則:目的に合ったトレーニングを行うことが重要。
これを踏まえ、負荷・回数を決めます。
【負荷設定のモノサシ】
- RM(最大反復回数)法
- 筋力増強が目的:高負荷・低回数(例:ギリギリ8回〜12回できる重さ=8〜12RM)
- 筋持久力向上が目的:低負荷・高回数(例:15回〜20回できる重さ=15〜20RM)
- 自覚的運動強度(ボルグスケール)
- 患者さんに「どのくらいキツいですか?」と尋ね、「ややきつい(13程度)」を目安にする方法。高齢者にも使いやすい指標です。
さらに、STEP1で考えた「原因」も考慮します。
例えば、疼痛性の筋力低下がある患者さんに、いきなり高負荷なスクワットを行うのは逆効果です。まずは等尺性運動(関節を動かさない筋トレ)や自動介助運動から始めるなど、原因に応じた最適な方法を選択することが専門性です。
ケースで実践!「立ち上がりが不安定なAさん」のプログラム立案
では、これら3ステップを使って、具体的なプログラムを考えてみましょう。
- 患者情報:Aさん(70代女性)。大腿骨頚部骨折術後2週。目標は「ポータブルトイレへの移乗自立」。
- 【STEP 1:原因分析】
- 術後の安静による廃用性の筋力低下と、術創部周囲の疼痛性の筋出力抑制が考えられる。
- 【STEP 2:ターゲット選定】
- ADLの課題は「立ち上がり」。動作観察で、殿部が上がりにくく、膝がガクッと揺れる。
- → ターゲットは大殿筋と大腿四頭筋に絞る。
- 【STEP 3:処方箋の作成】
- プログラム①:まずは疼痛に配慮し、関節運動を伴わない大腿四頭筋セッティング(等尺性運動)。負荷は自動運動。回数は10回2セットから開始。
- プログラム②:痛みのない範囲で、ベッド上で行えるブリッジ運動(大殿筋)を追加。負荷は自重。回数は10回2セット。
- 声かけ:「Aさん、この太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)がしっかりすると、立ち上がりの時の膝のグラつきが減りますよ。痛みがない範囲でやってみましょう」
このように、一つひとつの運動に「なぜこれを行うのか」という根拠が生まれます。
まとめ:根拠あるプログラムで、信頼されるセラピストへ
今回は、新人理学療法士が「とりあえずの筋トレ」から卒業するための、運動療法プログラムの立て方について解説しました。
- STEP 1:【原因分析】 なぜ弱いのか?(廃用・神経・疼痛)を評価する
- STEP 2:【ターゲット選定】 ADLから逆算してキーマッスルを絞り込む
- STEP 3:【処方箋作成】 目的に合わせて負荷・回数・方法を決定する
この3ステップの思考法は、あなたの臨床での迷いを減らし、リハビリの質を格段に上げてくれるはずです。
「なんとなく」ではなく「根拠あるオーダーメイドの運動療法」を提供する。それが、患者さんから本当に信頼されるセラピストへの第一歩です。
まずは明日の臨床で、一人の患者さんだけでもこの3ステップに沿ってプログラムを見直してみませんか?
日々の臨床の一助となりますように。