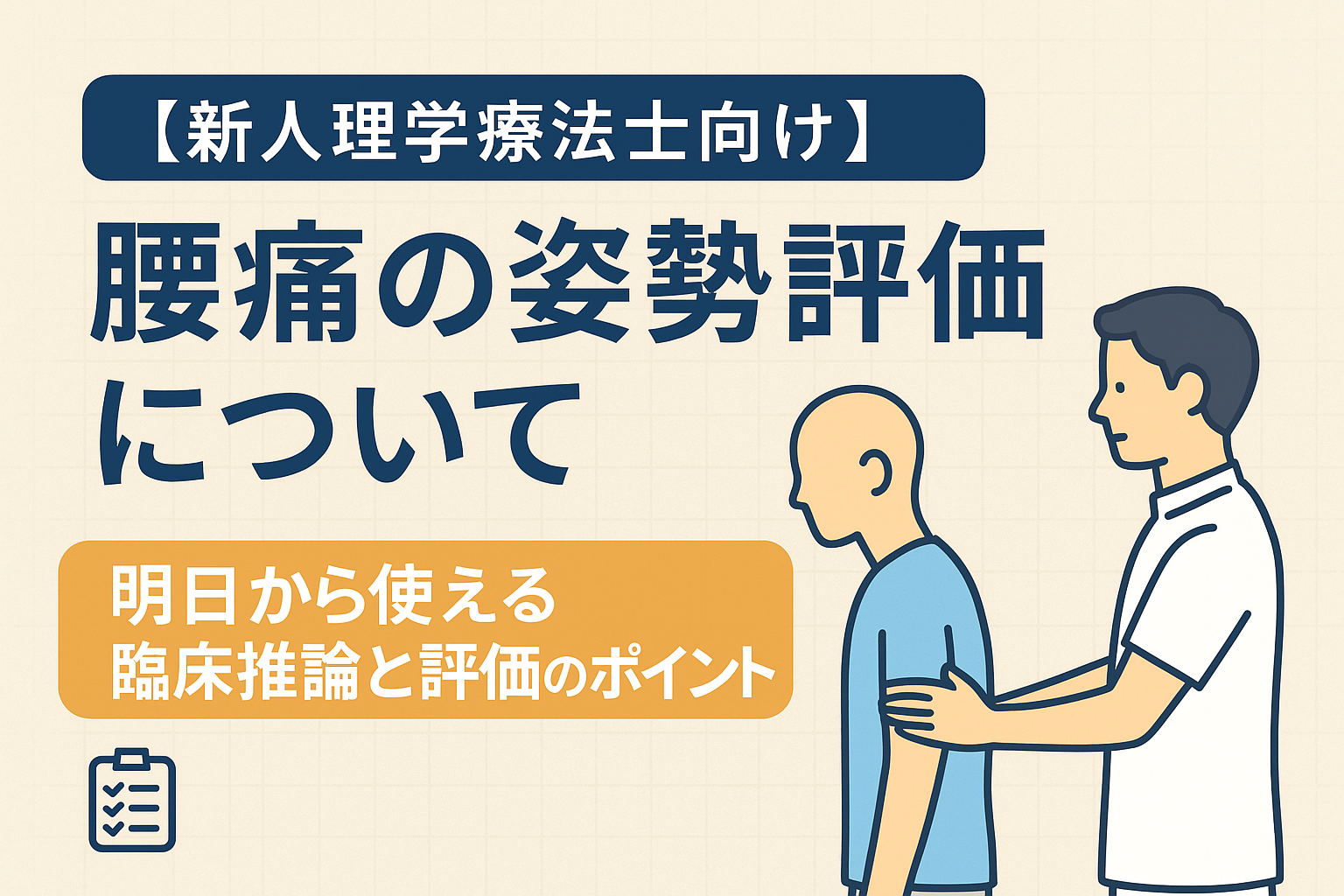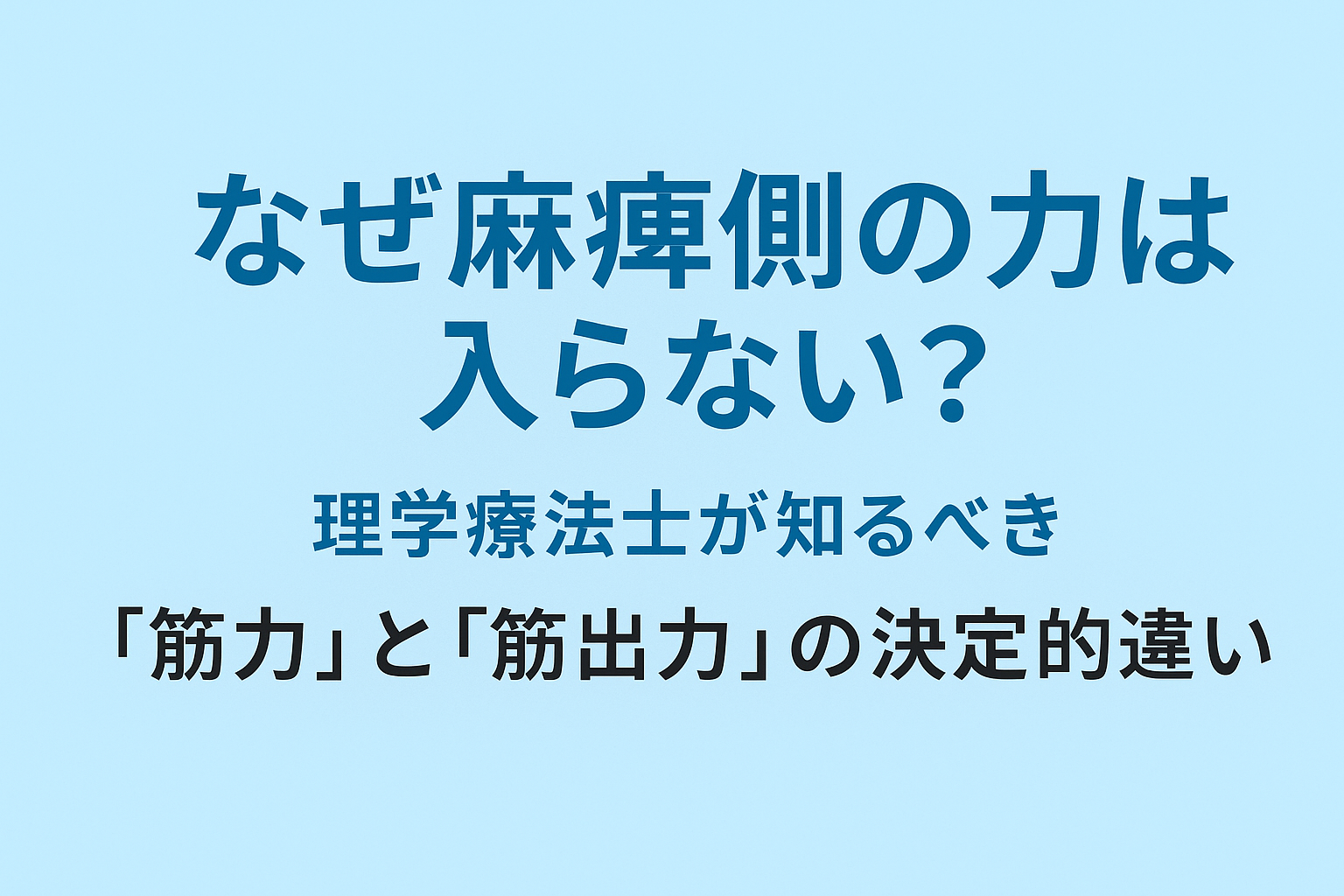はじめに
【想定する読者の悩み】
- 腰痛患者の姿勢評価は行うが、いつも同じ視点でしか見られていない…
- 視診で得た情報を、その後のアプローチにどう繋げれば良いか分からない…
- 痛みの原因を「姿勢」と結論づけるが、その先の思考が深まらない…
新人・若手セラピストが臨床で必ずぶつかる「腰痛患者への姿勢評価」。ルーチンワークになりがちですが、一歩踏み込んだ視点を持つだけで、治療の精度は劇的に向上します。
本記事では、腰痛に繋がりやすい代表的な不良姿勢を運動学的・解剖学的に解説し、評価結果を治療に繋げるためのクリニカルリーズニング(臨床推論)のプロセスの例をご紹介します。
【この記事で学べること】
- 腰痛を誘発する不良姿勢の力学的メカニズム
- 表層的な観察で終わらない、詳細な静的・動的姿勢評価の視点
- 評価結果を統合し、治療仮説を立てるための思考プロセス
なぜ姿勢評価が重要なのか?腰部への力学的ストレスを理解する
改めて、我々セラピストが姿勢を評価するのは、単に「形」を見るためではありません。そのアライメントが、どの組織(椎間板、椎間関節、靭帯、筋・筋膜)に、どのような力学的ストレス(圧縮、伸張、剪断)を与え続けているかを推測するためです。
特に矢状面アライメントの破綻は、腰椎への負担を増大させる主要因となります。まずは代表的な3つの不良姿勢パターンと、それに伴う力学的ストレスを再確認しましょう。
① Sway-back(スウェイバック)
骨盤が前方へ変位し、胸椎が後方へ代償的に変位した姿勢。重心線は股関節の後方を通過します。
- 運動学的特徴
- 骨盤前方変位+後傾
- 股関節過伸展位
- 胸椎後弯増強、頭部前方変位
- 力学的ストレス
- 腰椎下部(特にL4/5, L5/S1)の椎間関節および後方支持組織(棘上・棘間靭帯)への伸張ストレス。
- 股関節前面の靭帯(腸骨大腿靭帯など)への持続的な伸張ストレス。
- 筋活動の特徴 (Janda: Lower Crossed Syndrome類似)
- 短縮/過緊張: ハムストリングス、腹直筋上部、胸部傍脊柱筋群
- 伸張/弱化: 腸腰筋、大腿直筋、腹斜筋群、多裂筋、大殿筋
② Flat-back(フラットバック)
腰椎前弯が減少し、骨盤が後傾した姿勢。生理的S字弯曲が失われ、衝撃吸収能力が低下します。
- 運動学的特徴
- 腰椎前弯減少(平坦化)
- 骨盤後傾
- 股関節伸展位、膝関節軽度屈曲位代償
- 力学的ストレス
- 椎間板への軸圧・圧縮ストレスが増大。衝撃吸収能の低下により、椎間板性腰痛やヘルニアのリスク因子となる。
- 腰椎屈曲モーメントが増大し、背部筋群の持続的な遠心性収縮を要求される。
- 筋活動の特徴
- 短縮/過緊張: ハムストリングス、腹直筋
- 伸張/弱化: 腸腰筋、腰部脊柱起立筋
③ Lordosis(反り腰 / 腰椎過前弯)
骨盤が過度に前傾し、腰椎前弯が増強した姿勢。
- 運動学的特徴
- 骨盤前傾
- 腰椎前弯増強
- 股関節屈曲位、膝関節過伸展位代償
- 力学的ストレス
- 腰椎椎間関節への圧迫・剪断ストレスが増大。椎間関節性腰痛や腰部脊柱管狭窄症のリスク因子。
- 椎間孔が狭小化し、神経根への刺激が生じやすい。
- 筋活動の特徴 (Janda: Lower Crossed Syndrome)
- 短縮/過緊張: 腸腰筋、大腿直筋、腰部脊柱起立筋、大腿筋膜張筋
- 伸張/弱化: 腹筋群(特に腹横筋、内腹斜筋)、大殿筋、ハムストリングス
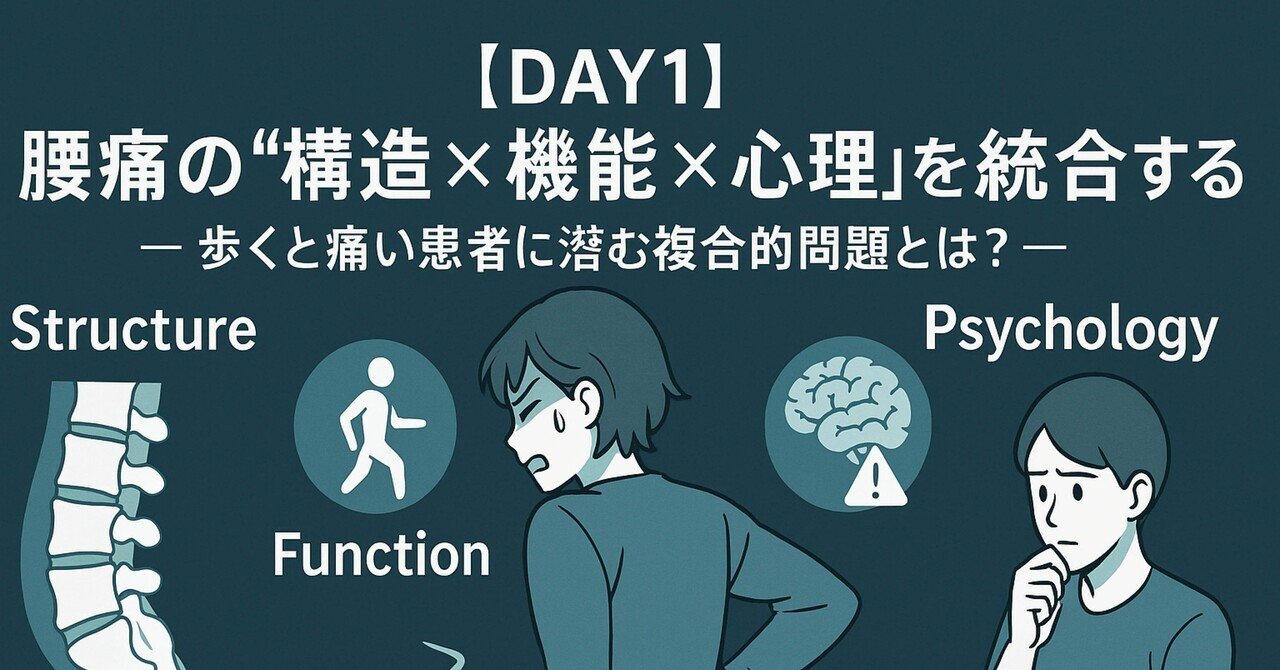
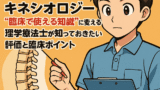
表層で終わらせない!理学療法士の姿勢・動作評価プロセス
問診で得た情報(痛みの部位、時間帯、増悪・寛解因子など)を基に、以下の評価を通じて機能障害の仮説を立て、検証していきます。
Step 1: 静的姿勢評価(Static Posture Assessment)
矢状面、前額面から以下のポイントを観察し、上記姿勢パターンに分類するだけでなく、「なぜそのアライメントになっているのか」を考えます。
- 矢状面
- 重力線とランドマークの関係: 耳垂-肩峰-大転子-膝関節前部-外果前方を結ぶ線からの逸脱を確認。
- 骨盤の傾き: ASISとPSISの高さ関係から前傾・後傾を評価。
- 胸椎・腰椎の弯曲: 過後弯、過前弯、平坦化はないか。
- 隣接関節のアライメント: 股関節、膝関節、足関節の代償パターンは?(例:骨盤後傾に伴う股関節伸展・膝屈曲など)
- 前額面
- 左右の肩の高さ、肩甲骨の位置(内外転、上下方回旋)
- 骨盤の高さ(腸骨稜)、Trendelenburg徴候の有無
- ウエストラインの非対称性
- 下肢アライメント(内外反膝、足部回内外)
Step 2: 動的評価・動作分析(Dynamic Movement Assessment)
静的評価で得た仮説を、実際の動きの中で検証します。腰部だけでなく、胸椎と股関節の機能が腰椎の代償運動を生むケースは非常に多いため、重点的に評価します。
- 体幹の分節的な動き
- 前屈/後屈: 腰椎-骨盤リズムはスムーズか?特定の分節での過剰な動き(ヒンジモーション)はないか?後屈時に胸椎伸展が出ているか、腰椎の過伸展で代償していないか?
- 機能的動作
- スクワット: 股関節・足関節の可動性制限により、腰椎が過度に屈曲(Butt wink)していないか?
- 片脚立位: 骨盤の水平保持は可能か?中殿筋の機能不全(Trendelenburg徴候)や体幹側屈による代償はないか?
- 歩行: 立脚中期での股関節伸展は十分か?腸腰筋の短縮により骨盤前傾・腰椎前弯が増強していないか?
Step 3: 理学所見の聴取(Physical Examination)
動作分析で見られた機能不全の原因を、徒手的な評価でさらに絞り込みます。
- 関節可動域(ROM-T)
- 胸椎: 伸展・回旋可動性。胸椎伸展制限は、リーチ動作や体幹伸展時に腰椎の過伸展を招く。
- 股関節: 屈曲、伸展(Thomas test)、内外旋。特に股関節伸展制限は、立位・歩行時の腰椎過伸展の最大の原因の一つ。
- 足関節: 背屈制限(Knee to wall test)。歩行時の代償として下腿の内旋や骨盤の過剰な回旋を引き起こす。
- 筋力テスト(MMT)
- コア(インナーユニット): 腹横筋(ドローイン)、多裂筋の収縮を触診で確認。
- 抗重力伸展筋: 大殿筋、中殿筋の筋力と収縮タイミングを評価。これらの弱化は骨盤の不安定性や腰椎への過剰な負荷に直結する。
- 筋・筋膜の柔軟性/伸張性テスト
- ハムストリングス(SLR)、大腿直筋(Ely test)、大腿筋膜張筋(Ober test)、梨状筋など、骨盤アライメントに影響を与える筋群を評価。
臨床推論の実践:評価結果を統合し、治療仮説を立てる
評価で得られた複数の情報を繋ぎ合わせ、患者個別の「痛みのメカニズム」をストーリーとして構築します。
【臨床推論の例:デスクワーカーの慢性腰痛】
- 問診: 長時間座位後の立ち上がり、歩き始めに腰部中央に痛み。
- 静的評価: Lordosis姿勢(骨盤前傾、腰椎過前弯)。
- 動的評価: 歩行立脚中期で腰椎の過伸展が著明。
- 理学所見:
- Thomas test 陽性(股関節伸展制限)
- 大殿筋・腹筋群のMMT低下(3/5レベル)
- 腸腰筋・腰部脊柱起立筋に圧痛と過緊張
▼ 統合と解釈(クリニカルリーズニング)
長時間の座位(股関節屈曲位)により腸腰筋が短縮
→ 立ち上がり・歩行時に必要な股関節伸展が制限される
→ 代償として骨盤前傾と腰椎過伸展が生じる(Lumbopelvic rhythmの破綻)
→ 腰椎椎間関節への圧迫ストレスが持続的に加わり、痛みが発生
→ さらに、腹筋群・殿筋群の弱化がこの代償パターンを助長している(Force coupleの不均衡)
▼ 治療アプローチへの展開
この推論に基づけば、ただ腰をマッサージするのではなく、
- 腸腰筋のリリースとストレッチ(股関節伸展可動域の改善)
- 大殿筋・腹横筋の選択的な筋力強化(骨盤後傾方向への安定化)
- 腰椎と股関節の分離運動の学習(正しい動作パターンの再教育)
といった、根本原因にアプローチする治療プログラムが立案できます。
まとめ:個別性の高い評価こそ、セラピストの価値
腰痛患者の姿勢は千差万別です。Sway-backやFlat-backといった典型的なパターンに当てはめるだけでなく、**「なぜ、この患者さんはこの姿勢戦略をとらざるを得ないのか?」**という視点を常に持つことが重要です。
今回ご紹介した評価の視点や臨床推論のプロセスは、その「なぜ?」を解き明かすための強力なツールとなります。明日からの臨床で、ぜひ一つでも多くの視点を取り入れ、パターン化した評価から脱却してみてください。それが、患者さんの症状を根本から改善に導く第一歩となるはずです。