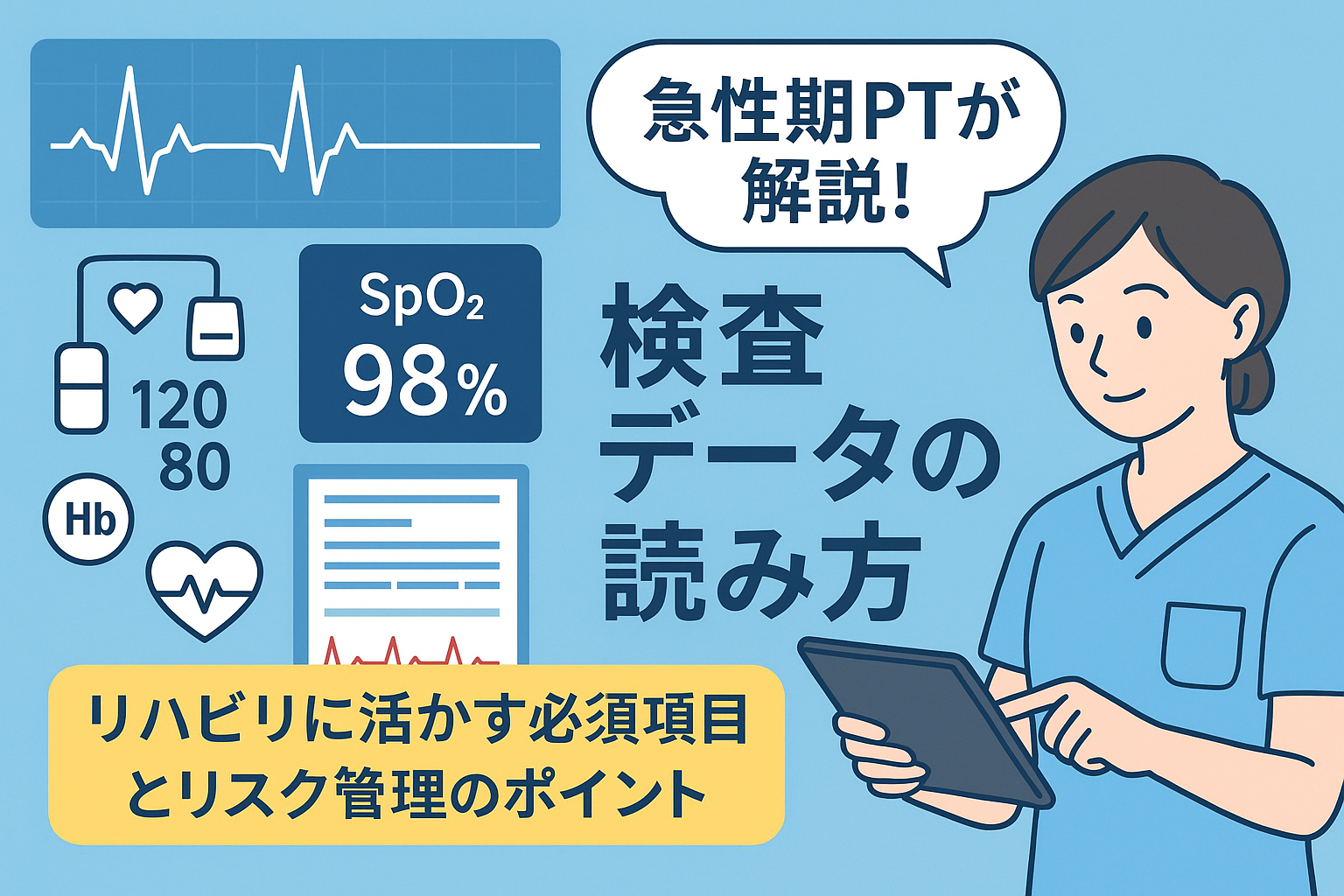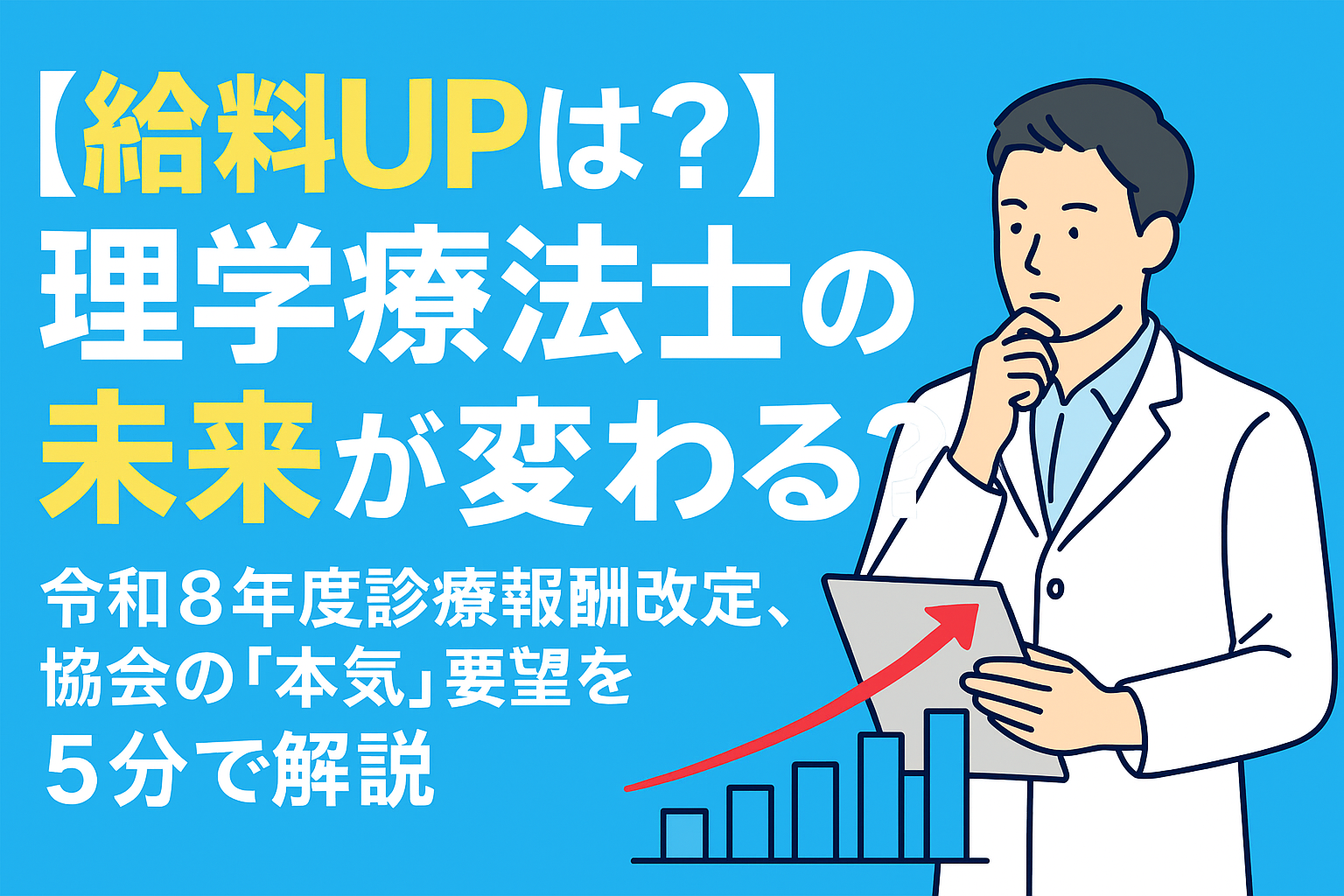はじめに
「今日の患者さん、リハビリを進めても大丈夫かな…?」
急性期病院で働く理学療法士(PT)なら、誰もが一度はこんな不安を感じたことがあるのではないでしょうか。その判断、経験や感覚だけに頼っていませんか?
こんにちは。急性期病院で勤務している理学療法士です。
今回は、若手PTや学生さんが自信を持ってリハビリを提供するために、必ず押さえるべき検査データの読み方と、リハビリへの活かし方について解説します。
検査データは、リハビリの「Go/Stop」を判断するだけでなく、リハビリの「質」と「安全性」を飛躍的に高めるための”羅針盤”となり得ます。
この記事が、明日からの臨床で、自信を持って患者さんの状態を説明し、適切なリハビリを計画できるようになる一助となれば幸いです。
\臨床理学Labでは?/
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

なぜ理学療法士(PT)が検査データを読む必要があるのか?
私たちPTの役割は、ただ運動を指導することではありません。患者さんの全身状態を正確に把握し、安全な範囲で最大限の効果を引き出すことが求められます。
特に状態が変動しやすい急性期では、検査データは患者さんの内部で起きている変化を客観的に示してくれる唯一の手がかりです。検査データを読めずにリハビリを行うことは、いわば「地図を持たずに嵐の海へ出る」ようなもの。リスクを察知し、安全な航路(リハビリ計画)を示すために、検査データを読み解くスキルは不可欠なのです。
【大前提】検査データと向き合う3つの心構え
具体的な項目を見る前に、検査データと向き合う上での大切な心構えを3つお伝えします。これを知っているだけで、数値に振り回されなくなります。
- 「点」ではなく「線」で見る
今日のデータ(点)だけを見るのではなく、昨日から今日への「変化(トレンド)」を捉えましょう。「CRPが10」という情報だけでは不十分です。「昨日20→今日10」なら回復傾向、「昨日5→今日10」なら悪化傾向と、意味が全く異なります。 - 「木」だけでなく「森」を見る
データ(木)だけに囚われず、患者さんの表情、訴え、バイタルサインなど全身状態(森)と合わせて「統合的に解釈」しましょう。数値が悪くても患者さんが元気な場合もあれば、その逆もあります。 - 「基準値」は絶対ではない
基準値はあくまで一般的な目安です。年齢、性別、基礎疾患(腎不全、肝硬変など)によって、患者さん個々の「許容範囲」は異なります。その患者さんにとってのベースラインはどこか、意識することが重要です。
【保存版】急性期PTが必ず押さえるべき検査データ「基本セット7選」
それでは、リハビリ介入前に必ずチェックすべき「基本セット」を見ていきましょう。ここでは、特にリハビリとの関連が深い7つの項目を厳選しました。
1. 【炎症・感染】CRP / 白血球数(WBC)
| 項目 | 基準値(目安) |
| CRP | 0.3 mg/dL 以下 |
| WBC | 3,300~8,600 /μL |
- 何がわかる?
体内の「炎症」の強さや「感染症」の有無を示します。術後や肺炎などで数値が上昇します。 - リハビリへの活かし方(リスク管理と介入のヒント)
- 高値・上昇傾向の場合: 炎症の活動期であり、発熱や倦怠感を伴いやすい状態です。無理な運動は避け、安静度や運動負荷量を慎重に検討します。
- ピークアウト・低下傾向の場合: 回復期に入ったサイン。解熱し、全身状態が安定していれば、リハビリの負荷量を上げる良いタイミングです。
2. 【貧血】ヘモグロビン(Hb) / ヘマトクリット(Ht)
| 項目 | 基準値(目安) |
| ヘモグロビン(Hb) | 男性: 13.7~16.8 g/dL女性: 11.6~14.8 g/dL |
- 何がわかる?
全身への「酸素運搬能力」の指標です。Hbは血液中の赤血球に含まれるタンパク質で、酸素と結合して全身に運びます。数値が低い状態が「貧血」です。 - リハビリへの活かし方(リスク管理と介入のヒント)
- 離床の目安: 一般的に「Hb 8.0g/dL」が離床を開始する一つの目安とされますが、7g/dL台でもバイタルが安定していれば離床を進めるケースもあります(必ず医師に確認!)。
- 症状の観察: Hbが低いと、少し動いただけでもめまい・動悸・息切れ・強い疲労感が出やすくなります。運動中はSpO2(酸素飽和度)や脈拍、患者さんの表情を注意深く観察しましょう。
- 輸血後: 輸血後はHb値が改善し、運動耐容能(持久力)が向上する可能性があります。リハビリ負荷量を見直すチャンスです。
3. 【栄養状態】アルブミン(Alb)
| 項目 | 基準値(目安) |
| アルブミン(Alb) | 4.1~5.1 g/dL |
- 何がわかる?
約2~3週間の長期的な**「栄養状態」**を示します。Albは体力、筋力、創傷治癒(傷の治り)に深く関わります。 - リハビリへの活かし方(リスク管理と介入のヒント)
- 低アルブミン血症(3.5 g/dL未満など)の場合:
- 筋力が低下しやすく、疲れやすい。
- 浮腫(むくみ)が起こりやすい。
- 褥瘡(床ずれ)のリスクが高い。
- 高負荷な筋力トレーニングは避け、ADL(日常生活動作)中心の練習を計画します。栄養科と連携し、栄養状態の改善をチームで働きかけることが重要です。
- 低アルブミン血症(3.5 g/dL未満など)の場合:
4. 【腎機能】BUN / クレアチニン(Cre)
| 項目 | 基準値(目安) |
| BUN(尿素窒素) | 8~20 mg/dL |
| Cre(クレアチニン) | 男性: 0.65~1.07 mg/dL<br>女性: 0.46~0.79 mg/dL |
- 何がわかる?
腎臓の**「老廃物排泄能力」**を示します。腎機能が低下すると、これらの数値が上昇し、体内に毒素が溜まりやすくなります。 - リハビリへの活かし方(リスク管理と介入のヒント)
- 高値の場合: 倦怠感、疲労感、吐き気などの症状(尿毒症症状)が出やすいです。患者さんの訴えに耳を傾け、その日の体調に合わせてリハビリ内容を調整します。
- 透析患者さんの場合: 透析後は老廃物や余分な水分が除去され、体が楽になります。リハビリは、血圧が安定しやすい透析翌日に行うのがベストタイミングと言われています。
5. 【凝固・線溶系】PT-INR / D-dimer
| 項目 | 基準値(目安) |
| PT-INR | 0.85~1.15(ワーファリン内服中は2.0~3.0でコントロール) |
| D-dimer | 1.0 μg/mL 未満 |
- 何がわかる?
PT-INRは血液の「固まりにくさ(出血しやすさ)」、D-dimerは体内で「血栓(血の塊)が溶けた量」を示します。 - リハビリへの活かし方(リスク管理と介入のヒント)
- PT-INR高値の場合: 血液がサラサラで出血しやすい状態です。転倒による内出血や、関節内出血のリスクが高まります。環境設定を工夫し、転倒予防を徹底しましょう。
- D-dimer高値の場合: 深部静脈血栓症(DVT)の可能性があります。足の腫れ・痛み・色の変化などを確認し、疑わしい場合はすぐに医師・看護師に報告!安易なマッサージは血栓を肺に飛ばす(肺塞栓)危険があるため絶対に禁忌です。
6. 【心機能】BNP
| 項目 | 基準値(目安) |
| BNP | 18.4 pg/mL 以下 |
- 何がわかる?
心臓への**「負担」**の大きさを示します。心不全の重症度を評価する代表的な指標です。 - リハビリへの活かし方(リスク管理と介入のヒント)
- 高値の場合: 心臓に負担がかかっている状態であり、心負荷に弱いです。少しの運動で息切れや疲労が出やすくなります。
- 運動強度は慎重に設定し、息切れ、動悸、むくみの悪化などの心不全増悪のサインを見逃さないようにしましょう。
7. 【電解質】カリウム(K)
| 項目 | 基準値(目安) |
| カリウム(K) | 3.6~4.8 mEq/L |
- 何がわかる?
筋肉や神経の働きを調整する重要なミネラル。特に心臓の筋肉に影響を与え、不整脈のリスクに直結します。 - リハビリへの活かし方(リスク管理と介入のヒント)
- 高カリウム血症・低カリウム血症ともに危険! どちらも致死性の不整脈を引き起こす可能性があります。
- リハビリ前に必ず数値をチェックしましょう。特に腎機能が悪い患者さんや、利尿薬を使用している患者さんは値が変動しやすいので要注意です。介入中はモニター心電図の波形にも気を配りましょう。
他にもこんな記事があります!
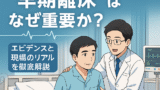
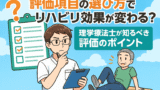
【症例で学ぶ】検査データをリハビリ計画にどう活かすか?
では、実際の症例を通して、検査データをどうリハビリに活かすか見てみましょう。
【症例】78歳女性、既往に心不全。転倒による大腿骨頸部骨折で手術(人工骨頭置換術)。
- 術後1日目:
- 検査データ: Hb 8.2g/dL、CRP 3.5mg/dL、BNP 350pg/mL
- 解釈とリハビリ計画:
- 貧血(Hb↓)と心不全(BNP↑)があるため、急な離床はリスクが高い。
- 炎症(CRP↑)が始まっている。
- 計画: まずはベッド上での足関節の自動運動(DVT予防)、深呼吸の練習から開始。バイタルサインの変動に注意。
- 術後3日目:
- 検査データ: Hb 9.0g/dL、CRP 15.0mg/dL、BNP 350pg/mL
- 解釈とリハビリ計画:
- Hbは改善傾向。炎症はピークだが、発熱なくバイタルは安定。
- 計画: 貧血と心不全のリスクは継続するが、離床を進めるタイミング。疼痛管理を十分に行い、息切れや動悸に注意しながら、端座位や車椅子移乗の練習を開始。
- 術後7日目:
- 検査データ: CRP 5.0mg/dL、Alb 2.5g/dL
- 解釈とリハビリ計画:
- 炎症は低下傾向で回復期へ。しかし、低栄養(Alb↓)が顕著。
- 計画: 体力や筋力の回復が遅れる可能性を考慮。平行棒内での立位・歩行練習を実施しているが、負荷量は慎重に調整。低栄養状態について、医師・看護師・栄養士と情報共有し、チームでアプローチする必要がある。
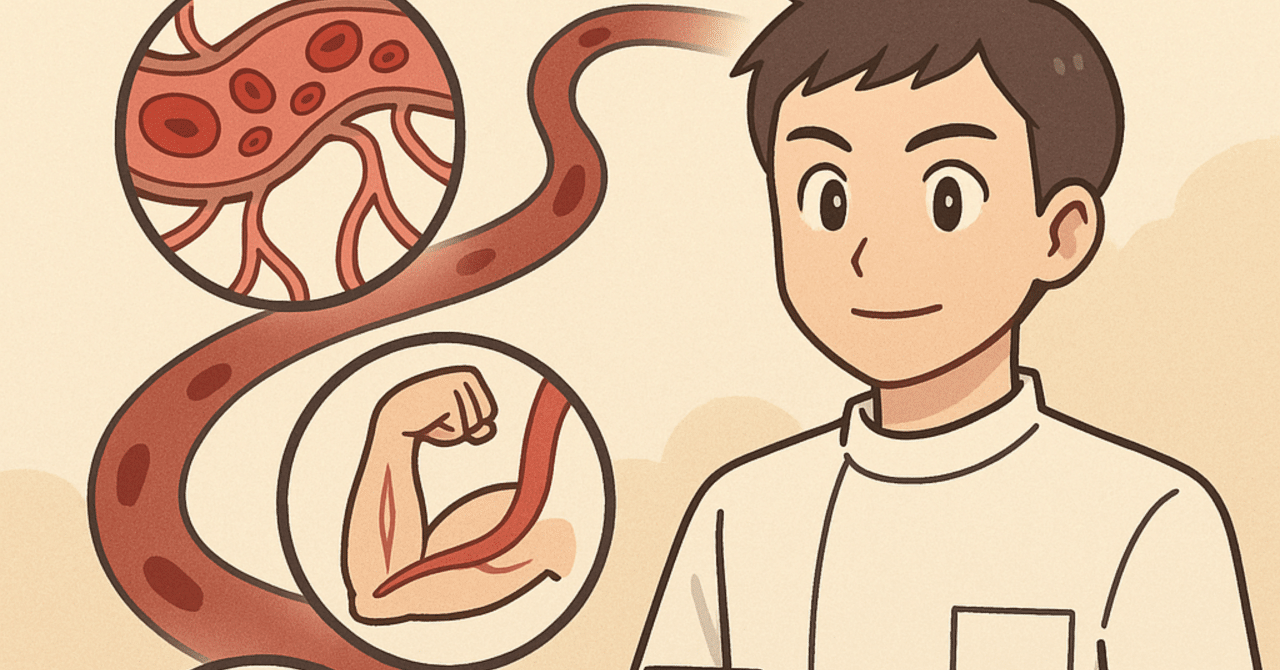
まとめ:検査データを味方につけて、信頼されるセラピストへ
今回は、急性期PTが押さえるべき検査データの基本セットと、リハビリへの活かし方を解説しました。
- 検査データは患者さんの状態を知るための”羅針盤”
- 「点ではなく線」「木ではなく森」「基準値は絶対ではない」の3つの心構えを持つ
- 基本セット7選(炎症、貧血、栄養、腎機能、凝固、心機能、電解質)は必ずチェック
検査データは、医師や看護師との**「共通言語」**でもあります。数値の変化からリスクを察知し、「〇〇の数値がこう変動しているので、本日のリハビリは△△に注意して進めます」と論理的に説明できれば、チームからの信頼は格段に上がります。
まずは明日、担当患者さんの「基本セット7選」を確認し、その数値がリハビリにどう影響するかを自分の言葉で考えてみてください。その一歩が、あなたを「信頼されるセラピスト」へと成長させてくれるはずです。