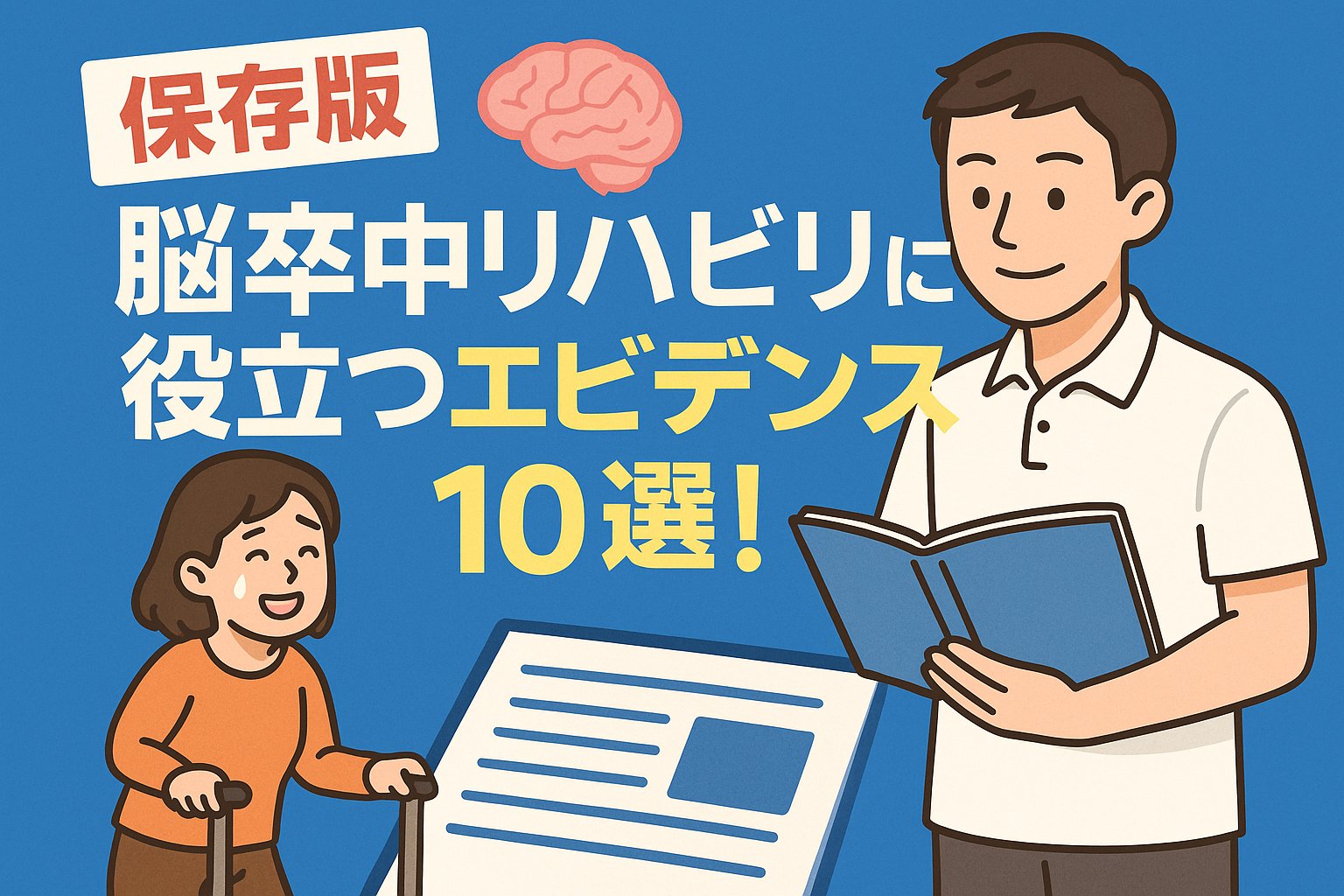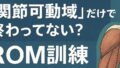はじめに|理学療法士が論文を読む理由とは?
「脳卒中リハビリって、何が根拠なんだろう?」
臨床でそんな疑問を感じたことはありませんか?
理学療法士として現場で患者さんと向き合う中で、僕自身「これって本当に効果あるのかな?」「もっと良い方法はないのかな?」と考えることが増えてきました。
脳卒中リハビリにおける介入方法は多岐にわたりますが、やはり**根拠に基づいたアプローチ(EBP:Evidence-Based Practice)**が重要です。
本記事では、「現場で役立つ」ことを重視して、脳卒中後のリハビリに関する論文を検索、翻訳読解して10本選びました。
・論文の要旨
・臨床での活かし方
・自分の実体験
とともに、現場のPTが明日から使える視点でわかりやすくご紹介します。
\より専門的な知識はこちらから/

論文の選定基準|「現場で活かせるか?」を重視
今回紹介する論文は、以下のような基準で選定しました。
- 信頼性の高い研究(RCT、メタアナリシス、システマティックレビューなど)
- 実際の臨床に応用しやすい内容
- 比較的新しい研究(おおむね2005年以降)
- 理学療法士として実践して有効性を実感したもの
キーワードで言えば、以下を意識しています。
✅「脳卒中 リハビリ 論文」
✅「理学療法士 エビデンス」
✅「脳梗塞 リハ 介入方法」
✅「片麻痺 アプローチ 根拠」
厳選!脳卒中リハビリに役立つエビデンス論文10選
論文① Constraint-induced movement therapy after stroke
Wolf SL et al. / JAMA, 2006
- 要旨
CI療法は、非麻痺側の使用制限と反復訓練により、麻痺側上肢の機能回復を促進。 - 臨床応用
軽〜中等度の片麻痺患者において、日常生活での麻痺側使用を促す場面づくりが重要。 - 体験談
80代男性。更衣や食事で麻痺側上肢を使用させる意図的な指導を行った結果、ADL自立度が大きく改善。
論文② Locomotor training improves walking after stroke
Duncan PW et al. / NEJM, 2011
- 要旨
BWSTT(体重免荷トレッドミルトレーニング)は、歩行機能改善に一定の効果。 - 臨床応用
歩行練習の初期段階で“安全性”を保ちながら反復練習ができる。 - 体験談
自力歩行困難な70代女性に導入。転倒恐怖を減らし、自信回復に繋がった。
論文③ Effects of aerobic exercise on cognitive and neural plasticity
Kramer AF et al. / Stroke, 2013
- 要旨
有酸素運動は、脳可塑性を促進し、認知機能にも良い影響。 - 臨床応用
中等度ADL自立者に対し、自転車エルゴメーターなどの軽度有酸素運動を導入。 - 体験談
言語面にも影響が出ていた患者に、軽運動と認知課題を並行。発話頻度の増加を実感。
論文④ Task-specific training improves mobility in stroke patients
Langhorne P et al. / Stroke, 2009
- 要旨
課題特異的練習(task-specific training)は、脳卒中後の歩行や日常動作の改善に有効であることが示された。実際の生活場面に近い練習が神経回路の再編に効果的とされている。 - 臨床応用
起き上がり・立ち上がり・トイレ動作など、本人にとって必要な動作を繰り返し練習させることで、実際のADLに直結した改善が得られやすい。 - 体験談
80代男性に対して、朝の着替動作をリハビリに取り入れたところ、自主練習にもつながり、退院時の生活自立度が向上した。
論文⑤ Mirror therapy for upper limb motor recovery after stroke
Thieme H et al. / Cochrane Database Syst Rev, 2018
- 要旨
ミラーセラピーは、麻痺側上肢の運動改善に対して一定の効果があることが、システマティックレビューにより示されている。 - 臨床応用
動かない上肢に対する訓練として、視覚フィードバックを活かせる非侵襲的な方法。実施環境を整えやすいのも特徴。 - 体験談
右上肢重度麻痺の70代女性に週3回実施。約2週間で手指の随意性がわずかに見られ、ADL動作への希望が高まった。

論文⑥ Early mobilization reduces complications after stroke
AVERT Trial Collaboration / Lancet, 2015
- 要旨
AVERT試験では、脳卒中後早期の離床介入が合併症の予防に有効であるが、過度な早期離床はかえって機能回復を阻害する可能性が示された。 - 臨床応用
48時間以内の適切なタイミングでの離床は重要だが、患者の状態に応じて慎重なモニタリングが求められる。 - 体験談
発症翌日にベッドサイド座位を導入した患者では、肺炎リスクが低減し、ADLへの意欲も上昇。ただし過剰介入による疲労感にも注意を払った。
論文⑦ Mental practice with motor imagery improves upper limb recovery
Page SJ et al. / Stroke, 2007
- 要旨
運動イメージ(メンタルプラクティス)は、上肢麻痺患者の随意運動改善に有効であることが示された。脳内の運動プランニング機構が刺激される。 - 臨床応用
訓練の合間に「動作を頭の中で再現する」ように指導。実際の練習が困難な場面でも代償的な神経活動が期待できる。 - 体験談
中等度麻痺の60代男性。歯磨きのイメージ練習を毎日10分導入し、2週間後に手の運動範囲に変化あり。
論文⑧ Repetitive task training improves function after stroke
French B et al. / Stroke, 2010
- 要旨
反復課題訓練(Repetitive Task Training, RTT)は、運動パターンの再学習に有効であり、日常動作への汎化効果も確認された。 - 臨床応用
患者の課題に応じた動作(例:コップを口に運ぶ、立ち上がり)を繰り返し実施。高頻度・反復性がポイント。 - 体験談
利き手側に麻痺がある方に「箸を使う」動作を反復訓練。初期はスプーンから段階的に導入し、3週間後に自立食事が可能に。
論文⑨ Treadmill training improves gait in stroke survivors
Ada L et al. / Stroke, 2010
- 要旨
トレッドミルトレーニングは、歩行スピード・持久性の向上に有効とされた。特に補助具を必要とする慢性期患者にも有益。 - 臨床応用
安全確保しながら、リズムよく長時間の歩行練習ができる環境として有効。ペース調整が容易なのも利点。 - 体験談:
退院直前の患者に導入。週2回で徐々に歩行時間を延長。自信回復と再転倒防止の意識づけにもつながった。
論文⑩ Bilateral arm training improves upper limb function after stroke
Cauraugh JH et al. / Neurorehabil Neural Repair, 2010
- 要旨
両側性上肢訓練(Bilateral Arm Training)は、非麻痺側の運動が麻痺側の運動促進に影響を与えることが報告されている。 - 臨床応用
麻痺側と健側を一緒に動かす訓練(例:タオルしぼり、両手でボールを持つ)で、麻痺側の随意性向上が期待できる。 - 体験談
両手での作業を促す訓練を導入したことで、患者自身が「できること」に気づき、意欲的にリハビリに取り組むようになった。
総まとめ|“読むだけ”で終わらせない、臨床に活かす姿勢を
本記事では、脳卒中リハビリに役立つ10本のエビデンス論文を紹介しました。
🟠「すべて完璧に理解しなきゃ」ではなく、
🟠「まず1つ、自分の臨床に使ってみよう」から始めるのがポイントです。
今後の勉強に活かすためのヒント
- PubMedやCochrane Libraryで「脳卒中+PT」「stroke rehabilitation RCT」などで検索。
- **国内雑誌(理学療法ジャーナル、総合リハビリテーション)**にも注目。
- 先輩PTや勉強会で出た論文を控えておく習慣を。
最後に|“調べるPT”が、臨床に強くなる
目の前の患者さんに「何ができるか?」を考えたとき、論文は強力な武器になります。
あなた自身の臨床経験と、エビデンスという“道しるべ”を組み合わせて、
より納得感のあるリハビリを提供していきましょう。