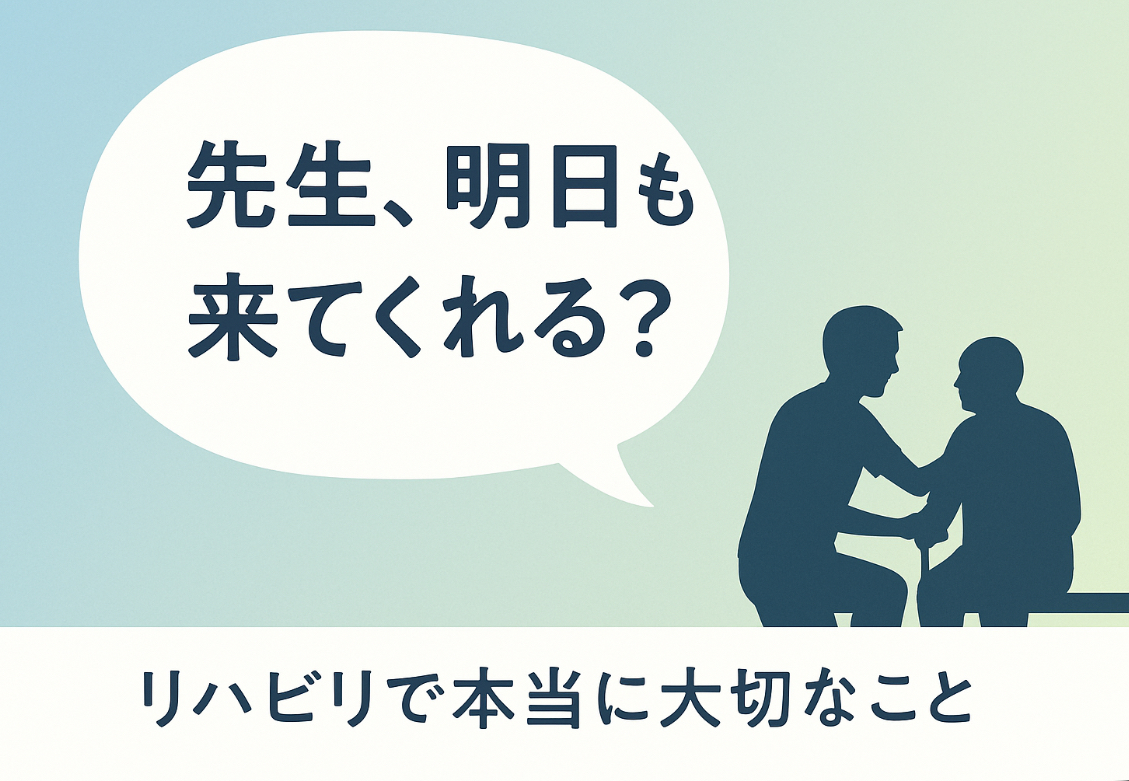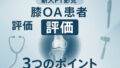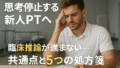その一言が、私の“当たり前”を壊してくれた
リハビリの現場に立つ私たちは、常に「制度」や「研鑽」という言葉と共にあります。
疾患別リハビリの算定日数、診療報酬のルール、回復期や生活期といった病期ごとの枠組み。そして、セラピストとしての日々の勉強や技術の追求――。
これらは、質の高いリハビリを提供するために不可欠で、プロとして意識するのは当然のことです。
しかし、その「当たり前」は、あくまで私たち“提供する側”の視点に過ぎないのかもしれません。
ある日、私が担当していた患者さんから、忘れられない一言をかけられました。
「先生、制度のことはよくわからないけど……明日もリハビリしてくれるんですよね?」
たった一言でしたが、まるで頭を殴られたような衝撃を受けました。
私たちが必死に考えている「正しい算定」や「より良い技術」は、患者さんには見えていない。患者さんにとっての現実は、もっとシンプルで、切実なものです。
この記事では、日々の業務に追われる中で見失いがちな「患者さんが本当に求めていること」について、私の経験を元にお伝えします。もしあなたが「今の関わり方で良いのだろうか?」と少しでも悩んでいるなら、きっとヒントが見つかるはずです。
患者さんが求めているのは「正しいリハビリ」ではなく「信頼できる伴走者」
結論からお伝えします。
私たちがどれだけ制度を理解し、専門知識を深めても、それだけでは患者さんの心には届きません。
患者さんがリハビリに本当に求めているのは、制度に則った“正しいリハビリ”そのものではなく、「今、自分のために全力を尽くしてくれる人がいる」という安心感であり、「自分は一人じゃない」と感じられる希望です。
制度や研鑽は、安全で効果的なリハビリを提供するための重要な“土台”です。しかし、その土台の上に何を築くのかが、セラピストとしての価値を決めると、私は考えています。
なぜ「制度」や「研鑽」だけでは、患者さんの心に届かないのか?
もちろん、制度や研鑽を軽視して良いわけではありません。これらは私たちの仕事を支える両輪です。
- セラピスト側の事情
- 制度の理解: 診療報酬に沿って正しく運用できなければ、病院や施設の経営が成り立たず、リハビリ自体を提供し続けられません。
- 技術の研鑽: 知識や技術を磨き続けなければ、患者さんに安全で効果的なリハビリを提供できません。
これらを追求するのは、プロとして当然の責任です。しかし、この「プロとしての責任」と「患者さんの実感」との間には、大きなギャップが存在します。
- 患者さん側から見た現実
- 算定区分や病期は、患者さんの日常の関心事ではありません。「昨日より痛みが楽になるか」「家に帰れるか」という目の前の現実がすべてです。
- 私たちがどれだけ学会に参加し、専門書を読んでいるかは、直接見えるものではありません。その学びが、目の前のリハビリにどう活かされているかでしか伝わらないのです。
この埋めがたいギャップを繋ぐのが、専門家としての知識や技術を超えた「人としての関わり方」です。
患者さんの言葉の奥にある「3つの本当の願い」
患者さんが口にする「歩けるようになりたい」「痛みをなくしたい」といった言葉。その奥には、もっと具体的で、生活に根ざした「本当の願い」が隠されています。
①【生活の再建】自分の人生を取り戻したい
リハビリの目標は、単なる機能回復ではありません。患者さんが取り戻したいのは、病や怪我をする前の「当たり前の日常」です。
- 「歩けるようになりたい」 → 「もう一度、自分の足でスーパーに買い物に行きたい」
- 「手が動くようになりたい」 → 「もう一度、箸を持って家族と同じ食事がしたい」
- 「話せるようになりたい」 → 「もう一度、孫と電話で笑い合いたい」
私たちが向き合うべきなのは、この具体的な生活シーンであり、人生そのものなのです。
②【不安の共有】この気持ちを分かってほしい
体の自由が利かない状況は、計り知れない不安や焦りを生みます。
- 「痛い」という訴えの裏には → 「このまま家族に迷惑をかけ続けるのではないか」という不安
- 「やる気が出ない」という言葉の背景には → 「本当に良くなるのだろうか」という焦り
患者さんは、ただ痛みや症状を訴えているのではありません。その奥にある言葉にならない不安を誰かに受け止めてほしい、と願っています。
③【孤独からの解放】一人じゃないと感じたい
リハビリは、時に孤独な闘いです。昨日できたことが今日できない、先の見えない不安。そんな中で、セラピストは唯一無二の「伴走者」になれる存在です。
「この人は自分のことを分かってくれている」
「この人と一緒なら頑張れる」
そう感じてもらえること自体が、何よりの治療になるのです。
明日から実践できる!患者さんと心で繋がるための5つのアクション
では、具体的にどうすればいいのでしょうか。特別な技術は必要ありません。大切なのは、日々の関わりの中での少しの意識です。
- □ 「今日の調子はどうですか?」と、目を見て本気で尋ねる。
作業的に聞くのではなく、「あなたの今日の状態を心から知りたい」という気持ちを込めてみましょう。 - □ どんなに小さな「できたこと」も見逃さず、一緒に喜ぶ。
「指が少し動きましたね!」「昨日より長く座れましたね!」と、変化を言葉にして共有することで、患者さんは希望を見出すことができます。 - □ 評価や訓練だけでなく、ただ話を聞く「余白の時間」を意識的につくる。
世間話や愚痴の中に、その人の大切な価値観や本当の願いが隠れていることは少なくありません。 - □ 「できないこと」を指摘するより、「できるようになったこと」を一緒に数える。
リハビリは減点法ではなく加点法。「これもできるようになった」という積み重ねが、自己肯定感を育みます。 - □ 専門用語を自分の言葉に翻訳し、分かりやすく伝える努力をする。
「大腿四頭筋の筋力低下が…」ではなく、「太ももの前の、立ち上がる時に使う筋肉が少し弱っていますね。ここを鍛えましょう」と伝えるだけで、患者さんの理解と納得度は大きく変わります。
【コラム:現場のリアルな葛藤】
理想を語っても、現場は綺麗事だけでは回りません。診療報酬の制約でリハビリを打ち切らざるを得ない時。「本当は制度のせいなのに…」と思いつつ、曖昧な説明をして患者さんの残念そうな顔を見るのは、本当に胸が痛みます。
忙しさのあまり、記録や評価に追われて患者さんの小さな訴えを聞き逃し、「先生、今日は話を聞いてくれるだけで良かったのに」と後から言われて、自分の関わり方を猛省したことも一度や二度ではありません。
しかし、そんな葛藤の中で働く私たちを救ってくれるのも、また患者さんからの言葉です。
「先生と話すと安心する」
「リハビリの時間だけが楽しみです」
これらの言葉は、制度やルールの中で見失いそうになる**「リハビリの本質は、人と人との繋がりの中にある」**ということを、何度でも思い出させてくれるのです。
まとめ:リハビリの未来は、私たち一人ひとりの「姿勢」が創る
制度や研鑽は、私たちがプロとして立つための土台です。この土台がなければ、安全で質の高いリハビリは提供できません。
しかし、患者さんが本当に価値を感じ、心を動かされるのは、その土台の上にある**「あなた」というセラピストの人間性や向き合う姿勢**です。
- 小さな変化を一緒に喜んでくれること。
- 不安や悩みに、ただ耳を傾けてくれること。
- そして、「自分は一人じゃない」と感じさせてくれること。
これこそが、どんな先進的な技術や制度にも勝る、リハビリの核心だと信じています。
最後に、この記事を読んでくださったあなたに問いかけたいと思います。
「患者さんにとって、自分はどんな存在でありたいですか?」
「今日のリハビリの時間を、その人にとってかけがえのないものにできていますか?」
リハビリの未来をつくるのは、新しい制度でもシステムでもありません。それを使いこなし、目の前の患者さんと真摯に向き合う、私たち一人ひとりの「姿勢」です。その積み重ねが、患者さんの人生をより豊かにしていくのだと、私は信じています。
\臨床推論を一緒に鍛えていきませんか?/
「なぜこの痛みが起きたのか?どんな治療が効果的なのか?」
「どんな視点で評価すればよかったのか?」
「論文をどんな風に臨床に活かせばいいのか?」
そんな問いに一緒に向き合いながら、臨床で役立つ“推論の引き出し”を増やしていく場を、メンバーシップ限定コンテンツとしてご用意しています。
🔸 メンバー限定で読める「評価→推論→介入→再考察」付きの深掘り症例ノート
🔸 痛みや治療の考え方に特化した臨床推論の解説
🔸 コメント・質問歓迎のクローズドな学びの空間