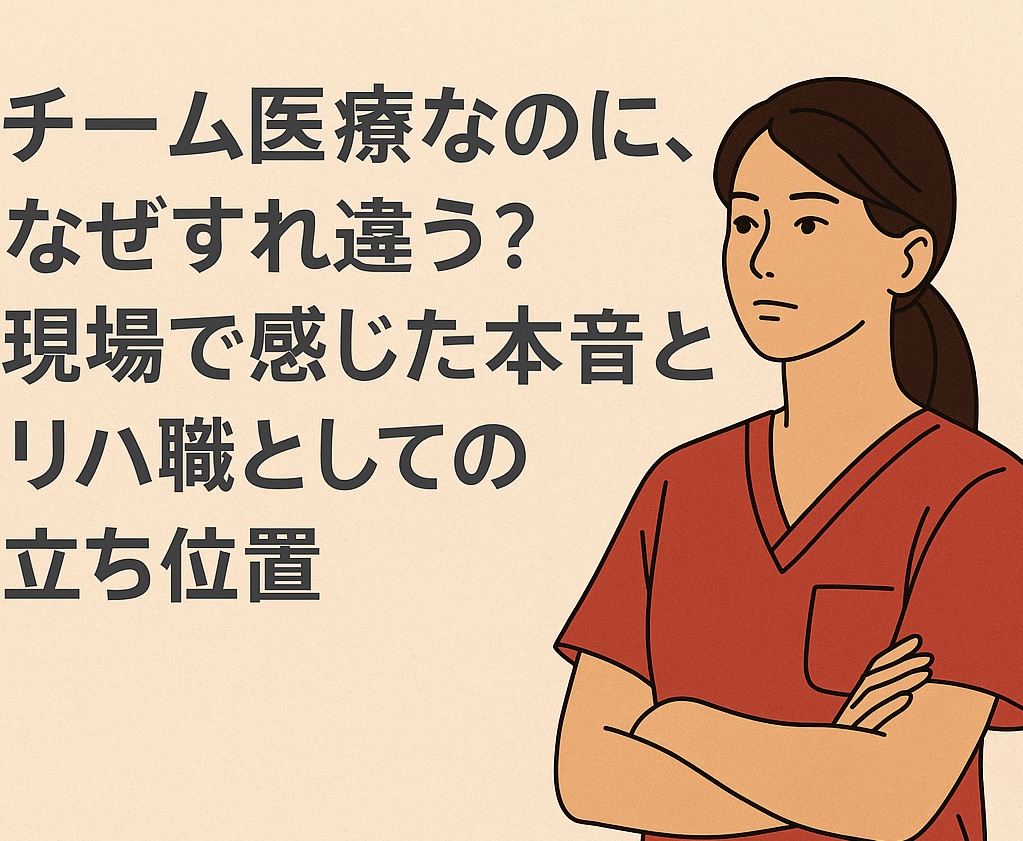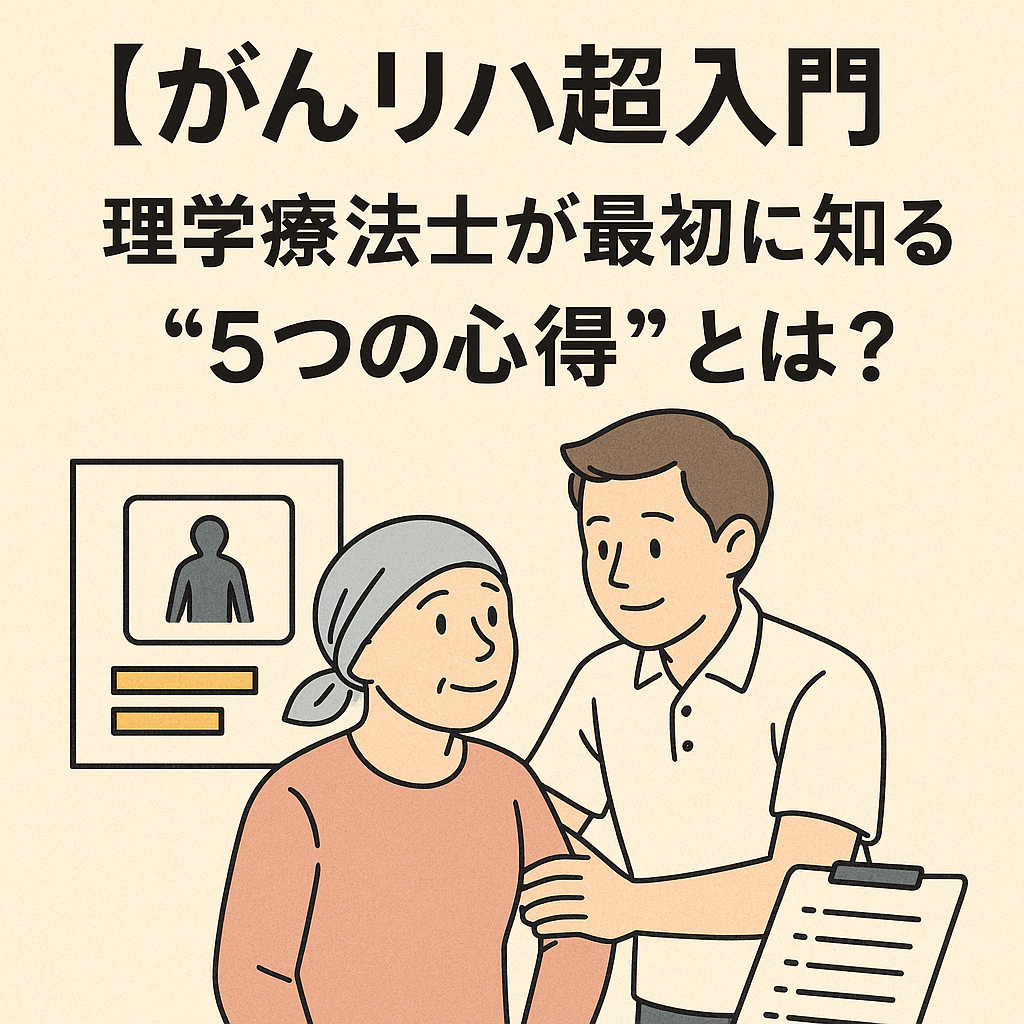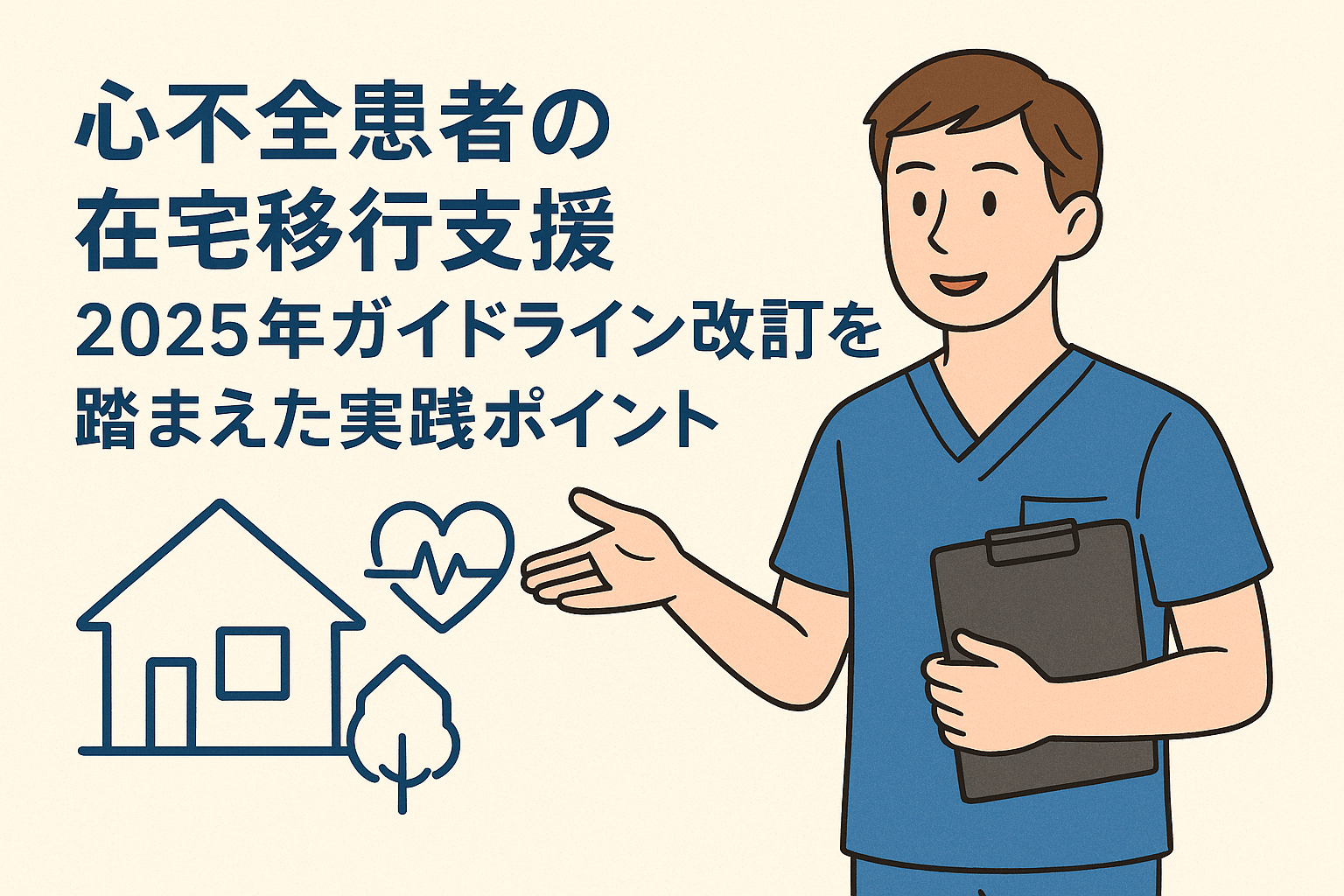【はじめに】
チーム医療の理想と、現場で感じる違和感
「チーム医療」──この言葉は、医療現場で働く誰もが一度は耳にしたことがあるはずです。
医師、看護師、リハビリ職、薬剤師、管理栄養士、ケースワーカー…。
それぞれが対等な専門職として連携し、患者さんの回復に向かって力を合わせる。これが、医療の理想のかたちだと言われています。
しかし実際には、現場で働く中でふとした違和感を覚えることがあります。特に、「看護部はリハよりも多忙で責任が重いのです」という言葉に象徴されるような、すれ違い。
もちろん、すべての看護師さんがそういう考えを持っているわけではありません。
むしろ多くの方は、リハビリ職の努力を尊重し、連携を大切にしてくださっています。
ここで書くのは、あくまで「ごく一部」で起きる摩擦の話です。
でも、その小さな違和感がチーム全体の雰囲気に影響してしまうことも事実。だからこそ、この記事では以下のことを考えてみます。
- どこですれ違いが起きるのか
- リハ職としてどう向き合うべきか
【現場あるある】「看護部はリハより多忙で責任が重い」という主張
ある日、こんな場面に遭遇しました。

看護部はリハビリ職よりも忙しく、責任も重いのです。だから、小さな協力すらできない療法士と、対等に協働するのは無理です。
さらに、こう付け加えられました。

更衣や排泄を済ませたくらいで『万全』だと思うのは浅はかです。こちらは日々、バイタルチェック、内服管理、観察、患者家族対応……ありとあらゆる看護をして、リハビリができるよう整えているんです。
この言葉には、看護師としての誇りと、日々の重圧がにじみ出ています。
その大変さを軽視するつもりは、もちろんありません。ただ、「忙しさ」や「業務量」を持ち出して、専門職同士の対等な関係性を崩してしまう論理展開には、慎重であるべきだと感じました。
【なぜすれ違いが起きるのか?】
現場でこうした摩擦が生まれる理由には、いくつかの背景があると思います。
① 業務量と専門性を混同してしまう
たしかに、看護師の業務は多岐にわたります。
バイタルチェック、清拭、点滴管理、内服指導、患者家族対応──どれも簡単な作業ではなく、高度な知識と判断力を要します。
看護師さんは患者の命を直接預かる場面が多く、24時間体制で業務があり、急変対応や薬剤管理、家族対応など多岐にわたる責任を担っています。その意味では、「多忙で責任が大きい」と感じるのは自然なことです。
一方で、リハビリ職(理学療法士など)も、限られた時間の中でリスク管理をしながら機能回復を促したり、計画的に運動負荷や生活動作訓練を実施し、退院後の生活を見据えた介入もします。
もちろん、患者さんの現段階の全身状態を把握した上で、最大限のパフォーマンスを引き出せるように細心の注意を払って。です。
特に、患者さんの「生活の質」に直結する役割を担っているので、別の角度から大きな責任があるとも言えます。
その点ではまた違った形で深い責任があります。
「業務が多い=専門性が高い」ではない。
「忙しい=対等でない」でもない。
役割が違うだけであり、どちらも医療にとって不可欠な存在です。
業務の多さや負担感を競い合うことは、本来の目的からズレてしまいます。
② 忙しさが感情論を引き起こしやすい
日々、限界まで働いていると、
つい「私たちの方が頑張っているのに!」という気持ちが顔を出してしまうのは人間として自然です。
しかし、感情論に流されると、
本来話し合うべき「患者さん中心の協力体制」が後回しになってしまいます。
忙しいときこそ、冷静なコミュニケーションが必要なのです。
③ 相互理解の欠如
看護師もリハビリ職も、
お互いの専門領域や業務の細かい実態を十分に知らないことがほとんどです。
- リハビリ職が「1単位20分」単位制で働いていること
- 1日の担当は多くて20人超える施設もある
- 身体負荷量や覚醒レベルによってリスク管理しながら実施していること
こうした背景を知らなければ、
「リハはただ座らせて歩かせるだけ」くらいに誤解されても不思議ではありません。
情報共有と理解の積み重ねが、すれ違いを防ぐ鍵になります。
【リハ職としてどう対応するか?】
摩擦に直面したとき、リハ職が心がけるべき姿勢は次の通りです。
① 患者中心に話を戻す

確かに看護師さんの業務の多さや責任の重さは承知しています。
ですが、今この場で一番大事なのは、お互いの負担を比較することではなく、患者さんにとって最善の環境を作ることだと思っています。
感情的に反論せず、
常に「患者さん」という共通ゴールに立ち戻ることで、議論を建設的に整えます。
② 業務量ではなく役割の違いを認め合う
- 看護師には看護師の
- リハビリ職にはリハビリ職の
それぞれの専門性と役割があります。
業務量の多少に優劣をつけるのではなく、
**「違うからこそ、力を合わせる必要がある」**という視点を持つことが大切です。
【まとめ】
本当の「対等なチーム」とは
本当に機能するチームとは、
- 忙しさ比べをせず
- 相手を尊重し
- 患者さん中心で動けるチーム
です。
日々の業務の中で、多少の不満やストレスは誰にでもあります。
でも、そのたびに
「誰が偉いか」「誰が大変か」ではなく、
**「どうすれば患者さんのために最善を尽くせるか」**を問い続ける。
それが、私たちリハビリ職に求められる大人の態度だと思っています。