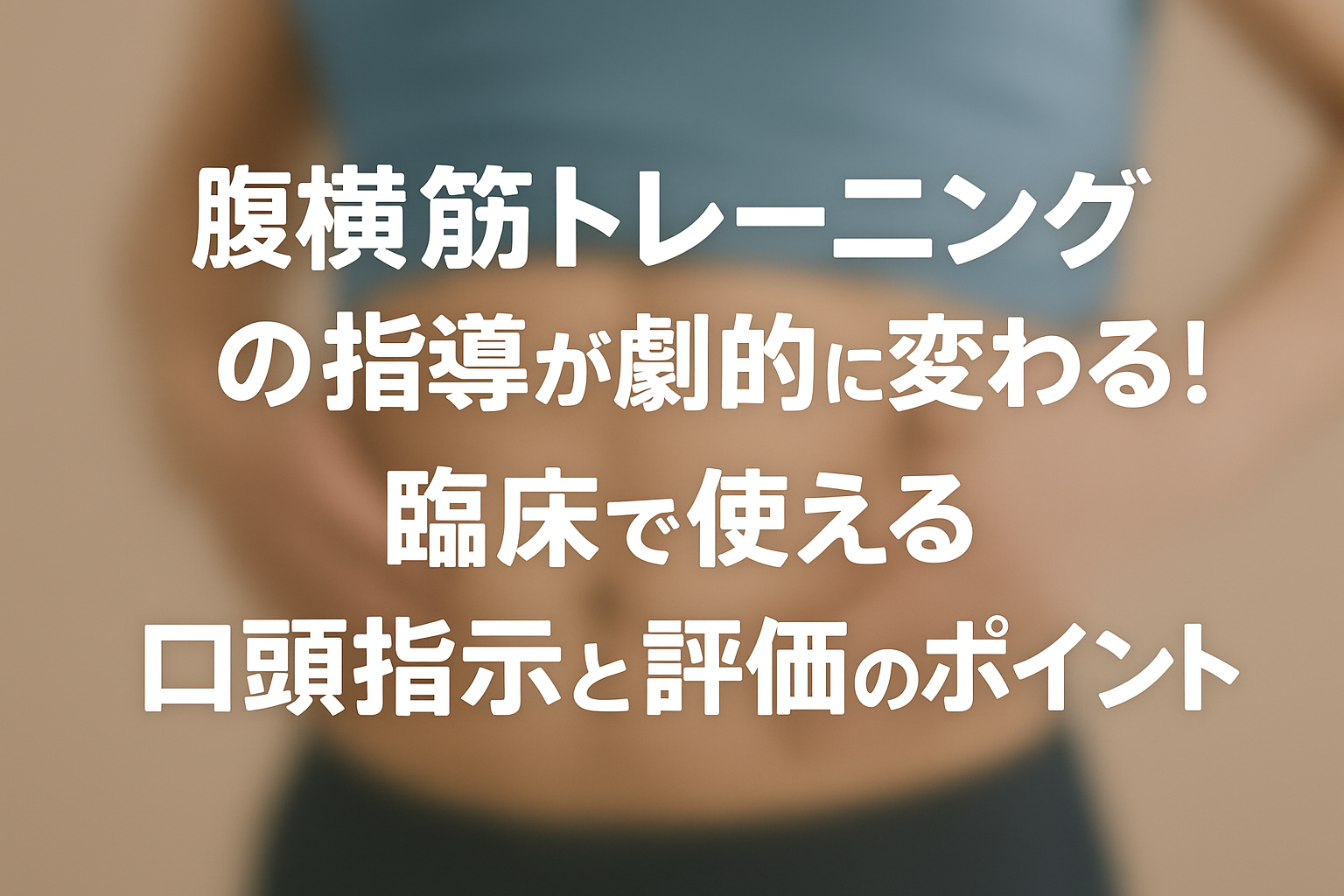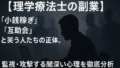はじめに
臨床で「腹横筋(ドローイン)」の指導をする際、こんな悩みはありませんか?
- 「お腹に力を入れて」と言うと、息を止めてしまう
- どうしても腹直筋(アウター)がガチガチになる
- 患者さんが「できている感覚」を掴めない
腹横筋は深層にあるため、ただ「鍛えましょう」と言うだけでは伝わりにくい筋肉の代表格です。しかし、ここが使えないと腰痛予防や動作の安定性は獲得できません。
そこで今回は、Noteメンバーシップで公開した記事『【Day 11】腹横筋をどう教える?臨床で確実に収縮を引き出すための口頭指示と実践例』の内容から、明日から意識できる重要なポイントを要約してシェアします。
【要点1】患者さんへの説明は「コルセット」一択
専門用語で解剖学を語っても、患者さんの体は動きません。まずはイメージを共有することが大切です。
記事で紹介している説明の鉄板例
- 「体の奥にある天然のコルセットです」
- 「おへその裏側、骨盤の奥で働く筋肉です」

「表面の筋肉」と「奥の筋肉」は別物である、という認識を持ってもらうだけで、代償動作(アウターの過緊張)は減らせます。
【要点2】「力を入れて」はNGワード?口頭指示の工夫
腹横筋の収縮を引き出す最大のコツは、指示の出し方(バーバルコマンド)を変えることです。
多くのセラピストが「お腹をへこませて」「力を入れて」と言いがちですが、これでは防御性の収縮を招きます。
効果的な指示のキーワード
- 「そっと」(強くやらない)
- 「薄くする」(へこませるのではない)
- 「チャックを閉める」(下から引き上げるイメージ)
特にnote本編で解説している「ズボンのチャックをそっと閉めるような感覚」という比喩は、骨盤底筋との連動も促せるため、臨床での成功率が非常に高い指示の一つです。
【要点3】「できた!」を実感させるフィードバック技術
患者さんがトレーニングを続けられない最大の理由は、「正解がわからないから」です。
セラピストは、正しく収縮した瞬間に「それです!」と伝える技術が必要です。
本編で解説している評価テクニック
- 触診: ASIS(上前腸骨棘)の内側2cmの「張りの変化」をどう触り分けるか
- 視覚: 患者さん自身にお腹を見てもらい「薄くなる」現象を確認させる
- 動作: SLRや片脚立位を使って、即時効果(足が軽くなる等)を実感させる

「あ、これか!」という感覚(成功体験)を初回のリハビリで作れるかどうかが、その後の経過を左右します。
【もっと詳しく】そのまま使える「指導スクリプト」を公開中
今回の要点を踏まえた上で、実際に臨床現場でどう会話を進めていけばいいのか?
現在公開中のNote記事では、「導入の説明」から「触診」「口頭指示」「代償動作の修正」までの一連の流れを、そのまま使える**会話形式のスクリプト(台本)**として掲載しています。
Note記事で学べること
✅ 高齢者・腰痛患者・アスリート別の言葉の選び方
✅ うまくいかない時の「修正指示」のバリエーション
✅ 「呼吸」を使って無意識に収縮させる誘導テクニック
✅ 新人セラピストでも再現できる「会話の台本」
「明日の担当患者さんに、どう声をかけようか悩んでいる」
「感覚的な指導ではなく、論理的な指導スキルを身につけたい」
そんな方は、ぜひ全編をチェックして、ご自身の「引き出し」に加えてください。
▼ 記事の本編はこちら ▼
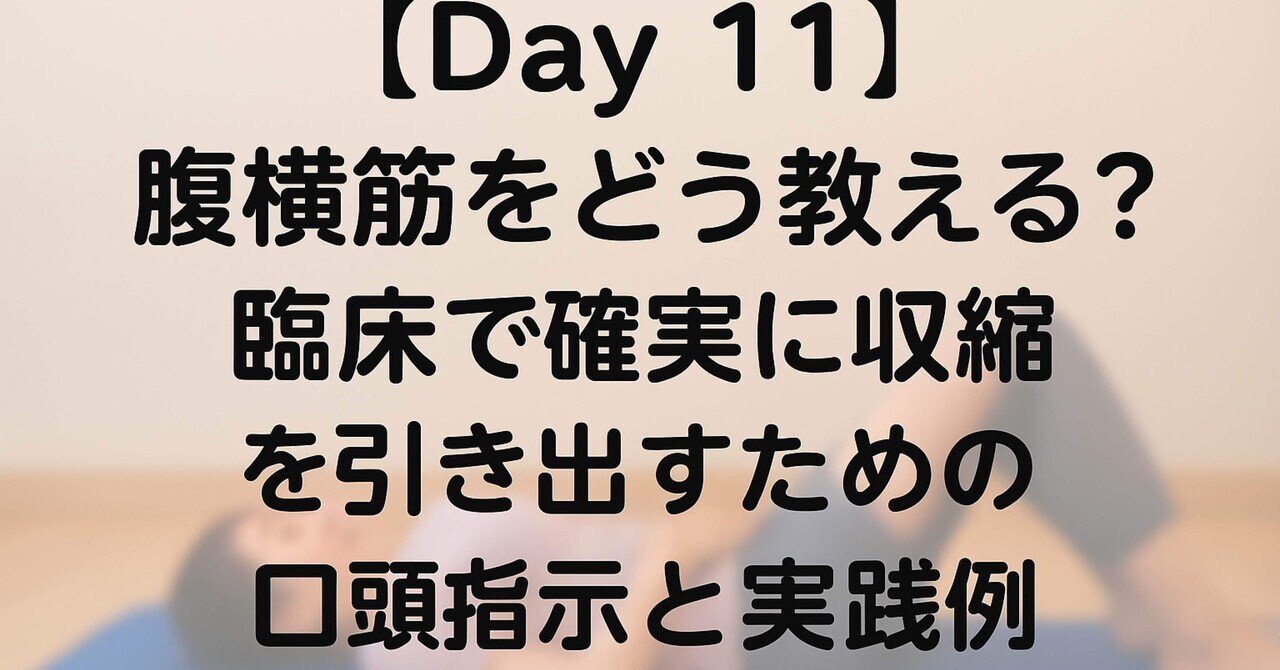
メンバーシップのご案内
当メンバーシップでは、教科書には載っていない「臨床のリアルな技術」を定期的に深掘り解説しています。
初月無料(※設定による)で、過去のアーカイブ記事も読み放題です。現場ですぐに使える知識を一緒にアップデートしていきましょう!
教科書には載っていない現場のコツや、最新のエビデンスに基づいた理学療法のノウハウや症例検討(ケーススタディ)を通して臨床で役立つ情報を、月々わずかスターバックス1杯分ほどのお値段でお届けしています。