「運動麻痺だけじゃない…」高次脳機能障害が絡む脳卒中リハビリに悩むあなたへ
脳卒中の患者さんを担当していて、こんな悩みを抱えたことはありませんか?
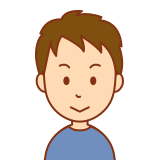
運動麻痺の評価はできても、注意障害や半側無視といった**「見えない障害」**が動作にどう影響しているか分からず、アプローチに悩む…。
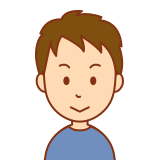
評価項目をたくさん取ったものの、それをどう結びつければいいか分からず**「統合と解釈」**で手が止まってしまう…。
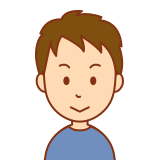
ICFを使って問題点を整理したいけど、具体的にどう書けばいいか分からず、結局いつも同じような内容になってしまう…。
そんな若手理学療法士や学生の皆さんが、明日からの臨床で自信を持って使える**「思考の型」**を学べる、リアルな症例検討会を記事にまとめました。
今回のテーマは「50代男性・料理人」の右被殻出血。なぜこの症例から多くを学べるのか?
今回取り上げるのは、**「右被殻出血を発症した50代男性、職業は料理人」**という、臨床で出会う可能性の高い症例です。
この症例の臨床推論が難しく、そして学びが深いポイントは以下の3つです。
- 【複合的な障害】
重度な左片麻痺に加えて、**「注意障害」「半側空間無視」「病態失認」**といった高次脳機能障害が複雑に絡み合っている点。 - 【高いゴール設定】
職業が「料理人」であるため、復職には巧緻性・持久力・バランスなど、非常に高いレベルの身体機能が求められる点。 - 【心理的側面】
「早く仕事に戻りたい」という本人の焦りや不安にどう寄り添い、急性期のリスク管理とリハビリを両立させるかという点。
これらの複雑な要素をどう紐解き、根拠のあるリハビリ計画に落とし込んでいくのか。その思考プロセスを追体験することで、あなたの臨床力は格段にアップするはずです。
【チラ見せ】評価結果をどう結びつける?「統合と解釈」のポイントを一部公開!
有料記事では、詳細な初期評価から具体的なプログラム立案までを網羅していますが、ここでは臨床推論の核心である**「統合と解-釈」**の一部を特別に抜粋してご紹介します。
(有料記事からの抜粋)
これらを総合的に捉えると、本症例は「運動麻痺 × 注意障害 × 半側無視 × 病態失認 × 体幹・下肢支持性の低下」という、複数の障害が相互作用する典型的な重度脳卒中例であると言える。
一般的に、脳卒中後の運動学習は「注意」や「自己身体認識」の影響を強く受ける。注意が向かない部位の回復は著しく遅れ、使わない肢には“learned non-use(学習性不使用)”が生じやすい。本症例で麻痺側の随意性が回復しにくい背景には、この**“注意の偏り”が大きく関わっている可能性が高い。**
いかがでしょうか。
単に「麻痺がある」「注意障害がある」と問題点を並べるのではなく、それらの障害がどう相互作用し、患者さんの「動けなさ」の根本原因となっているのかを深く考察しています。
この思考プロセスこそ、効果的なリハビリプログラムを立案するための鍵となるのです。
明日からの臨床が変わる!この記事で学べる5つのこと
メンバーシップ限定記事を最後まで読むことで、あなたは以下の知識とスキルを自分のものにできます。
- 評価の視点: 運動麻痺と高次脳機能障害を同時に評価し、動作に与える影響を分析する力が身につきます。
- ICFの実践的活用法: 複雑な情報をICFのフレームワークで整理し、多角的な問題点を抽出する具体的な方法がわかります。
- 目標設定の立て方: 急性期から「復職」という長期目標を見据えた、現実的かつ具体的な短期・長期目標の立て方を学べます。
- プログラム立案の根拠: なぜそのアプローチを選択するのか? 根拠に基づいた一貫性のあるリハビリプログラムの組み方が理解できます。
- 症例報告・発表への応用: この記事自体が症例報告のテンプレートにもなり、カンファレンスでの発表やレポート作成にすぐに活かせます。
一人前のセラピストを目指すための、次の一歩へ
今回は、右被殻出血の症例を通して、理学療法士に求められる臨床推論のプロセスをご紹介しました。
この症例の**「ICFに基づいた詳細な問題点リスト」「具体的な短期・長期目標」「根拠に基づいた4つのリハビリプログラム」**の全貌は、noteメンバーシップ限定で公開しています。
先輩セラピストの思考プロセスを覗き見して、あなたの臨床力をもう一段階レベルアップさせませんか?
ご参加を心よりお待ちしております。
▼症例検討の全編はこちらから▼


