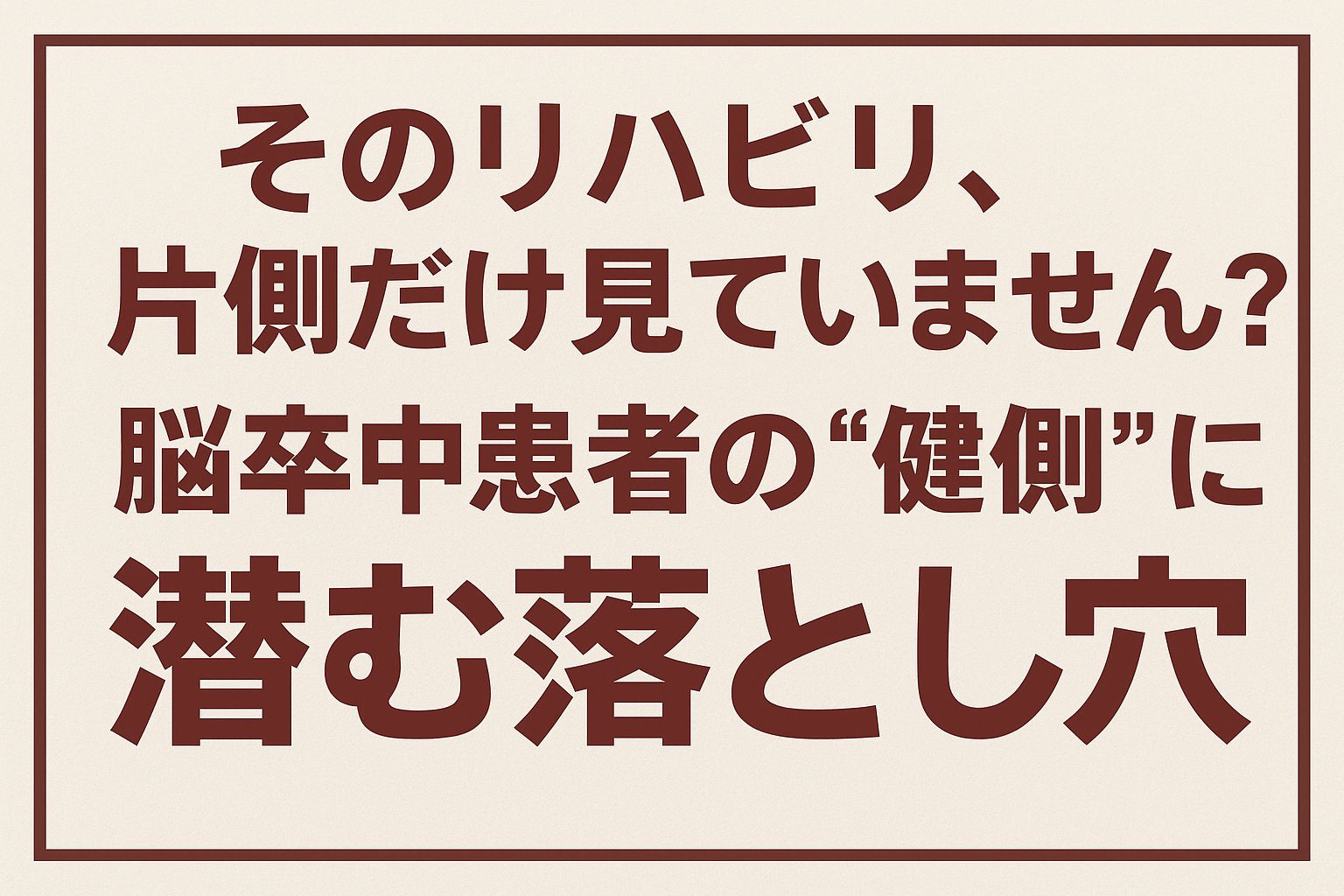高次脳機能障害のリハビリ悩みますよね…
「担当している患者さん、リハビリに集中できていないな…」
「簡単な着替えのはずなのに、なぜか袖に腕を通せない…」
「指示は理解しているようなのに、動き出すと戸惑ってしまう…」
新人・若手セラピストの皆さん、臨床でこのような場面に遭遇し、アプローチに悩んでいませんか?
その症状、もしかしたら高次脳機能障害の中でも特に頻度の高い「注意障害」や「失行」が原因かもしれません。
この記事では、注意障害と失行の基本的な知識から、明日からの臨床ですぐに実践できる具体的なリハビリ方法までを、分かりやすく解説します。この記事が日々の臨床の一助となれば幸いです。
お知らせ
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

まずは基本から!「注意障害」のリハビリテーション
注意障害とは、一言でいうと「注意のアンテナがうまく働かない状態」です。脳卒中後の患者さんなどでよく見られ、リハビリの効果を最大限に引き出すためには、この障害への理解と適切なアプローチが不可欠です。
臨床でよく見る症状タイプと具体例
注意障害にはいくつかのタイプがあります。患者さんのどのタイプに当てはまるか観察してみましょう。
- 全般性注意障害:なんだかボーッとしている、すぐに疲れてしまう、反応が鈍い。
- 持続性注意障害:課題を始めてもすぐに集中が途切れ、他のことをし始めてしまう。
- 選択性注意障害:周囲の物音や会話など、関係ない刺激に気を取られやすい。
- 転換性注意障害:複数の作業を切り替えるのが苦手(例:料理中に電話対応後、元の作業に戻れない)。
- 配分性注意障害:2つ以上のことを同時に行う「ながら動作」が極端に苦手になる(例:話しながら歩く、メモを取りながら話を聞く)。
【実践編】注意障害への具体的なリハビリアプローチ
アプローチの基本は、「集中できる環境を作り、本人の工夫を促すこと」です。
まずは、患者さんが集中しやすい「場」を作ることが最優先です。
- 刺激を減らす:静かな個室やリハビリ室の隅を選ぶ、カーテンを閉める。
- 情報を絞る:机の上は課題に必要な物品だけにする。ポスターなどが少ない壁側を向いてもらう。
机上訓練から始め、徐々にADL(日常生活動作)に繋げていきます。
- 机上課題の例
- 単純な計算ドリル、間違い探し、文字探し
- ペグボード、カードの仲間分け
- セラピストの動きを真似する模倣課題
- ADL訓練への応用
- 調理、買い物、掃除など、生活に直結した課題を通して注意機能の改善を目指します。
患者さん自身が注意をコントロールする工夫を身につけるためのアプローチです。
- 指差し確認・声出し:「次は〇〇をする」と声に出したり、手順を指で差したりして、注意を課題に向けさせます。
- タイマーやアラームの活用:時間を区切って課題を行うことで、持続性注意の訓練になります。「このタイマーが鳴るまで頑張りましょう」といった声かけが有効です。
- チェックリストの活用:手順の多い動作(調理や整容など)は、チェックリストを作成し、一つひとつ確認しながら行ってもらうことで、抜け漏れを防ぎます。
麻痺はないのに動けない?「失行」のリハビリテーション
失行とは、運動麻痺や感覚障害がないにも関わらず、「体の動かし方のプログラム」が思い出せず、意図した動作が正しく行えない状態です。患者さん本人は「やろうとしているのに、なぜかできない」と混乱していることも少なくありません。
臨床でよく見る症状タイプと具体例
失行もいくつかのタイプに分けられます。
- 観念運動失行:「バイバイして」と指示するとできないが、帰り際には自然に手が振れる。指示や模倣での動作が苦手。
- 観念失行:歯ブラシを渡しても髪をとかそうとするなど、物品の目的や一連の動作の順序が分からなくなる。
- 構成失行:積み木で手本と同じ形が作れない、図形の模写が苦手など、パーツを組み合わせて全体を形作ることが困難。
- 着衣失行:服の上下や前後、裏表が分からず、うまく袖に腕を通せない。
【実践編】失行への具体的なリハビリアプローチ
アプローチの基本は、「エラーレス・ラーニング(無誤学習)」です。誤った運動パターンを学習させないよう、失敗させずに正しい動きを導くことが重要です。
一つの動作を細かい工程に分け、一つずつ確実にクリアしてもらいます。
- 例(歯磨き):「①歯ブラシを持つ」→「②歯磨き粉のキャップを開ける」→「③歯ブラシにつける」…
- 前方連鎖法(フォワードチェイニング):①から順に教える
- 後方連鎖法(バックワードチェイニング):最後の工程だけ本人に行ってもらい、達成感を得やすくする
言葉の指示だけで動けない患者さんには、様々な感覚情報で動きをガイドします。
- 視覚的キュー
- セラピストがやって見せる(鏡のように対面ではなく、隣に並んで見せるのがコツ)。
- 写真やイラストで手順を示す。
- 物品に目印をつける(例:靴下の踵に色のついたテープを貼る)。
- 聴覚的キュー
- 「右手を袖に…ぐーっと入れます」のように、動作を実況中継する。
- 「サッと」「トン」などのオノマトペ(擬音語・擬態語)を使う。
- 体性感覚的キュー
- セラピストが患者さんの手や足を取り、一緒に動かす(ハンドリング)。
- 動かしてほしい身体部位を軽く触れて、意識を促す。
正しい運動パターンを再学習するためには、実際の物品を使った反復練習が効果的です。日常生活の場面で、意味のある動作を繰り返し行い、身体に覚えさせていきましょう。
ワンランク上のセラピストになるために
注意障害と失行は、密接に関連しています。注意が散漫だと、動作のプログラムを正しく実行することも困難になります。そのため、両方の側面から評価・アプローチする視点が重要です。
また、リハビリは専門職だけで完結しません。
- ご家族への指導:症状を分かりやすく説明し、ご家庭でできる介助のコツ(声かけの仕方、環境設定など)を伝え、最強のチームメンバーになってもらいましょう。
- チームアプローチ:看護師や介護福祉士と、有効だった声かけやアプローチ方法を共有し、病棟生活全体で一貫したケアを目指すことが、患者さんの能力向上に繋がります。
【まとめ】
今回は、注意障害と失行のリハビリアプローチについて解説しました。
- 注意障害には「環境調整」で集中できる場を作り、「代償戦略」で本人の工夫を引き出す。
- 失行には「エラーレス・ラーニング」を基本に、「動作の分解」と「多様なキュー」で正しい動きを導く。
最も大切なのは、マニュアル通りのリハビリではなく、患者さん一人ひとりの状態をよく観察し、その人に合ったアプローチを試行錯誤することです。この記事が、明日からの皆さんの臨床のヒントになれば幸いです。