はじめに
「先生、リハビリすると痛いんですけど…このまま動かして大丈夫ですか?」
手術後のリハビリを担当していると、多くの患者さんからこのような不安の声をいただきます。回復のために頑張りたい気持ちと、痛みへの不安。その間で揺れ動くのは、とても自然なことですよね。
術後のリハビリにおいて、「痛み」は避けて通れないテーマの一つです。しかし、すべての痛みが「悪いもの」というわけではありません。中には、回復過程で必要な「良い痛み」もあります。
この記事では、私たち理学療法士がどのように「術後の痛み」を見極め、リハビリを進めているのか、その臨床推論(考えるプロセス)の一端をご紹介します。
\臨床理学Labとは?/
「なぜこの痛みが起きたのか?どんな治療が効果的なのか?」
「どんな視点で評価すればよかったのか?」
「論文をどんな風に臨床に活かせばいいのか?」
そんな問いに一緒に向き合いながら、臨床で役立つ“推論の引き出し”を増やしていく場を、メンバーシップ限定コンテンツとしてご用意しています。※有料記事が読み放題です。
🔸 メンバー限定で読める「評価→推論→介入→再考察」付きの深掘り症例ノート
🔸 痛みや治療の考え方に特化した臨床推論の解説
🔸 コメント・質問歓迎のクローズドな学びの空間

まずは基本から!2種類の痛みの正体を知ろう
術後の痛みは、大きく2つのタイプに分けられます。これを理解するだけで、痛みへの不安が少し和らぐかもしれません。
1. 身体からの赤信号:「炎症」による痛み
手術は、身体にとっては大きなダメージです。メスを入れた皮膚や筋肉、骨などの組織は傷つき、それを治そうと身体が反応します。これが「炎症」です。
- 原因:手術による組織の損傷。身体からの「今は安静にして、回復に集中して!」というサインです。
- 特徴:
- 安静時痛:じっとしていてもズキズキ、ジンジン痛む。
- 夜間痛:夜、寝ようとすると痛みが強くなる。
- 熱感:患部が熱を持っている感じがする。
- 腫脹(腫れ)・発赤(赤み):見た目にも腫れていたり、赤くなっていたりする。
- 例えるなら。:「火事」の状態。まずは消火活動(安静、冷却)が最優先です。この状態で無理に動かすと、火に油を注ぐことになりかねません
2. 身体からの黄信号・青信号:「筋肉痛」のような痛み
手術後、安静にしていた筋肉は硬く、弱くなっています。リハビリで久しぶりにその筋肉を動かすと、筋肉繊維に微細な傷がつき、痛みとして感じられることがあります。これは、運動後の筋肉痛(専門的には遅発性筋痛:DOMS)と似たメカニズムです。
- 原因:安静によって衰えた筋肉を、リハビリで動かしたことによる正常な反応。
- 特徴:
- 運動時痛:動かした時や、筋肉に力を入れた時に痛む。
- 圧痛:筋肉を押すと痛い。
- 筋肉の張りや重だるさ。
- リハビリの翌日に痛みのピークが来ることが多い。
- 例えるなら:「久しぶりの筋トレ後の心地よい疲労感」。筋肉が強くなるために必要な、成長の証とも言えます。
他にもこんな記事があります^_^
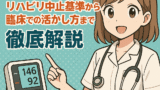
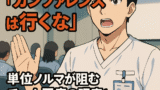
理学療法士の頭の中を覗いてみよう!痛みの鑑別(臨床推論)
では、私たちはこの2つの痛みをどうやって見分けているのでしょうか?
実は、一つの情報だけで判断するのではなく、患者さんの言葉や身体のサインをパズルのように組み合わせて考えています。
① 問診:「いつ、どこが、どんなふうに痛みますか?」
患者さんとの会話は、最も重要な情報源です。私たちはこんなことを聞いています。
- 痛みのタイミング:「朝起きた時が一番痛いですか?」「動かし始めだけ痛くて、動いているうちに楽になりますか?」
- 痛みの種類:「ズキズキしますか?それとも、重だるい感じですか?」「ピリピリとしびれるような感じはありますか?」
- 痛みの変化:「昨日のリハビリの後、痛みはどうでしたか?」「湿布を貼ると楽になりますか?」
これらの質問から、痛みの背景にある原因を探っていきます。
② 視診・触診:「見せてくださいね、触りますよ」
言葉の情報だけでなく、身体が発するサインも見逃しません。
- 視診(目で見る):手術した側と反対側を比べて、腫れや赤みがないかを確認します。
- 触診(手で触れる):患部にそっと触れて、熱っぽさ(熱感)がないか、左右で差がないかを確かめます。また、どの筋肉を押すと痛むのか(圧痛点)を探し、痛みの原因となっている部位を特定します。
③ 動作分析:「ゆっくり動かしてみましょう」
実際に身体を動かしてもらうことで、痛みの本質が見えてきます。
- 可動域の確認:どの角度まで動かすと痛みが出るのか、痛みで動きが制限されていないかを確認します。
- 痛みの出方:特定の動き(例:膝を伸ばす時だけ、腕を上げる時だけ)で痛みが出るのかを評価します。
- 代償動作の有無:痛みをかばうあまり、不自然な身体の使い方(代償動作)になっていないかを見ています。これは別の痛みの原因になることもあるため、重要なチェックポイントです。
これらの情報を統合し、「この痛みは炎症が主体だな」「これは筋肉をしっかり使えた証拠の痛みだ」と判断していくのです。これが、理学療法士の臨床推論です。
痛みによってアプローチは変わる!それぞれの対処法
痛みの種類によって、リハビリの進め方(アプローチ)は大きく変わります。
「炎症の痛み」が疑われる場合
- 理学療法士の対応:無理な運動は中止、または負荷を軽くします。アイシング(冷却)を徹底し、炎症を抑えることを優先します。自主トレーニングのメニューを見直し、炎症を悪化させない範囲の運動を指導します。
- 患者さんができること:自己判断で無理は禁物です。「痛いけど頑張らなきゃ」は逆効果になることも。担当の理学療法士や医師の指示に従い、安静や冷却を心がけましょう。
「筋肉痛」が疑われる場合
- 理学療法士の対応:回復に必要な痛みだと判断した場合、適切な負荷で運動を継続するよう促します。運動後のストレッチやケアの方法を指導し、翌日の状態を確認しながら、少しずつ負荷を上げていきます。
- 患者さんができること:これは「良い痛み」のサインかもしれません。怖がりすぎず、指示されたリハビリを続けてみましょう。入浴で身体を温めて血行を良くしたり、軽いストレッチを行ったりするのも効果的です。

もちろん、over use”使いすぎ(頑張りすぎ)”ている筋肉痛のような痛みも中にはあります。その要素も踏まえて治療プランを考えていく必要がありますね。
まとめ:痛みを味方につけて、リハビリを成功させよう
術後のリハビリにおける痛みは、身体からの大切なメッセージです。
- 「ズキズキする」「熱っぽい」 → 身体からの**「休んで」**という赤信号(炎症)
- 「動かすと痛い」「筋肉が張る」 → 身体からの**「効いてるよ」**という黄信号・青信号(筋肉痛)
この違いを少しでも理解できると、リハビリへの向き合い方が少しずつ変わってくると思います。
しかし、一番大切なのは、痛みを我慢したり、自己判断でリハビリを中断したりしないことです。不安なこと、些細な変化でも構いません。ぜひ、私たち担当の理学療法士に正直に伝えてください。
私たちは、その痛みの声に耳を澄まし、あなたにとって最適なリハビリを一緒に考えるパートナーです。二人三脚で、焦らず、着実に、回復への道を歩んでいきましょう。


