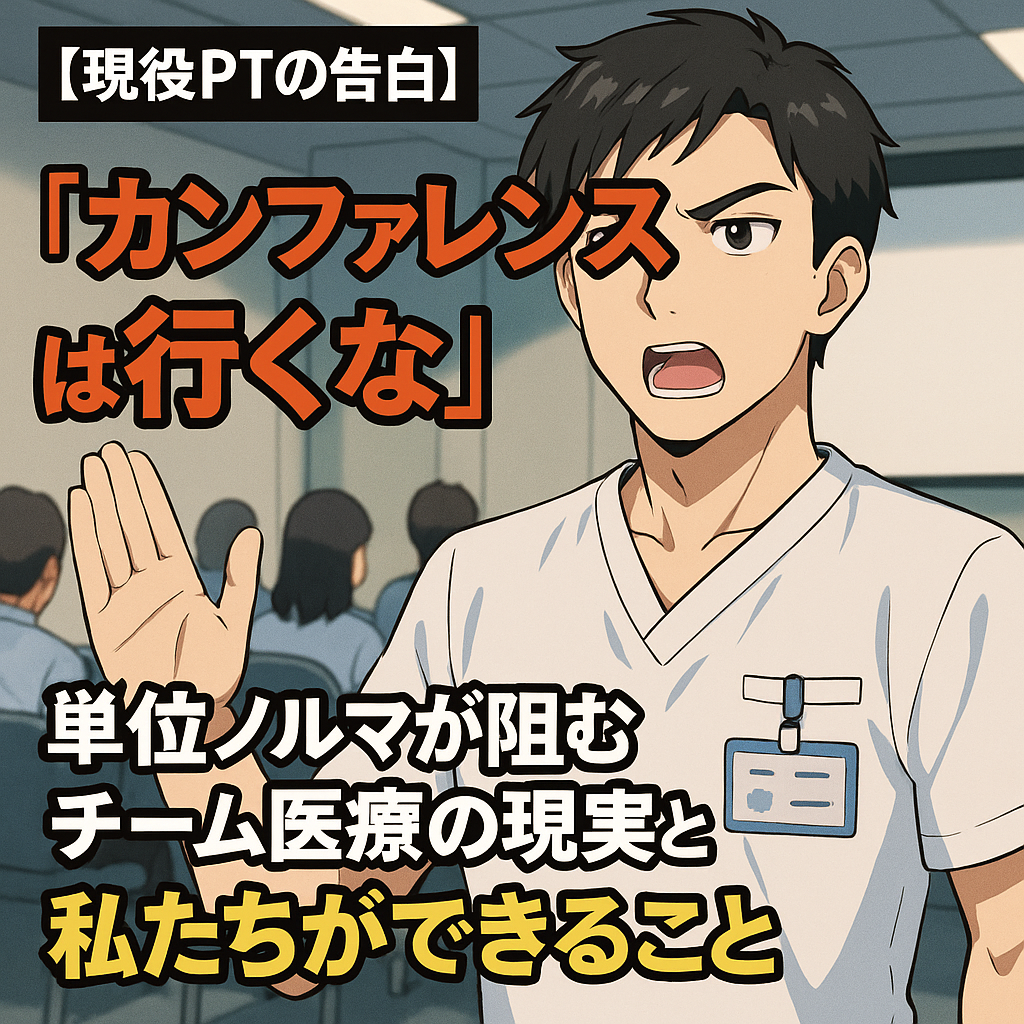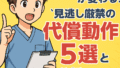はじめに
「患者さんのカンファレンス、リハビリさんも来てくれると助かります」
看護師さんからこう声をかけられたら、あなたはどう感じますか?
「頼りにされている」「チームの一員として認められている」と、誇らしい気持ちになりますよね。
患者さんの生活を本気で支えたいリハビリ専門職にとって、多職種カンファレンスは非常に重要な場です。しかし、その想いとは裏腹に、上司からこんな言葉を投げかけられた経験はないでしょうか。
「カンファレンスに行くと単位が削られるから、行かなくていいよ」
この一言で、患者さんのために貢献したいという熱意が、冷水を浴びせられたように消えてしまう…。これは、多くのリハビリスタッフが抱える、現場の切実なジレンマです。
この記事では、単位ノルマを理由にカンファレンス参加を制限される問題に焦点を当て、その背景にある構造的な課題と、先進的な施設の取り組み事例を紹介します。そして最後に、「どうせ変わらない」と諦める前に、私たち一人ひとりが踏み出せる「小さな一歩」を一緒に考えていきたいと思います。
\意見を仲間と一緒に共有しませんか?/

■ なぜ?リハビリ職のカンファレンス参加が不可欠な理由
入院中の患者さんを支える医療は、医師、看護師、MSW(医療ソーシャルワーカー)、栄養士、薬剤師など、多くの専門職が連携する「チーム医療」によって成り立っています。当たり前ですが、リハビリ職だけで患者さんの全てを支えることはできません。
そのチームの中で、私たちリハビリ専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が担うべき重要な役割とは何でしょうか。
それは、**「日々のリハビリから見えてくる、患者さんのリアルな生活機能の実態」**をチームに共有することです。
具体的には、以下のような情報をリハビリの視点から提供します。
- 基本動作能力:歩行、移乗、起き上がりなど、どの程度できるか、介助は必要か。
- ADL(日常生活動作):食事、更衣、トイレ、入浴などの具体的な遂行状況と課題。
- 高次脳機能:認知、注意、記憶などの機能が、生活にどう影響しているか。
- 心理・意欲面:本人の不安や希望、リハビリへのモチベーション。
- 環境要因:自宅の段差や手すりの有無、福祉用具の必要性。
「歩行器を使えば病棟内は歩けるけれど、屋外の坂道や砂利道はまだ不安が強い」
「トイレ移動は自立しているが、夜間の暗い中では転倒リスクが高い」
こうした“教科書には載っていない生きた情報”は、リハビリで密に関わるからこそ気づけるもの。カンファレンスは単なる業務報告の場ではなく、患者さんの生活を守るための“現場の声”を、他職種に直接届けられる唯一無二の機会なのです。
■ 高い壁となる「単位ノルマ」と「管理体制」の現実
しかし、その重要な機会を阻む大きな壁があります。それが、診療報酬制度における「単位」の存在です。
私の職場では、カンファレンスへの参加意欲は、こんな言葉で打ち砕かれます。
「カンファレンスに行ってたら単位が減るでしょ?行かなくていい」
「管理職が出るから、伝えたいことは申し送りしておいて」
この言葉の裏には、「リハビリスタッフの仕事は、1対1のリハビリで単位を取得すること」という強い価値観が根付いています。カンファレンスに参加する20〜30分は、直接的なリハビリが提供できず、「単位を生まない時間」と見なされてしまうのです。
もちろん、管理職が情報を伝達してくれること自体はありがたいことです。しかし、誰かを通した情報は、どうしても熱量やニュアンスが削ぎ落とされてしまいます。
- 私が感じた患者さんの表情の変化
- ふとした瞬間に漏らした本音
- ほんの少し見えた機能回復の兆し
こうした血の通った情報は、報告書や申し送りだけでは決して伝わりきりません。結果として、**患者さんの“生活に最も近い情報”がチーム内で共有されず、**退院後の生活を見据えた最適な方針決定が難しくなる可能性があります。これは、本当に患者さんのための医療と言えるのでしょうか。
■【他施設の事例】参加を後押しする、柔軟な仕組みとは?
一方で、すべての施設が同じような課題を抱えているわけではありません。私の知人が勤める先進的な病院では、スタッフが安心してカンファレンスに参加できる、素晴らしい仕組みが導入されています。
ある病院では、カンファレンス参加時間も業務の一環として評価し、単位数に換算してノルマを調整する仕組みがあります。
例えば、1日のノルマが19単位のスタッフが30分のカンファレンスに参加した場合、その日のノルマを1単位減らして18単位にする、といった柔軟な対応です。
これにより、スタッフは「単位が取れない」というプレッシャーを感じることなく、「患者さんのために行ってきます」と胸を張って言える環境が整っています。
また、別の施設では、病院全体で「多職種連携の強化」を最重要課題と位置づけ、カンファレンスへの参加をリハビリスタッフの“重要な役割”として制度化しています。
「忙しいから行けない」ではなく、「忙しい中でも参加することが当然の責務」という文化が醸成されているのです。参加の意義が上層部から現場スタッフまで共有されているため、後ろめたさを感じることなく、専門職としての役割を全うできます。
これらの事例は、経営や管理の視点が変われば、現場の働き方は大きく変わる可能性を示しています。
「チーム医療」の理念と現実のギャップをどう埋めるか
多くの病院が理念として「チーム医療の推進」を掲げています。私たちリハビリ職も、その言葉を信じてチームの一員としての役割を果たしたいと願っています。
しかし、現実の現場では、
- 単位の都合でカンファレンスから意図的に外される
- 現場の多忙さを理由に、不参加が常態化する
- 「行きたい」という声が、上司の一言でかき消される
といったことが起きています。
この理念と現実の大きなギャップは、スタッフのモチベーションを低下させるだけでなく、何よりも患者さんが受ける医療の質そのものに影響を与えかねません。
「どうせ変わらない」と諦める前に。私たちができる小さな一歩
「うちの職場は古い体質だから無理」
「言っても無駄だよ」
そう諦めてしまう気持ちは、痛いほどわかります。声をあげることには勇気が必要ですし、「和を乱す」「余計なことを言うな」と否定的な目で見られる不安もあるでしょう。
それでも、私は自分自身にこう問いかけ続けたいと思います。
「私は、患者さんの“今”と“未来”に本気で向き合えるセラピストでありたいか?」
その答えが「YES」である限り、私たちは諦めるわけにはいきません。現状を変えるのは簡単ではありませんが、指をくわえて待っているだけでは何も始まりません。
では、私たち現場のスタッフにできることは何でしょうか。
- 「参加したい」という意思を表明し続ける
たとえすぐに認められなくても、「〇〇さんのカンファレンス、生活状況を直接伝えたいので参加したいです」と、具体的に、そして粘り強く声を上げ続けることが第一歩です。 - 質の高い情報提供で価値を示す
カンファレンス資料を事前に作成し、「ここまで具体的に分析しているなら、直接話を聞いた方が良さそうだ」と管理職や他職種に思わせるのも一つの手です。参加の必要性を、実績で示しましょう。 - 仲間と問題意識を共有する
同じ思いを抱える同僚と話し、一人ではなく複数人で改善を働きかけることで、声の重みが増します。まずは職場の数人で課題を共有することから始めてみませんか。
こうした小さな一歩が、やがて大きなうねりとなり、職場の体制や文化を変えていく力になると信じています。
【まとめ】
今回は、リハビリ職が直面する「カンファレンスに参加したくても、単位を理由に参加させてもらえない」という深刻なジレンマについて掘り下げてきました。
- リハビリ職のカンファレンス参加は、患者のリアルな生活情報を共有する上で不可欠。
- しかし「単位ノルマ」が壁となり、参加が制限される職場は少なくない。
- 先進的な施設では、参加を評価する制度や文化が醸成されている。
- 「どうせ変わらない」と諦めず、意思表示や情報提供の工夫など、できることから始めよう。
この問題は、単なる一個人の悩みではなく、医療の質に関わる構造的な課題です。もしこの記事を読んで共感してくださった方がいれば、ぜひ一緒に声をあげていきましょう。
患者さんの“代弁者”として、私たちにしか伝えられない価値が、そこには必ずあるはずです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。