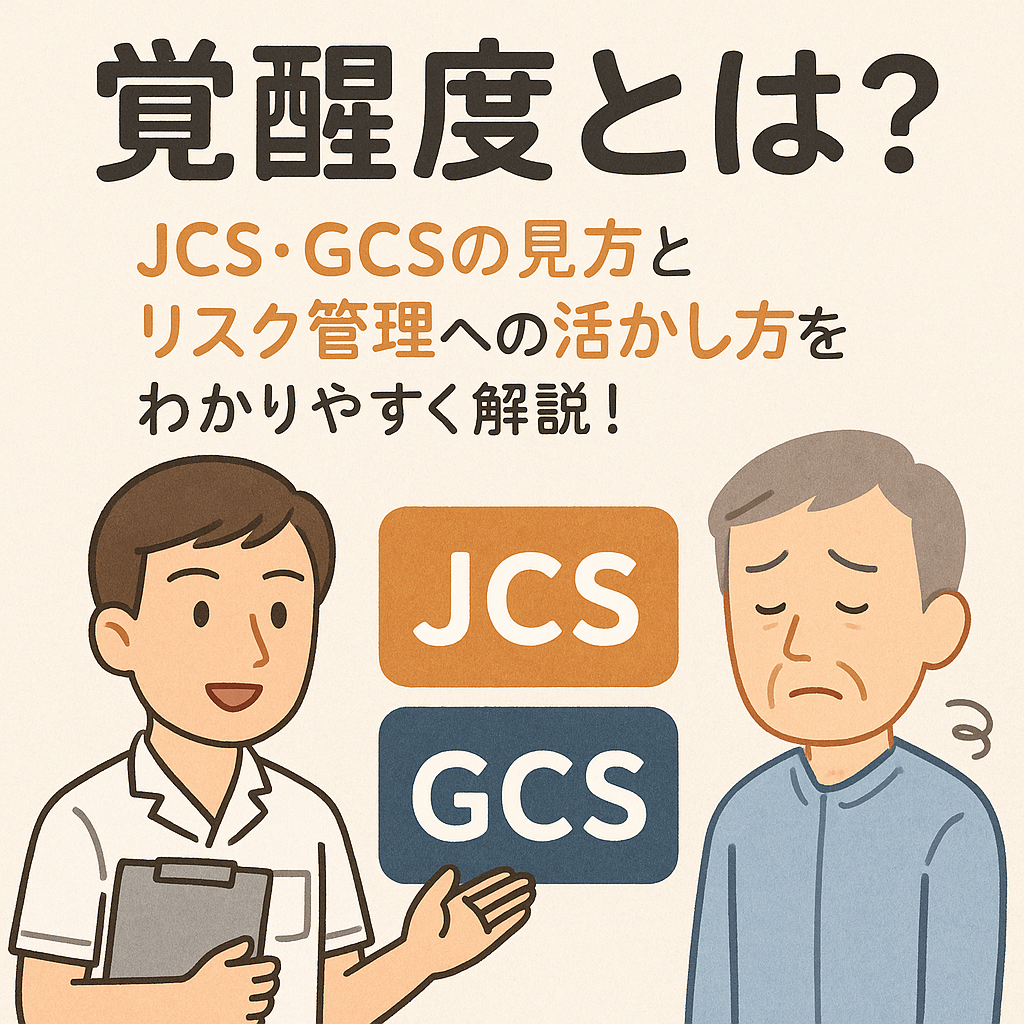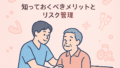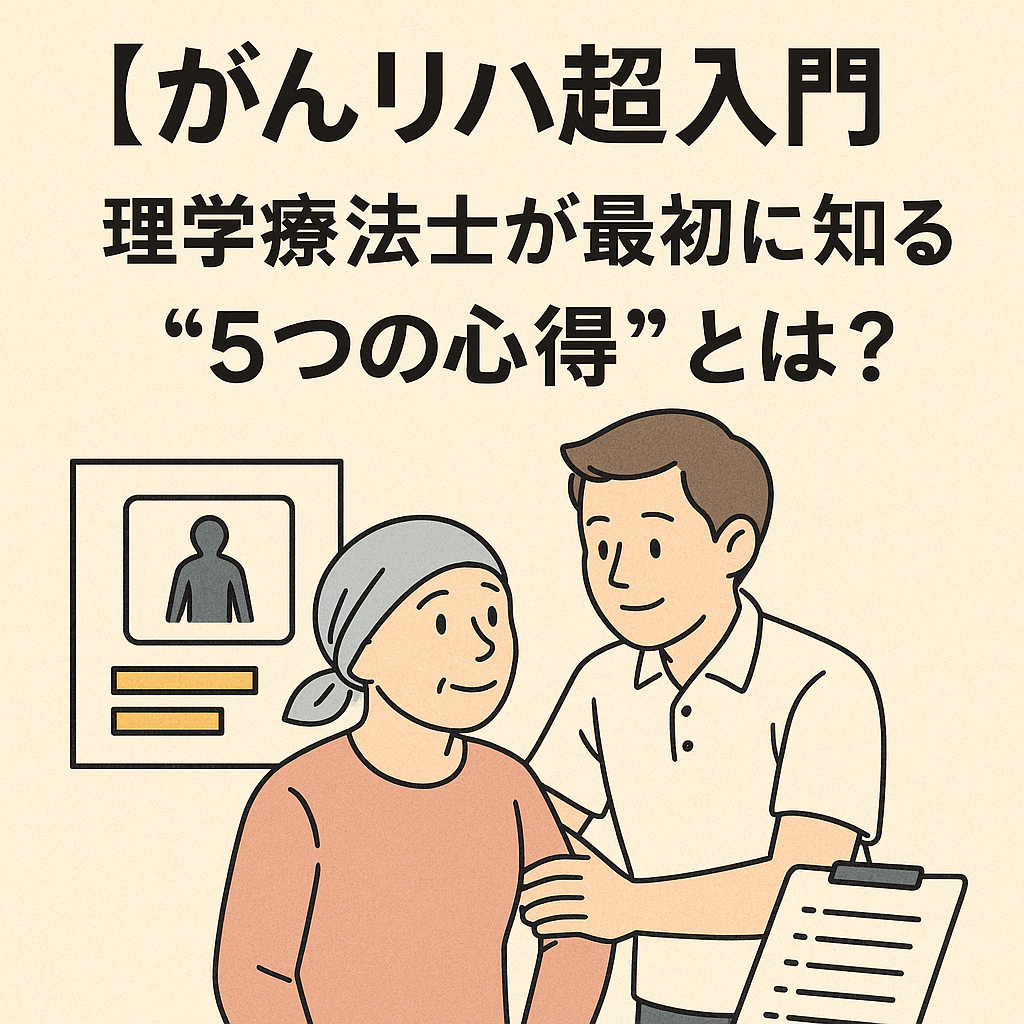はじめに:その「なんとなく反応が鈍い」は見逃し厳禁!
病棟で患者さんと接しているとき、「今日はなんとなく目の動きが鈍い」「声かけに対して反応が弱い」など、普段と違う様子に気づくことがありますよね。
理学療法士としての“観察力”が光る瞬間です。
実はその違和感、「覚醒度の変化」によるものかもしれません。
覚醒度は、単なる意識レベルの評価にとどまらず、リハビリの内容・進行度・安全性を大きく左右する重要な評価項目です。
しかし、学生時代に習って以来、正確に評価したり活かしたりする場面が少なく、なんとなく避けてきた人もいるのではないでしょうか?

本記事では、そんな「覚醒度」について、基礎から実践までを深掘りして解説していきます。
■ この記事がオススメな人
- 覚醒度の評価方法(JCSなど)に自信がない理学療法士
- リスク管理スキルを高めたい若手~中堅PT
- 急性期・回復期病棟で働いている理学療法士
- 「反応が鈍い…でも何が原因?」と感じたことがある人
- 覚醒度の変化を臨床でどう活かせばいいか知りたい人
- 患者さんの「いつもと違う」に敏感になりたい人
- もっと実践で使えるようになりたい人
⸻
覚醒度とは?〜意識レベルとの違いも整理しよう〜
覚醒度とは、「脳がどれだけ外界からの刺激に反応できる状態にあるか」を示す尺度です。
より噛み砕いて言えば、「目が覚めていて、話しかけたり触れたりしたときに、きちんと反応が返ってくる状態かどうか」を測るものです。
覚醒度は、以下のような要因の影響を強く受けます
• 中枢神経系の損傷や機能障害(例:脳卒中、頭部外傷)
• 代謝性疾患(例:低血糖、肝性脳症)
• 薬物の影響(例:鎮静薬、抗てんかん薬など)
• 精神状態(例:せん妄、うつ状態)
覚醒度と混同しやすい「意識レベル」という言葉との違いも整理しておきましょう。
| 用語 | 定義 | 例 |
| 覚醒度 | 目が覚めていて、刺激に反応できるか | 声かけに反応して目を開ける |
| 意識レベル | 覚醒と認知を含めた総合的な意識の状態 | 開眼しているが発語が支離滅裂 |
つまり、「目が開いている=覚醒している」ではなく、その人がどの程度“関われるか”が覚醒度の指標なのです。
なぜ理学療法士が覚醒度を評価すべきなのか?
1. 指示理解やリハビリ参加可否の判断
理学療法では、起き上がりや立ち上がり、歩行など、ある程度の意思疎通が必要な場面が多くあります。
覚醒度が低いと、「話しかけても反応がない」「命令に従えない」などの場面に遭遇します。
そのまま無理に進めると、転倒・事故などのリスクが高まります。
2. 病態悪化の早期サインに
例えば、昨日までしっかり歩けていた患者が、今日は眠そうで声にも反応が鈍いといったケース。
せん妄や感染、低酸素、低血糖などの兆候である可能性があります。
「なんとなくおかしいな」を見逃さず、JCSなどで客観的に評価することで、早期対応につながります。
3. 安全なリハビリ設計に活かせる
覚醒度が高い人には積極的なADL訓練が可能ですが、覚醒度が不安定な場合は環境調整やポジショニング重視の介入へ変更する必要があります。
評価なしにルーチンで介入していると、患者の状態に合わない負荷をかけてしまうことにもなりかねません。
覚醒度評価に使えるスケール:JCSとGCS
Japan Coma Scale(JCS)
JCSは日本で広く使われており、数字が大きくなるほど重度というシンプルな構造が特徴です。
| 分類 | 状態 | 例 |
| 1桁(1~3) | 自分で目を開ける | ぼんやりしているが会話可能 |
| 2桁(10~30) | 刺激で開眼・反応する | 肩をたたくと目を開ける |
| 3桁(100~300) | 無反応 | 強く揺すっても反応なし |
■ JCS(Japan Coma Scale)の点数づけ
Ⅰ桁台:
刺激なしで覚醒しているが何らかの意識障害あり
| スコア | 内容 |
| 1 | 見当識障害あり(人・時間・場所がわからない) |
| 2 | 見当識はあるが、言動が少しおかしい(会話がかみ合わないなど) |
| 3 | 自分の名前や年齢が言えないなど、より明らかな意識混濁がある |
Ⅱ桁台:
呼びかけや軽い刺激で覚醒する状態
| スコア | 内容 |
| 10 | 普通の声かけで開眼・応答するが、すぐ眠ってしまう |
| 20 | 大声や肩をたたくなどの強めの刺激で覚醒する |
| 30 | 痛み刺激でようやく開眼・反応するレベル |
Ⅲ桁台:
痛み刺激でも覚醒しない状態(昏睡)
| スコア | 内容 |
| 100 | 痛み刺激で開眼やわずかな反応がある(逃避・顔をしかめる) |
| 200 | 痛み刺激で手足を動かすような無意味な動作がある(除皮質硬直など) |
| 300 | 痛み刺激に全く反応しない(完全昏睡) |
Glasgow Coma Scale(GCS)
GCSはより詳細に「開眼」「発語」「運動」の3つの反応を点数化して評価します。
| 項目 | 概要 | 点数範囲 |
| 開眼反応(E) | 自発~刺激で開眼 | 1〜4点 |
| 言語反応(V) | 正常会話~意味不明発語 | 1〜5点 |
| 運動反応(M) | 指示通りの動作~無反応 | 1〜6点 |
合計点15点が正常、8点以下は重篤とされ、意識障害が強い状態と判断されます。
■ GCS(Glasgow Coma Scale)の点数づけ
① E:開眼反応(Eye opening)
| 点数 | 内容 |
| 4点 | 自発的に開眼している |
| 3点 | 呼びかけにより開眼 |
| 2点 | 痛み刺激により開眼 |
| 1点 | 開眼しない |
② V:言語反応(Verbal response)
| 点数 | 内容 |
| 5点 | 見当識があり、適切に会話できる |
| 4点 | 会話は成立するが見当識障害あり(混乱) |
| 3点 | 単語は出るが意味不明(不適切な言葉) |
| 2点 | 言葉ではない音声(うめき声など) |
| 1点 | 反応なし(発語なし) |
③ M:運動反応(Motor response)
| 点数 | 内容 |
| 6点 | 指示に従って四肢を動かせる |
| 5点 | 痛み刺激に対して目的ある動作(払いのける) |
| 4点 | 痛みに対して逃避する動き(手足を引っ込める) |
| 3点 | 痛みに対して不自然な屈曲反応(除皮質硬直) |
| 2点 | 痛みに対して伸展反応(除脳硬直) |
| 1点 | 反応なし |
■ GCSのスコア分類(合計点:E+V+M)
| 合計スコア | 意識レベルの目安 |
| 13〜15点 | 軽症(意識清明~軽度混乱) |
| 9〜12点 | 中等症(意識混濁あり) |
| 8点以下 | 重症(昏睡状態・緊急対応必要) |
状態別・覚醒度に応じたリハビリ戦略
| 覚醒度 | 評価例 | 実施可能なリハ内容 | 注意点 |
| 高(JCS1) | 受け答え・立位可能 | 歩行練習、動作訓練、ADL介入 | 過剰な刺激による疲労 |
| 中(JCS20) | 声かけ・触刺激で反応 | 関節可動域訓練、ベッド上起居練習 | 刺激量・時間の調整 |
| 低(JCS200) | 刺激でも反応鈍い | ポジショニング、呼吸介助、循環管理 | バイタル変化のモニタリング |
【実例紹介】覚醒度変化に気づいて命を守れた話
ある日、午前中のリハビリ中、普段は受け答えができていた脳卒中後の患者さんが、いつもより目が合わず、言葉の反応も弱い状態でした。
JCSを確認すると、前日はJCS1だったのが、この日はJCS200。バイタルチェックしたところ血圧が低く頻脈傾向であった。
すぐに看護師や担当医へ報告し、採血が行われたところ、低血糖が判明。
点滴後、症状は改善し、翌日からリハビリを再開できました。
覚醒度の変化は、病態悪化の最も早いサインの一つ。見逃さない観察力が、患者さんの安全と回復を守ります。
まとめ:覚醒度を見抜く力が、リハの質を高める
- 覚醒度は「今、この人がどれだけ反応できるか」を示す重要な指標
- 指示理解、安全性、病態変化の発見に関わる
- JCSやGCSを活用して、客観的に評価しよう
- 「なんか変だな」の直感を信じて、必ずチームで共有を
最後に:毎日の観察が、最大のリスク管理です
「バイタルは大丈夫だから大丈夫」ではありません。
「覚醒度が下がっている」=何かが身体の中で起きているサインかもしれません。
リハビリ前に1分だけ、患者さんの目、声、反応を観察してみてください。
あなたのその“気づき”が、患者の命と生活を守る力になります。
より知識を深めたい方は「臨床理学Lab」
「臨床理学Lab」ではより専門的な記事を作成しています。
ここでは全ての有料記事を読むことができます。
ここは、単なる情報提供の場ではありません。あなたの疑問や悩みを共有し、共に考え、共に成長できる場です。
単なる知識の提供ではなく、臨床で使える「考え方」を身につけることを重視していきたいと思います。
「この評価の結果から、次に何をすべきか?」
「この患者にはどんなアプローチが適切なのか?」
といった問いに対し、論理的に答えを導き出せるようになることを目標としています。
臨床推論を深め、評価力・判断力を向上させるために、一緒に学んでいきましょう!
👇