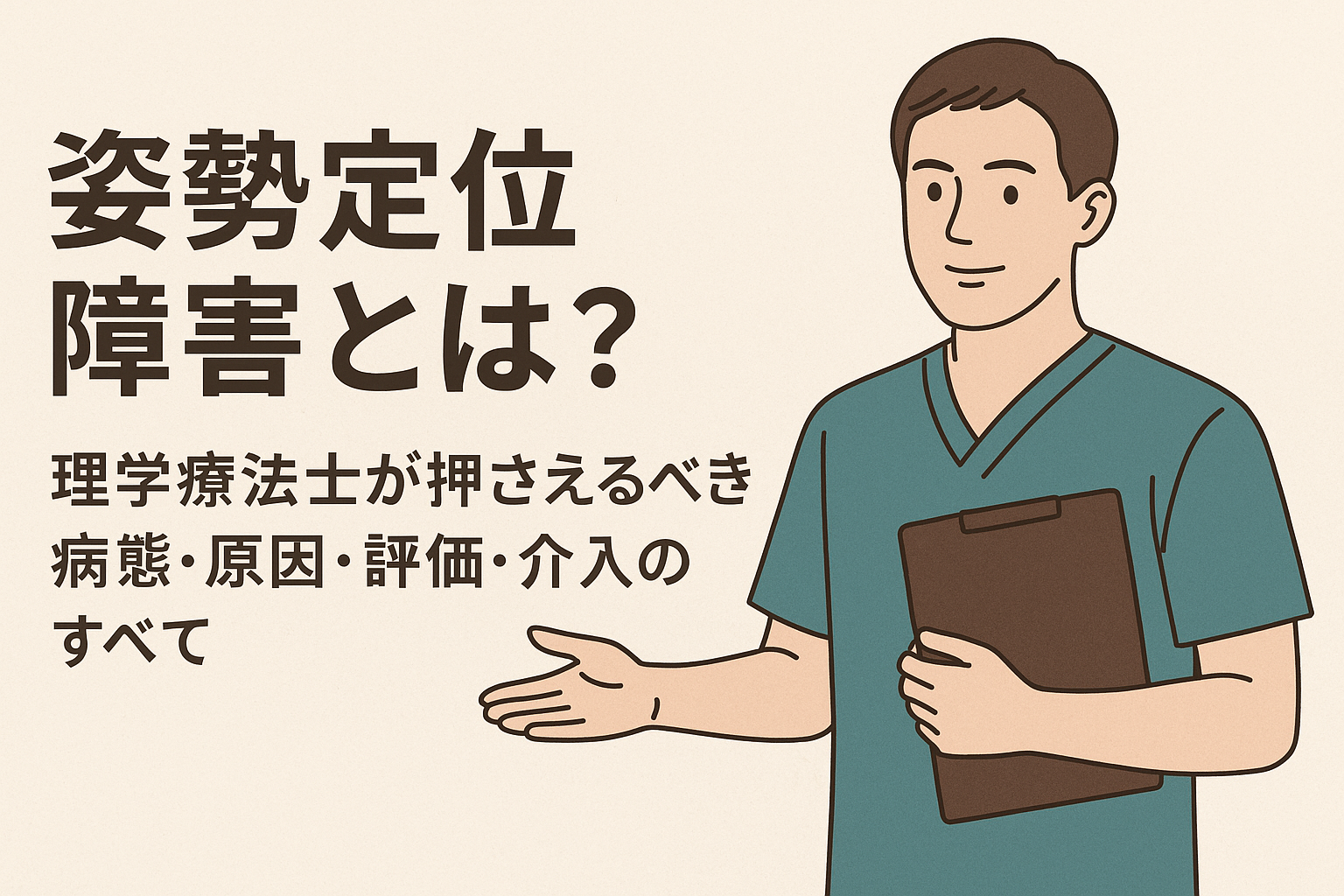はじめに
臨床でこう感じることはありませんか?

座位や立位の姿勢が不安定

立てるけどかなり体幹が傾く。

立位かなり不安定で、今にも転倒しそうなのに歩き出そうとする。
バランス能力や筋力低下だけでは説明しきれない“姿勢の崩れ”の背景には、「姿勢定位障害」という視点が欠かせないと思います。これは、日常生活動作の基盤となる姿勢制御機能の一部です。介入のポイントを押さえれば大きな変化をもたらせる領域でもあります。
本記事では、理学療法士として臨床に携わる上でぜひ知っておきたい姿勢定位障害の基本から臨床でアプローチまでを解説します。新人PTからベテラン、また学生の皆さんにも役立つような内容を目指しました。
⸻
姿勢定位とは何か?
まず押さえておきたいのは、「姿勢制御」は一枚岩ではないということです。一般的にはバランス能力としてひとまとめにされがちですが、実際には以下の2つの構成要素に分けて考えるべきだと考えています。
身体の各部位を空間や支持面に対して適切に配置する能力。
重心の移動や外乱に対してバランスを保つ能力。
つまり、定位=姿勢の“整え方”、安定性=姿勢の“保ち方”とも言えます。定位が崩れていれば、どれだけ安定させようとしても基本となる軸がズレているため、動作そのものが非効率になり、代償的なパターンが強化されてしまいます。
たとえば、
立位で体幹が左に偏位する症例がいた場合、
✖️「バランスが悪いから」ではなく
◯「正しい姿勢を取るという感覚や運動戦略自体が失われている可能性がある」
という風に考えることもできるわけです。
このように、“整える力”としての姿勢定位は、リハビリの出発点ともいえる大切な視点です。
⸻
姿勢定位障害の病態とは
姿勢定位障害とは、「身体を空間や支持面に対して適切に整える能力が低下している状態」を指します。
具体的な臨床場面では次のような問題として現れます。
• 座位や立位で身体が左右どちらかに傾く
• 重心が常に一方へ偏っている(非対称な荷重)
• 座っているだけで疲労感が強く、動作に結びつかない
• 起き上がりや立ち上がりで体幹が回旋・側屈し、効率の悪い運動になってしまう
• 立位の状態で既に不安定なのに歩き出そうとする
• 歩行時に身体軸が揺れ、ふらつく
これは、単に筋力や関節可動域の問題ではなく、自分の身体がどこにあるのか(身体図式)や、どう動かすのが“正しい”のかという感覚そのものが曖昧になっていることが原因です。
特に脳卒中後などでは、片麻痺や高次脳機能障害を伴っており、正しい姿勢を“わかっていない”というレベルでの障害が含まれていることも少なくありません。
⸻
姿勢定位障害の原因
姿勢定位障害はさまざまな要因の影響を受けて発症します。以下に代表的な原因を詳しく解説します。
中枢神経系の障害
• 運動麻痺:体幹・股関節周囲の抗重力筋の出力が低下することで、自然な軸保持が難しくなる。たとえば左片麻痺では、無意識に右側へ体重をかけ、左体幹を浮かせたような姿勢になることが多い。
• 感覚障害:関節位置覚・触覚・深部感覚の低下により、自身の身体の位置や傾きを正確に感じ取れない。結果として、姿勢を「直したつもり」がズレていることも。
• 高次脳機能障害:身体図式の障害(自分の身体の構成や位置関係の認識エラー)、半側空間無視(視覚空間の片側を認識できない)などは、著しい姿勢偏位や非対称性を引き起こす。
筋骨格系の要因
• 脊柱や骨盤の構造的変形(側弯、後弯、骨盤の左右傾斜)
• 関節可動域の制限(特に股関節や胸椎)
• 筋短縮や軟部組織の柔軟性低下
加齢・廃用性変化
• 長期臥床による筋萎縮・感覚低下
• 視覚・前庭覚の低下により、視覚依存が強まり、姿勢調整の戦略が乏しくなる
心理的要因
• 不安や恐怖心による過緊張
• 「倒れたくない」という思いから動きが固まり、逆に重心コントロールが困難になる
これらの因子が単独、または複合的に絡むことで、姿勢定位障害は発生・増悪していきます。
⸻
姿勢定位障害の評価ポイント
姿勢定位障害の評価では、「見た目の姿勢の崩れ」だけではなく、その背景にある要因の分析が非常に重要です。
- アライメント評価(静的・動的)
• 座位・立位での体幹の傾きや骨盤の偏位
• 頭部の位置(前方突出・回旋)
• 動作中の体幹の安定性(立ち上がり、起き上がりなど) - 運動機能(運動麻痺の有無や骨格筋機能の評価)
• 骨格筋機能、いわゆる筋力低下の有無
• 運動麻痺の有無(程度も含めて) - 感覚評価
• 深部感覚(関節位置覚、運動覚)の低下有無
• 体性感覚に対する反応
• 前庭・視覚への依存度 - 認知・高次脳機能スクリーニング
• 半側空間無視(クロックテスト、キャンセレーションテスト)
• 身体図式の障害(身体部位の認知・指示への反応) - 重心動揺・荷重分布評価
• フォースプレートやバランスマットを用いた定量的評価
• 非対称な荷重傾向、反応の遅延、外乱刺激への反応
これらを組み合わせることで、「なぜこの患者さんは姿勢を整えられないのか」という本質に近づくことができます。
姿勢定位障害への介入方法
姿勢定位障害への介入では、「姿勢を正す」ことを目的とするのではなく、“正しい姿勢を自ら感じ取り、再構築できるようにする”ことがポイントです。以下に具体的な介入の視点を紹介します。
- 感覚フィードバックの活用
• 鏡を使った視覚フィードバック:自分の姿勢を視覚的に確認することで、定位のずれを“見える化”します。特に左右の非対称を自覚できていない症例では有効です。
• 触覚刺激・軽擦:体幹や骨盤周囲の筋へ触覚刺激を入れ、感覚の注意を促すことで、身体図式の再構築をサポートします。
• 荷重計や体重計を活用した左右差の認識:対象者自身が重心偏位を視覚的・数値的に把握できるようにします。 - 姿勢誘導・促通
• 体幹・骨盤のポジショニング:座位や立位でセラピストが骨盤や体幹を整えることで、「正しい姿勢ってこういう感覚なんだ」という気づきを引き出します。
• PNF(固有受容性神経筋促通法):姿勢筋の活性化に対し、スロートーンな収縮と感覚入力を同時に与えます。 - 動的課題への応用
• 静的に定位できても、動作中に崩れる例は多くあります。そのため、「座った状態で物を取る」「バランスボール上で体幹を整える」「立ち上がりに手順を変化させる」など、動作の中で姿勢を整える練習が非常に重要です。 - 自主トレーニングの工夫
• 患者自身が自宅でも取り組めるように、“感じることを重視したトレーニング”を指導します。たとえば「毎朝鏡の前で1分間、自分の左右のバランスを確認する」など、小さな習慣が大きな変化につながります。
⸻
理学療法士としての臨床での視点
私たち理学療法士は、つい動作分析や筋力評価に目を向けがちになることもありますが、「なぜこの人は、正しい姿勢をとろうとしないのか?」「なぜ同じ麻痺でも崩れ方が違うのか?」という問いを持つことで、姿勢定位障害という視点が浮かび上がってきます。
僕自身の臨床経験でも、こうした視点を取り入れることで、「なぜこの人は疲れやすいのか」「なぜこの動作がこんなに非効率なのか」がクリアになり、より的確な介入につなげることができました。
また、患者さんの中には“本人が気づいていない不調”として姿勢の偏りが隠れていることがあります。こうした無意識レベルのズレにアプローチできることは、私たち理学療法士の強みです。
⸻
おわりに
姿勢定位障害は、目に見える「姿勢の崩れ」の奥にある、感覚・運動・認知の複雑な統合機能の障害です。
それを理解し、評価し、介入する力こそ、理学療法士としての“臨床の深さ”を育ててくれるものだと感じます。
もし、日々のリハビリの中で「なぜこの人は姿勢が整わないのか?」と感じたことがあれば、ぜひ今回の記事をヒントにして、姿勢定位障害の視点から評価・介入を見直してみてください。きっと、これまで見えていなかった景色が広がるはずです。
もっとより知識を深めたい方へ
「臨床理学Lab」ではより専門的な記事を作成しています。ここでは全ての有料記事を読むことができます。
ここは、単なる情報提供の場ではありません。
あなたの疑問や悩みを共有し、共に考え、共に成長できる場です。
単なる知識の提供ではなく、臨床で使える「考え方」を身につけることを重視していきたいと思います。
「この評価の結果から、次に何をすべきか?」
「この患者にはどんなアプローチが適切なのか?」
といった問いに対し、論理的に答えを導き出せるようになることを目標としています。
臨床推論を深め、評価力・判断力を向上させるために、一緒に学んでいきましょう!
👇