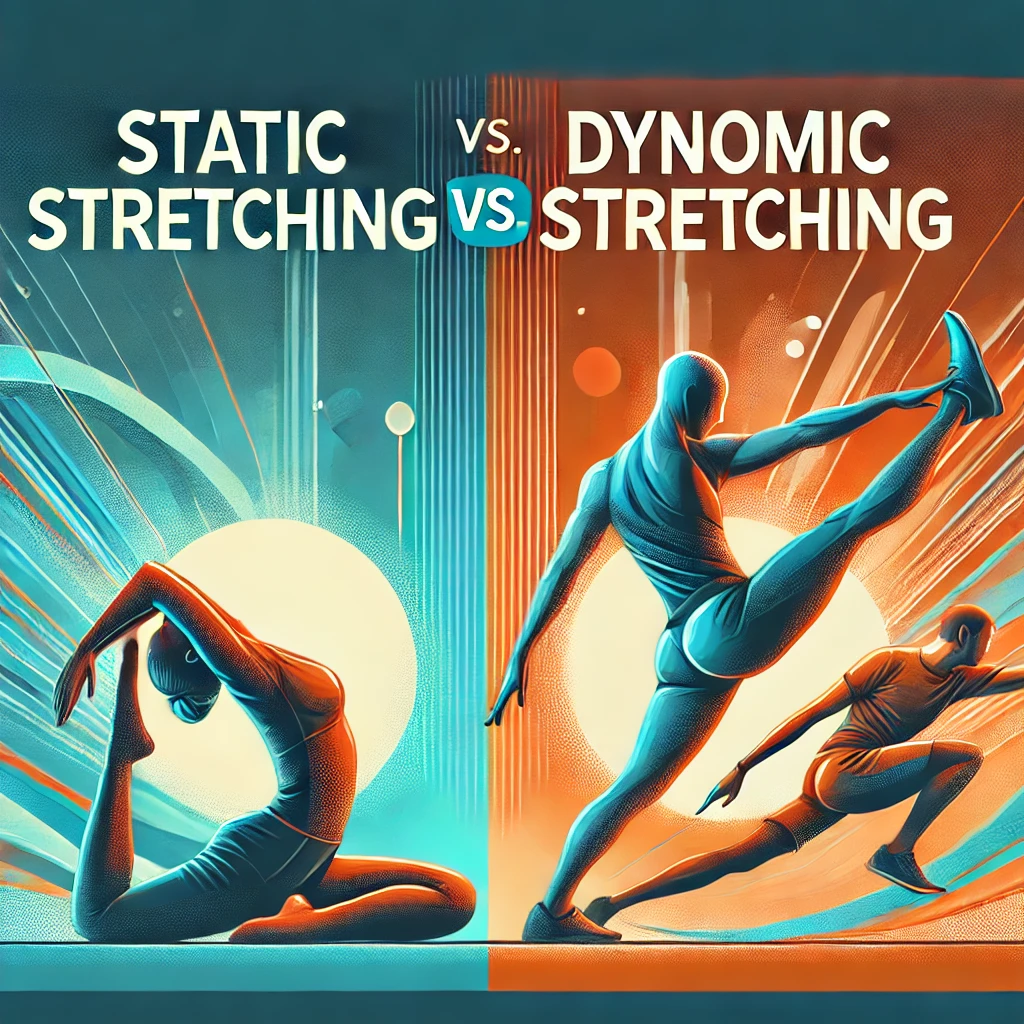はじめに
理学療法士として患者さんの可動域向上や運動機能の改善に携わる中で、「ストレッチの方法をどのように選択すべきか?」と悩んだことはありませんか?
ストレッチにはさまざまな種類がありますが、特に「スタティックストレッチ(静的ストレッチ)」と「ダイナミックストレッチ(動的ストレッチ)」の違いについて、科学的な根拠をもとに理解しておくことは重要です。
例えば、運動前にスタティックストレッチを行うと筋出力が低下し、パフォーマンスに悪影響を与える可能性があることが知られています。一方、ダイナミックストレッチは筋温を上昇させ、関節の可動域を拡大しつつ、筋力の低下を引き起こしにくいといわれています。

こんな疑問はありませんか?
- リハビリ場面ではどちらを使うべき?
- 患者さんに合わせた最適なストレッチは何か?

今回は、スタティックストレッチとダイナミックストレッチの違いやそれぞれの効果を論文を交えて詳しく解説し、臨床での適用方法を考えていきます。
スタティックストレッチとダイナミックストレッチの基本について、それぞれのストレッチの特徴を整理しておきましょう。
こんな方におすすめの記事です
• 理学療法士・作業療法士: 臨床でのストレッチの使い分けを学びたい人
• スポーツトレーナー・アスリート: パフォーマンス向上のために最適なストレッチを知りたい人
• リハビリに関わる医療従事者: 患者への適切なストレッチ指導を行いたい人
• 運動指導者・フィットネストレーナー: 効果的なウォームアップ・クールダウンの方法を知りたい人
スタティックストレッチ(静的ストレッチ)とは?
スタティックストレッチとは、特定の筋肉や筋群を一定の位置で伸ばし、その姿勢を10〜60秒程度保持するストレッチ方法です。一般的に、運動後のクールダウンやリラクゼーションの目的で用いられることが多いです。
スタティックストレッチの主な効果
✅ 柔軟性の向上:持続的な伸張により、筋肉の伸張性が改善される
✅ 筋の緊張を低下させる:副交感神経の働きが優位になり、リラックス効果が期待できる
✅ リハビリテーションへの応用:関節可動域制限がある患者に対して有効
デメリット
⚠ 運動前に行うと筋出力が低下する可能性:筋紡錘の感受性が低下し、筋収縮の効率が落ちることが指摘されている
⚠ 急性期のリハビリでは慎重な適用が必要:炎症がある部位に対して無理なストレッチは逆効果
臨床での活用例
• 関節可動域制限がある患者に対する柔軟性向上目的のストレッチ
• 神経筋疾患や脳卒中後の筋緊張異常を抑制するためのアプローチ
• リハビリ後のクールダウンや自宅でのセルフストレッチ指導
ダイナミックストレッチ(動的ストレッチ)とは?
ダイナミックストレッチとは、関節を大きく動かしながら筋肉を伸ばしていくストレッチ方法です。反復的な動作を取り入れることで、筋温を上昇させ、神経-筋連携を高めることができます。
ダイナミックストレッチの主な効果
✅ 運動前のウォームアップに最適:筋温を上昇させ、血流を促進する
✅ 関節可動域の拡大:動的な動きによって、より実際の運動に近い形で可動域を改善できる
✅ パフォーマンス向上:筋力低下を引き起こさず、爆発的な力を発揮しやすくする
デメリット
⚠ 適切なフォームを理解しないと怪我につながる可能性:反動を使いすぎると過度なストレスがかかる
⚠ 慢性疼痛がある患者には慎重な適用が必要:急な動作が痛みを誘発することがある
臨床での活用例
• スポーツ選手やアスリートのリハビリテーション
• 歩行訓練の前に股関節・膝関節の可動域を拡大する目的で使用
• 高齢者のバランストレーニングや転倒予防プログラム
⸻
論文から見るストレッチの効果
1. 可動域の向上に関する研究
• 論文:「大腿四頭筋に対するスタティックストレッチングおよびダイナミックストレッチングが膝屈曲可動域と膝伸展筋力に与える効果」(J-STAGE)
• 結果:
• スタティックストレッチとダイナミックストレッチはどちらも可動域を改善するが、スタティックストレッチ後は筋力が低下した。
• ダイナミックストレッチは筋出力を維持しつつ可動域を向上させる傾向がある。
2. 筋力や運動パフォーマンスへの影響に関する研究
• 論文:「ダイナミックストレッチングとスタティックストレッチングの組み合わせが筋出力に与える影響」(J-STAGE)
• 結果:
• 運動前のウォームアップとしてダイナミックストレッチを用いることで、筋力低下を防ぎつつ柔軟性を向上させることができる。
• スタティックストレッチ単独では筋出力が低下する可能性があるため、競技前の使用は慎重に考えるべき。
まとめ
1. スタティックストレッチは柔軟性向上に適しているが、筋力低下を招く可能性があるため運動前の使用には注意が必要。
2. ダイナミックストレッチは筋力低下を引き起こさず、運動前のウォームアップとして最適。
3. リハビリテーションでは、患者の状態や目標に応じて使い分けることが重要。
⸻
おわりに
ストレッチは一見シンプルな介入のように思われがちですが、その選択がリハビリの成果に大きく影響します。科学的根拠に基づいた適切な方法を選択することが、より良い臨床実践につながります。
今後の記事では、実際のストレッチングの実践方法や、リハビリでの応用例をより詳しく紹介する記事も検討中です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!