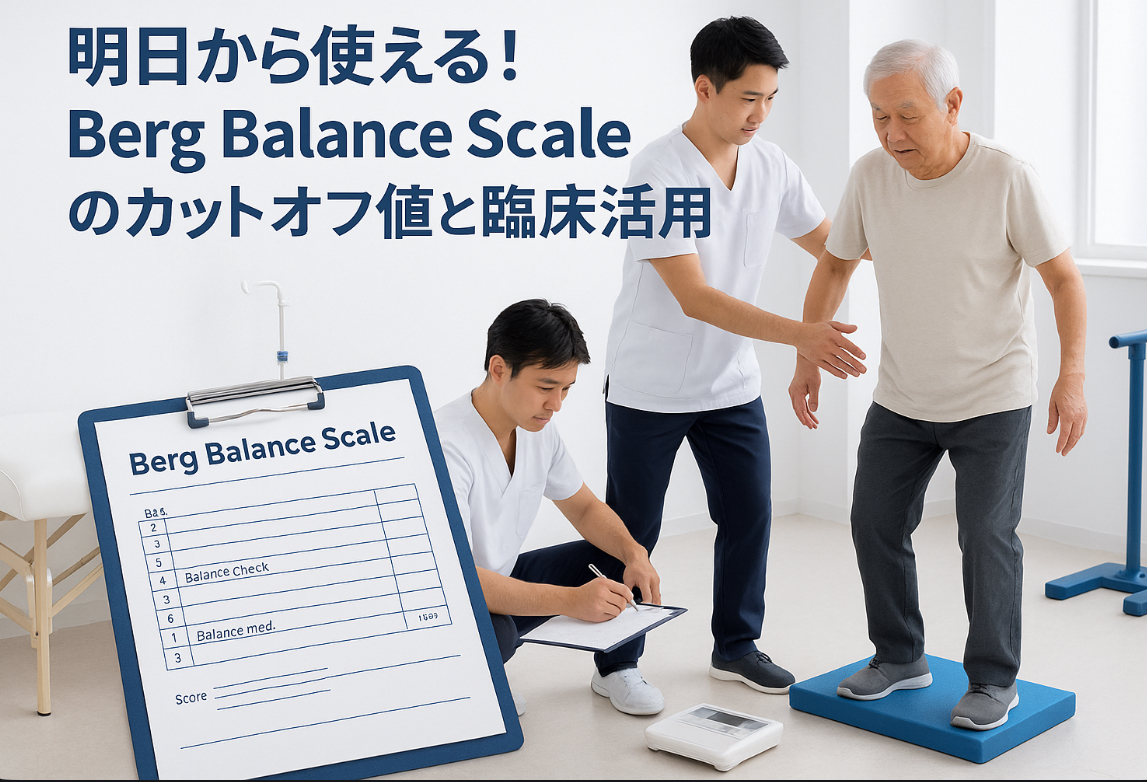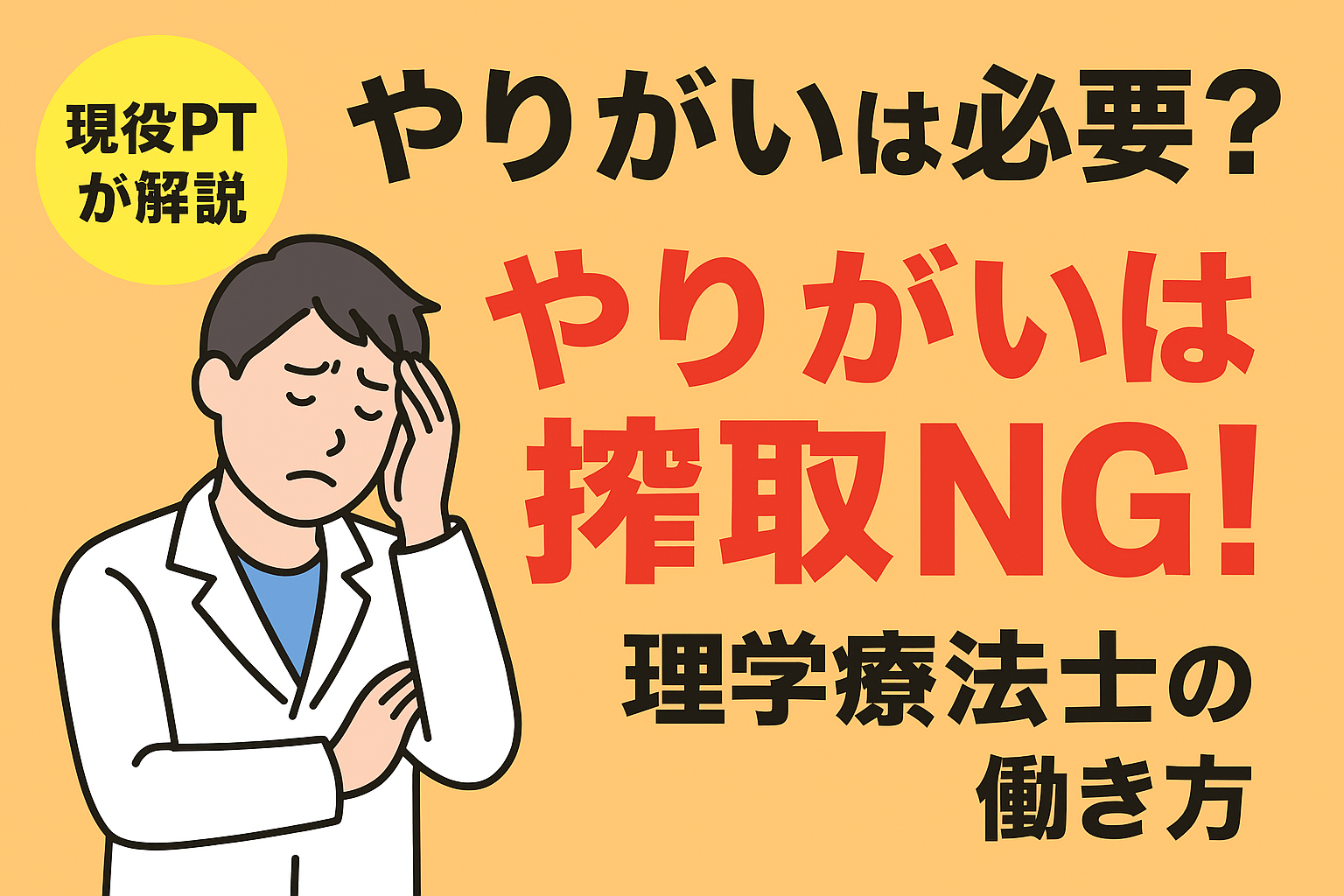はじめに
「担当している患者さんのバランス評価でBBSを使っているけど、合計点を出して『転倒リスクが高いですね』で終わってしまっている…」
「BBSの評価結果を、もっと具体的にリハビリプログラムに活かす方法が知りたい」
若手から中堅の理学療法士・作業療法士の皆さん、こんな悩みを抱えていませんか?
バランス能力評価のゴールドスタンダードとして知られるBerg Balance Scale (BBS) / バーグバランススケールは、正しく解釈することで、患者様の転倒リスクを予測し、効果的な治療プログラムを立案するための強力な武器になります。
この記事では、BBSの各評価項目の採点・観察ポイントから、臨床で最も重要なカットオフ値の解釈、そして評価結果を具体的な治療に繋げるための思考プロセスまで、理学療法士の視点で解説します。
お知らせ
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

なぜBBSは臨床で重要なのか?基本をおさらい
まず、BBSがなぜこれほど多くの臨床現場で使われているのか、その基本と特徴を再確認しましょう。
BBS(Berg Balance Scale)とは?
BBSは、カナダの理学療法士であるKatherine Berg氏らによって開発された、バランス能力を測定するための評価バッテリーです。以下の14項目の課題で構成されており、それぞれ0点〜4点の5段階で評価、合計56点満点となります。
- 静的バランス能力(例:立位保持、閉眼立位)
- 動的バランス能力(例:立ち上がり、リーチ、振り返り、移乗)
BBSの特徴と利点
- 手軽さ:ストップウォッチ、椅子、定規など、特別な器具がなくても実施できます。
- 信頼性・妥当性:多くの研究でその信頼性と妥当性が証明されており、世界中で広く使用されています。
- 適用範囲の広さ:高齢者はもちろん、脳卒中、パーキンソン病、多発性硬化症など、様々な疾患の患者様に適用可能です。
BBSの目的は、単に点数をつけることではありません。「転倒リスクのスクリーニング」「バランス能力の定量的評価」「リハビリテーション効果の判定」という重要な役割を担っています。
評価の精度を上げる!14項目の実施・採点ポイント
ここでは、BBSの各項目について、マニュアル通りの採点だけでなく、理学療法士として観察すべき「代償動作」や「動作の質」に焦点を当てて解説します。
【静的バランス】基礎的な安定性の評価
静的バランスは、すべての動作の基礎となります。動揺の有無だけでなく、どのような戦略で姿勢を保っているかを見極めましょう。
- 2. 立位保持 / 3. 座位保持
- ポイント:時間だけでなく、体幹の動揺や足底からの非対称な入力がないか観察します。「2分間安全に立位保持できれば、3. 座位保持は満点(4点)」というルールも忘れずに。
- 6. 閉眼での立位保持
- 指示:「目を閉じて10秒間立ってください。」
- ポイント:視覚情報を遮断した際に、**足関節戦略(Ankle Strategy)や股関節戦略(Hip Strategy)**が適切に機能しているか評価します。開眼時との動揺の差が大きい場合、視覚への依存度が高いと考えられます。
- 7. 両足を揃えての立位保持
- 指示:「足を揃えて、何もつかまらずに立っていてください。」
- ポイント:支持基底面を狭くした際の安定性を評価。ふらつきを抑えるために、体幹を側屈させたり、腕を広げたりする代償動作が見られないかチェックします。
【動的バランス①】基本的な動作の評価
日常生活に不可欠な起居動作。スピードや遂行の可否だけでなく、動作の滑らかさが重要です。
- 1. 立ち上がり / 4. 着座
- ポイント:手すりや膝に手をつくのは減点対象です。特に着座では、「ドスン」とコントロールせずに座る場合は高得点にはなりません。体幹の前傾と下肢の筋力を使って、滑らかに重心をコントロールできているか評価します。
- 5. 移乗動作
- ポイント:殿部をわずかに持ち上げて素早く移る**「ピボット移乗」ができているか、一度立ち上がってから向きを変える「スタンディング移乗」**になっているかなど、戦略を観察します。体幹の回旋が不十分で、足が引っかかっていないかも重要な視点です。
【動的バランス②】重心移動と予測的姿勢制御の評価
転倒の多くは、動いている最中に重心をコントロールできなくなることで生じます。
- 8. 両手前方リーチ
- 指示:腕を90°挙げ、できるだけ前方に手を伸ばしてください。
- ポイント:距離だけでなく、踵が浮いていないか、股関節が過度に屈曲していないかも確認します。これは前方への**予測的姿勢制御(APA)**を評価する重要な項目です。
- 9. 拾い上げ(床の物を拾う)
- ポイント:股関節と膝をしっかり曲げて、低い重心で安定して拾えるか、あるいは膝を伸ばしたまま不安定な姿勢で行っているかを見ます。拾った後、スムーズに立位姿勢に戻れるかも評価に含みます。
- 10. 振り返り(左右の肩越しに後ろを振り向く)
- ポイント:頸部だけでなく、胸椎の回旋とそれに伴う骨盤・下肢へのスムーズな体重移動が行えているかを評価します。「片方だけやりにくい」といった左右差は、体幹機能の問題や半側空間無視など、高次脳機能障害の可能性も示唆します。
【動的バランス③】より高度な課題
これらの項目は、地域生活や屋外歩行に必要な、より高度なバランス能力を評価します。
- 11. 360°方向転換(1回転)
- 指示:「完全に一回転回ってください。その後、逆方向にも一回転。」
- ポイント:**小刻みなステップ(パーキンソニズムなど)**になっていないか、軸足が安定しているか、めまいやふらつきが生じないかを確認します。4秒という時間制限もポイントです。
- 12. 段差交互踏み換え
- ポイント:リズミカルに足を交互に出せるか、股関節屈筋や足関節背屈筋の筋力、そして協調性が求められます。疲労による代償が出やすい項目でもあります。
- 13. 継ぎ足立位 / 14. 片脚立位
- ポイント:支持基底面が極端に狭くなる高難易度課題です。中殿筋の機能や足関節の安定性がダイレクトに現れます。どちらの足が不安定か、どんな代償戦略(体幹の側屈など)を使っているかを詳細に分析することが治療に繋がります。
【最重要】カットオフ値を読み解き、転倒リスクを予測する
BBSの合計点から、患者様の転倒リスクや歩行自立度を客観的に判断するための指標がカットオフ値です。これは必ず覚えておきましょう。
転倒リスクのカットオフ値
臨床で最も広く使われているカットオフ値は以下の通りです。
- 45点以下:転倒リスクが高い
- 覚え方:「45点以下は危ない」と覚えておけば、臨床でのスクリーニングに役立ちます。
より詳細な層別化として、以下の基準も参考にしてください。
- 41~56点:転倒リスク(低)
- 21~40点:転倒リスク(中)
- 0~20点:転倒リスク(高)
歩行自立度の予測
- 40点前後: 杖などの歩行補助具なしでの屋外歩行が可能になるかどうかの目安の一つとされています。
- 20点以下: 院内でも車椅子での移動が中心となる可能性が高く、介助下での歩行練習が必要なレベルと考えられます。
【臨床での注意点】
カットオフ値はあくまで目安です。認知機能、服用している薬(降圧薬、睡眠薬など)、視力、本人の性格(衝動性など)、家屋環境といった多角的な視点から総合的に転倒リスクを判断することが、我々理学療法士の専門性です。
評価を治療に繋げる!BBS活用実践ガイド
「評価はしたけれど、次のリハビリで何をすればいいか分からない…」とならないために、BBSの結果を治療プログラムに繋げる思考プロセスをケーススタディで見ていきましょう。
ケーススタディ1:前方への重心移動が苦手な症例
- BBSの失点項目:「1. 立ち上がり(3点)」「8. 両手前方リーチ(2点)」「9. 拾い上げ(1点)」
- 考えられる問題点:
- 体幹を前に倒すことへの恐怖心
- 足関節の背屈可動域制限
- 大殿筋や大腿四頭筋の筋力・遠心性収縮のコントロール低下
- 治療プログラム例:
- 座位でのリーチ動作訓練:前方の目標物に手を伸ばす練習で、骨盤前傾と体幹前傾を促す。
- 足関節背屈ストレッチ:立ち上がりやリーチ時の足関節の可動性を確保する。
- コントロールされた着座練習:セラピストの合図でゆっくり座る練習を行い、下肢の遠心性収縮を鍛える。
ケーススタディ2:回旋やステップ動作が苦手な症例
- BBSの失点項目:「10. 振り返り(2点)」「11. 360°方向転換(1点)」「13. 継ぎ足立位(2点)」
- 考えられる問題点:
- 胸椎の可動性低下、体幹の固定性低下
- 素早いステップを出すためのステップ戦略の遅延
- 片脚立位期の不安定性(中殿筋機能不全など)
- 治療プログラム例:
- 座位での体幹回旋運動:ボールの受け渡しなどで、骨盤を安定させた状態での体幹回旋を促す。
- 多方向へのステップ訓練:床に目印をつけ、「右斜め前にステップ」など、様々な方向へ素早く足を出す練習を行う。
- 不安定な支持面での立位保持:バランスパッドなどを使用し、足関節・股関節戦略を賦活する。
このように、合計点だけでなく「どの項目で、なぜ失点したのか」を分析することで、個別性の高いリハビリプログラムが立案できます。
まとめ
今回は、Berg Balance Scale (BBS) の評価ポイントから臨床での活用法までを解説しました。
- BBSは静的・動的バランスを網羅した、手軽で信頼性の高い評価法
- 転倒リスクのカットオフ値「45点」は必ず覚えておくべき指標
- 評価の鍵は、合計点だけでなく「どの項目で失点したか」の動作分析にある
- 失点項目の背景にある機能障害を推測し、個別性のある治療プログラムを立案しよう
BBSを深く理解し、臨床で使いこなすことは、患者様の転倒を予防し、安全で質の高い生活を支えるための大きな一歩です。明日からの臨床で、ぜひ今回のポイントを意識してBBS評価に取り組んでみてください。