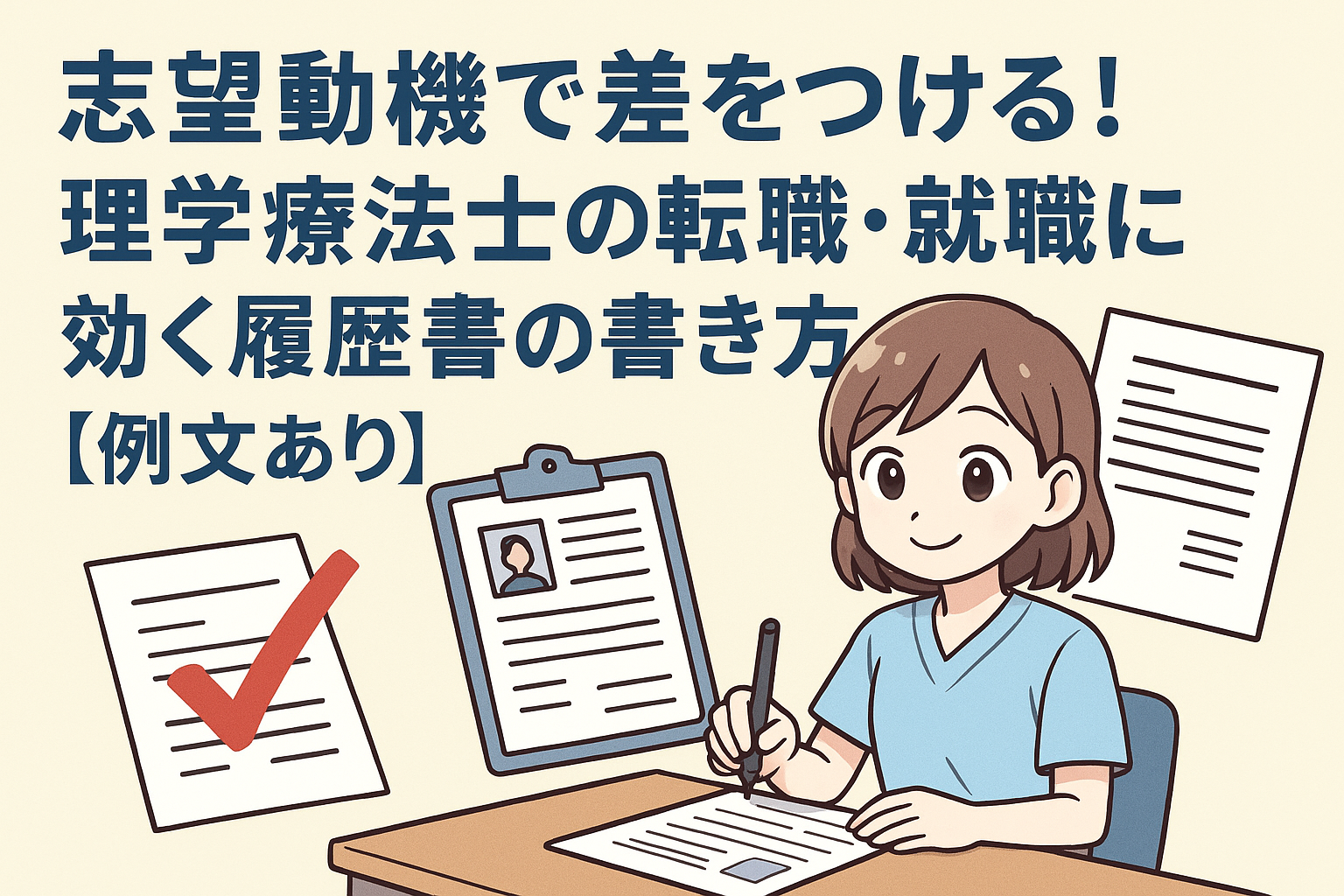はじめに
「先生、リハビリしないとどうなるの?」「なんで動かないといけないの?」
患者さんからこう質問された時、自信を持って分かりやすく説明できていますか?
長期臥床の患者さんが見せる筋力低下や関節拘縮。私たちは日常的に「廃用症候群」という言葉を使いますが、その背景にある生理学的なメカニズムについて説明できますか?
本記事では、「なぜ動かないと身体機能が低下するのか」という根本的な問いに、生理学的な根拠をもって考えていきます。
廃用症候群によって身体の各システムに何が起こるのかを整理し、知識をアップデートし、日々の臨床に活かしていきましょう!
この記事を読めば、患者さんやご家族への説明に説得力が増し、早期離床アプローチの重要性を再認識できるはず✨
明日からの臨床が変わる、廃用の知識を深掘りしていきましょう。
\より専門的な記事は臨床理学Lab/
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
メンバーシップ(月額プラン)に登録すると、有料記事を含む全コンテンツが読み放題になります。

臨床理学Lab|リハの地図~学びnote~
**「臨床理学Lab」**は、理学療法における基本的な知識の向上に加え、評価と臨床推論の強化を目的としたメンバーシップです。「なぜこの評価をするのか?」「その結果から何がわかり、どう治療に活かせるのか?」深く掘り下げ、現場で実践できる力を養...
「廃用症候群」とは? – 今さら聞けない定義の再確認
- 廃用症候群(Disuse Syndrome)の定義
- 過度な安静や活動性の低下によって、心身の様々な機能が低下する状態の総称。
- 生活不活発病との違いと関連性
- 原因(病気・怪我など)によらず、生活が不活発なことによって生じる全身の機能低下を指す「生活不活発病」という広い概念にも触れ、PTが関わる領域の広さを示す。
- 「全身病」としての廃用症候群:
- 単なる筋力低下や関節の問題ではなく、循環器、呼吸器、精神機能にまで影響が及ぶ「全身病」であることを強調。
システム別に徹底解説!「動かない」ことで身体に起こる変化
(※このセクションでは、図やイラストを交えるとさらに分かりやすくなります)
- ① 筋骨格系の変化 – 最も目に見える機能低下
- 筋萎縮・筋力低下
- メカニズム: 筋タンパクの「合成低下」と「分解亢進」のバランスが崩れる。特に抗重力筋(脊柱起立筋、大腿四頭筋、下腿三頭筋など)が急速に萎縮する理由。
- 具体的なデータ: 「1週間の絶対安静で筋力は10~15%低下し、3~5週間で半減する」といった具体的な数値を示し、危機感を醸成。
- 関節拘縮
- メカニズム: 関節周囲の結合組織(関節包、靭帯など)の水分量低下とコラーゲン線維の異常架橋(クロスリンク)形成。滑走性の低下。
- ポイント: なぜ不動肢位が拘縮を助長するのかを解説。
- 骨萎縮(骨粗鬆症)
- メカニズム: 骨への力学的ストレス(メカニカルストレス)の消失。ウォルフの法則(Wolff’s law)を引用し、骨芽細胞の活動低下と破骨細胞の活動亢進を説明。
- リスク: 骨折リスクだけでなく、高カルシウム血症や尿路結石のリスクにも言及。
- 筋萎縮・筋力低下
- ② 循環器系の変化 – 生命に直結するリスク
- 心機能低下と循環血液量の減少
- メカニズム: 心筋の萎縮、心拍出量の低下。なぜ安静臥床で身体が「省エネモード」になるのか。
- 起立性低血圧
- メカニズム: 圧受容体反射の感度低下など、循環調節機能の破綻。急に起き上がれない身体になる過程を解説。
- 深部静脈血栓症(DVT)
- メカニズム: ヴィルヒョウの3徴(血流のうっ滞、血管内皮障害、血液凝固能の亢進)と絡めて解説。特に筋ポンプ作用の消失が致命的であることを強調。肺血栓塞栓症(PTE)の危険性もセットで説明。
- 心機能低下と循環血液量の減少
- ③ 呼吸器系の変化 – 肺炎リスクの増大
- 拘束性換気障害
- メカニズム: 呼吸筋(横隔膜、肋間筋)の筋力低下と胸郭可動性の低下。
- 沈下性肺炎・無気肺
- メカニズム: 痰の貯留と喀出能力の低下(線毛運動の機能不全)。背側肺への換気血流不均等が起こる理由。
- 拘束性換気障害
- ④ その他の重要な変化
- 精神・神経系: 見当識障害、抑うつ、せん妄。感覚入力の減少が脳機能に与える影響。
- 消化器系: 食欲不振、便秘。
- 皮膚系: 褥瘡発生リスクの増大。

新人PTがまず押さえるべき!廃用症候群とは?症状・評価・リハビリの基本
はじめに「廃用症候群」は、臨床の現場で理学療法士が非常によく出会う病態の一つです。ベッド上での生活が続いていたり、安静が長期に及ぶと、驚くほど早く筋力や心肺機能が低下してしまいます。新人理学療法士にとって、「なぜこの人は歩けなくなったのか?...
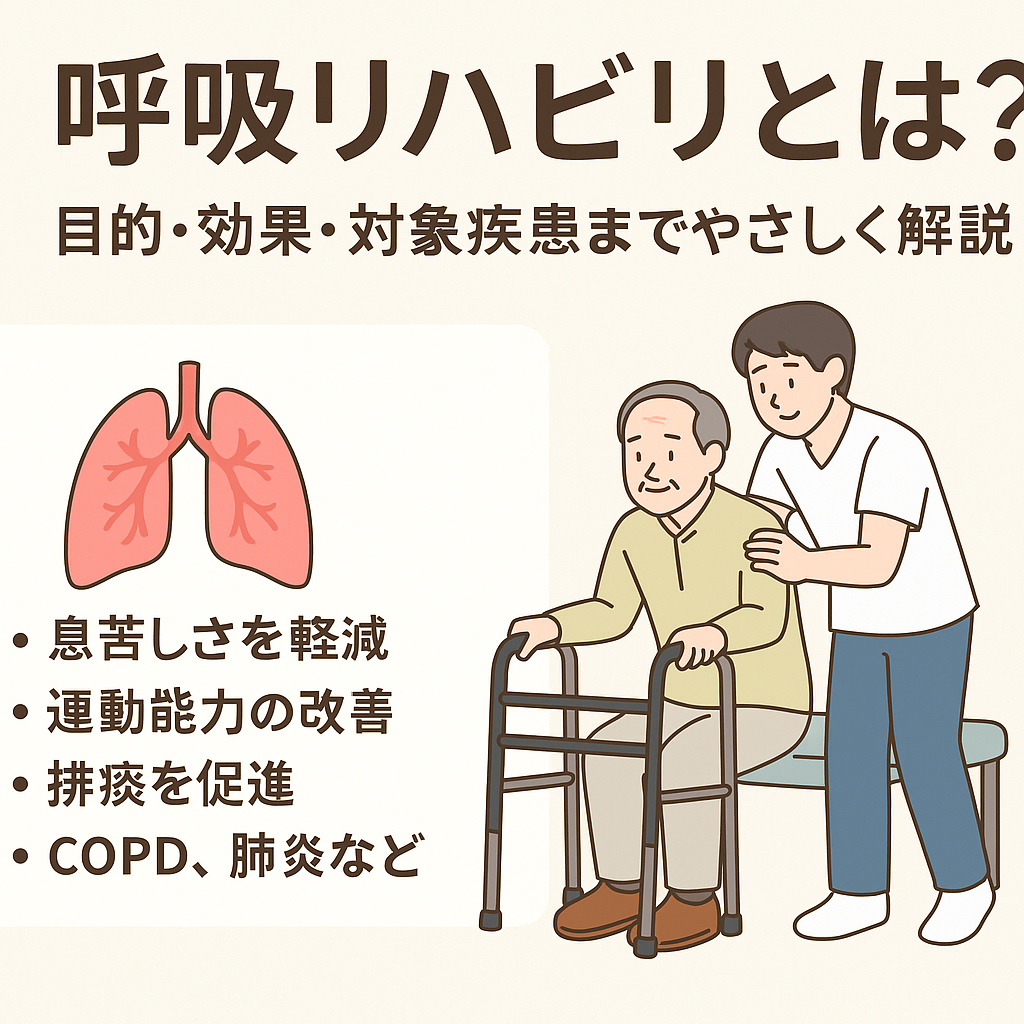
【初心者向け】呼吸リハビリとは?目的・効果・対象疾患までやさしく解説!
はじめに:なぜ今「呼吸リハビリ」が注目されているのか?近年、呼吸リハビリテーション(呼吸リハ)への注目が高まっています。高齢化社会が進み、慢性呼吸器疾患や肺炎などの患者が増加する中で、呼吸機能を改善し、QOL(生活の質)を維持・向上させるリ...
理学療法士として廃用とどう向き合うか? – 予防と対策
- 「動かす」ことが最良の薬である根拠
- セクション2で解説した各メカニズムに対し、「運動」がどのように作用するかを具体的に解説。
- 例:筋収縮はタンパク合成を促すシグナルになる。関節運動は滑液の循環を促し、結合組織の伸張性を保つ。重力負荷は骨を強くするスイッチを入れる。筋ポンプは血栓予防の要である、など。
- セクション2で解説した各メカニズムに対し、「運動」がどのように作用するかを具体的に解説。
- 明日から使える!患者さんへの説明フレーズ集
- 専門用語を使わずに、廃用のリスクと運動の必要性を伝えるための比喩表現や言い回しを紹介。
- 「筋肉は使わないとすぐにサボることを覚えてしまいます。貯金と同じで、使うのは簡単ですが貯めるのは大変なんです」
- 「関節は、自転車のチェーンと一緒です。動かして油をささないと、すぐに錆び付いて固まってしまいますよ」
- 「寝たきりだと、足の血の流れが川のように淀んで、血の塊(血栓)ができやすくなるんです」
- 専門用語を使わずに、廃用のリスクと運動の必要性を伝えるための比喩表現や言い回しを紹介。
- 予防のためのアプローチの視点
- 評価の重要性: 廃用のサインを見逃さないための評価項目(筋力、ROM、SpO2、血圧、精神状態など)を再確認。
- 多職種連携: 看護師(体位変換、離床計画)、栄養士(栄養状態)、医師との情報共有の重要性を強調。チームで廃用を防ぐという視点。
【まとめ】
- 廃用症候群は、単なる筋力低下ではなく、全身のシステムに悪影響を及ぼす深刻な病態である。
- そのメカニズムは、筋タンパクの代謝、結合組織の性質、循環・呼吸の生理学など、科学的な根拠に基づいている。
- 廃用のメカニズムを深く理解することは、私たち理学療法士のアプローチに根拠と説得力を与えてくれます。
- 「ただ動かす」のではなく、「なぜ動かすのか」を常に意識し、患者さん一人ひとりの「動く」価値を最大限に引き出す専門家であり続けましょう。
参考文献
リンク