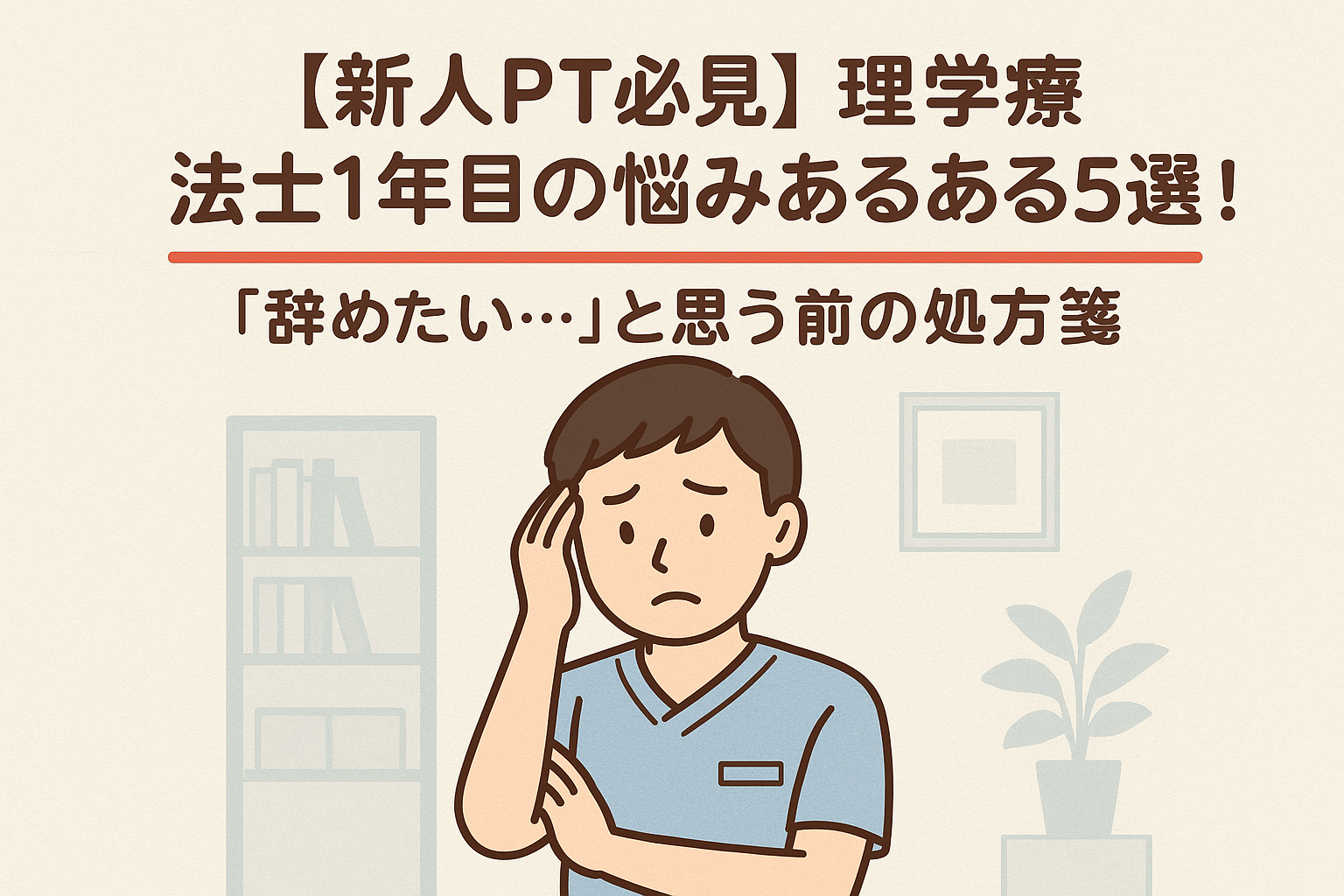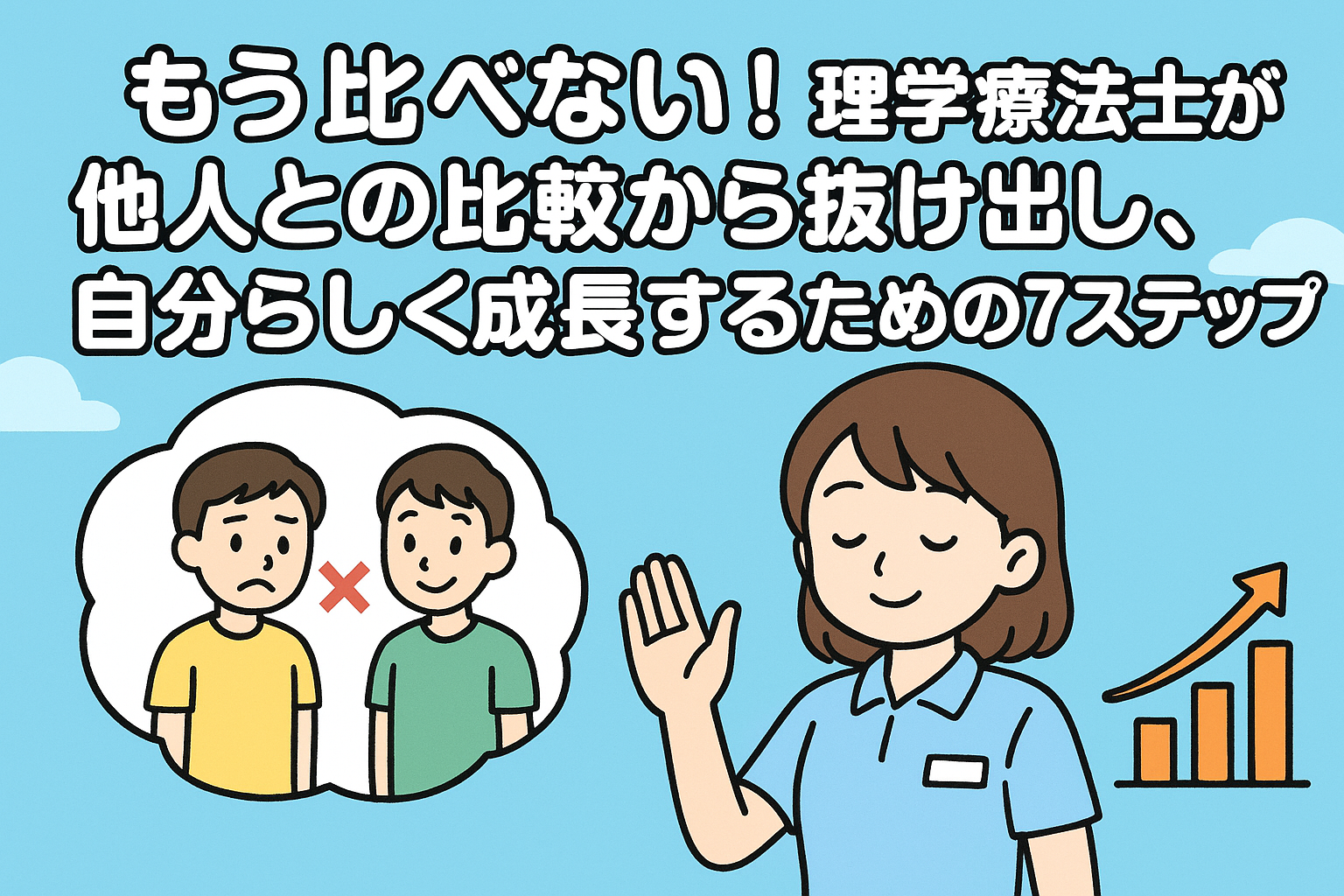はじめに
「先輩、この脳卒中の患者さんのAFO、どれがいいですか…?」
「装具をつけたのに、いまいち歩き方が良くならない…なぜだろう?」
「エビデンスに基づいた装具選択をしたいけど、何を参考にすれば…?」
理学療法士として臨床に立つ中で、こんな風に短下肢装具(AFO)の選択に頭を悩ませた経験はありませんか?
AFOは歩行改善に欠かせないツールですが、種類が多く、患者さん一人ひとりに最適なものを選ぶのは本当に難しいですよね。
この記事では、そんなあなたの悩みを解決するヒントを、お届けします。この記事を読めば、なぜAFO選びに迷ってしまうのか、そして明日からの臨床でどう考えれば良いのか、その第一歩がわかります。
なぜ、私たちのAFO選びは難しいのか? – それは単なる「固定具」ではないから
臨床でAFOがうまく機能しない時、私たちはつい「この装具は合わないのかな?」と考えてしまいがちです。しかし、問題の本質はもっと深いところにあります。
AFOは、単に足首を固定するだけの道具ではありません。歩行という複雑な運動システムに直接介入する「治療デバイス」です。
つまり、AFOを使いこなすには、
- 装具のメカニズムの知識
- 患者さんの歩行特性の分析力
- 筋力や疾患、生活環境まで考慮する臨床思考
これら全てが不可欠なのです。この視点が抜けていると、「なんとなく」で装具を選んでしまい、思うような結果に繋がらないのです。
【サクッと理解】AFOの代表的な5つの種類と役割
「種類が多すぎて覚えられない!」という方のために、まずは代表的なAFOをざっくりと整理しましょう。あなたの担当する患者さんにはどれが合いそうか、イメージしながら読んでみてください。
- 金属支柱付きAFO
- 特徴: とにかく頑丈!筋緊張が強い方や膝折れリスクが高い方に。
- プラスチック製AFO(シューホーン型など)
- 特徴: 軽くて目立たない!日常生活にフィットさせたい軽度麻痺の方に。
- 継手付きAFO(タマラックなど)
- 特徴: 関節の動きを補助・制御!歩行効率UPを狙える優等生。
- 油圧制動式AFO
- 特徴: ハイテクな油圧制御!不整地や長距離を歩く方の強い味方。
- PTB(膝蓋腱支持)型AFO
- 特徴: 体重を肩代わり!骨折後のリハビリで安全な歩行をサポート。
どうでしょうか?これだけでも、それぞれの「得意なこと」が違うのがわかりますよね。
メンバー限定記事ではこれらのメリット・デメリット、そして具体的な実践例まで踏み込んで解説しています。
「とりあえずAFO」はNG!疾患によって目的が全く違う
AFO選択で最も重要なのが、「疾患や病態によって、AFOに求める役割が全く異なる」という視点です。
例えば、代表的な2つの疾患を比べてみましょう。
- 脳卒中(片麻痺)の場合
- 課題: 下垂足による「つまずき」+立脚期の「膝折れ」
- AFOの目的: 遊脚期の足関節背屈補助 + 立脚期の足関節・膝の安定化
- 末梢神経障害(腓骨神経麻痺)の場合
- 課題: 下垂足(ドロップフット)による「つまずき」
- AFOの目的: 遊脚期の足関節背屈補助(クリアランス確保)がメイン
このように、同じ「歩きにくさ」でも、その原因と対策は異なります。脳卒中なら立脚期の安定性も重要ですが、腓骨神経麻痺なら遊脚期の補助が主目的になります。
この違いを理解することが、効果的な介入への第一歩です。
効果を最大化するプロの「評価視点」とは?
最適なAFOを選んだら、それで終わりではありません。本当に大切なのは、装着後の変化を正しく評価し、調整に繋げることです。
プロの理学療法士は、以下の3つの視点で評価を行っています。
- 歩行パターンの観察: 歩行速度や歩幅、クリアランス、膝折れは改善したか?(動画撮影も有効!)
- 筋活動の変化: 装具によって必要な筋肉の活動が過度に抑制されていないか?
- 患者さんの使用感: 「痛みはないか?」「歩きやすいか?」という主観的なフィードバック
ただ装着させるだけでなく、この評価サイクルを回すことで、AFOの効果を最大化し、患者さんの歩行を「デザイン」することができるのです。
もっと深く学び、臨床で結果を出したいあなたへ
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
AFOの奥深さと、その可能性を感じていただけたのではないでしょうか。
今回ご紹介したのは、有料note記事のほんの一部です。
もしあなたが、
- 「患者さん一人ひとりに最適なAFOを、自信を持って提案できるようになりたい」
- 「エビデンスに基づいたリハビリで、周囲から信頼されるセラピストになりたい」
- 「AFOの知識をアップデートして、臨床の引き出しを増やしたい」
そう強く願うなら、ぜひ本編の記事を手に取ってみてください。
▼メンバー限定記事では、より深掘りした内容を▼
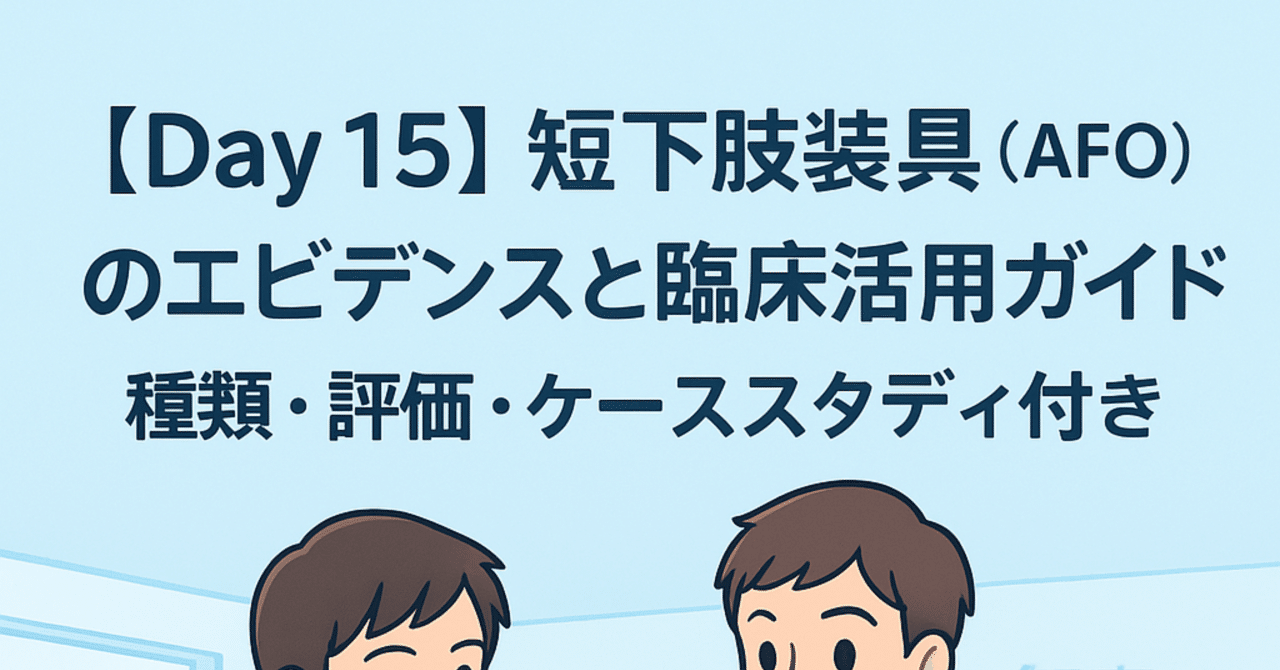
✅ 全種類のAFOを徹底比較! メリット・デメリット、臨床での使い分けが図解でわかる
✅ 最新の論文エビデンスを網羅! 歩行速度・歩幅への影響を根拠を持って説明できる
✅ 脳卒中、脳性麻痺など疾患別の最適戦略 がわかる
✅ リアルなケーススタディで、評価から装具選択までの思考プロセスを追体験できる
✅ 明日から使える評価視点と、臨床選択フローで実践力が身につく
「なんとなく」の装具選びは、もう終わりにしませんか?
あなたの臨床を次のステージへ引き上げる知識が、ここに詰まっています。
【お得なご案内】
この記事だけでなく、もっと継続的に学びを深めて、臨床での成果を出し続けたい。
そんな向上心のあるあなたに、特別なご案内です。
月額メンバーシップにご加入いただくと、この記事を含む、過去に公開された全ての専門記事が**“いつでも・すべて”読み放題**になります。
毎月のコーヒー1杯を、一生モノの臨床スキルに変えませんか?
スターバックスで一息つくのと同じくらいの自己投資で、明日からの臨床に自信が持てる知識が手に入ります。本気で学びたいあなたのためのプランです。