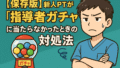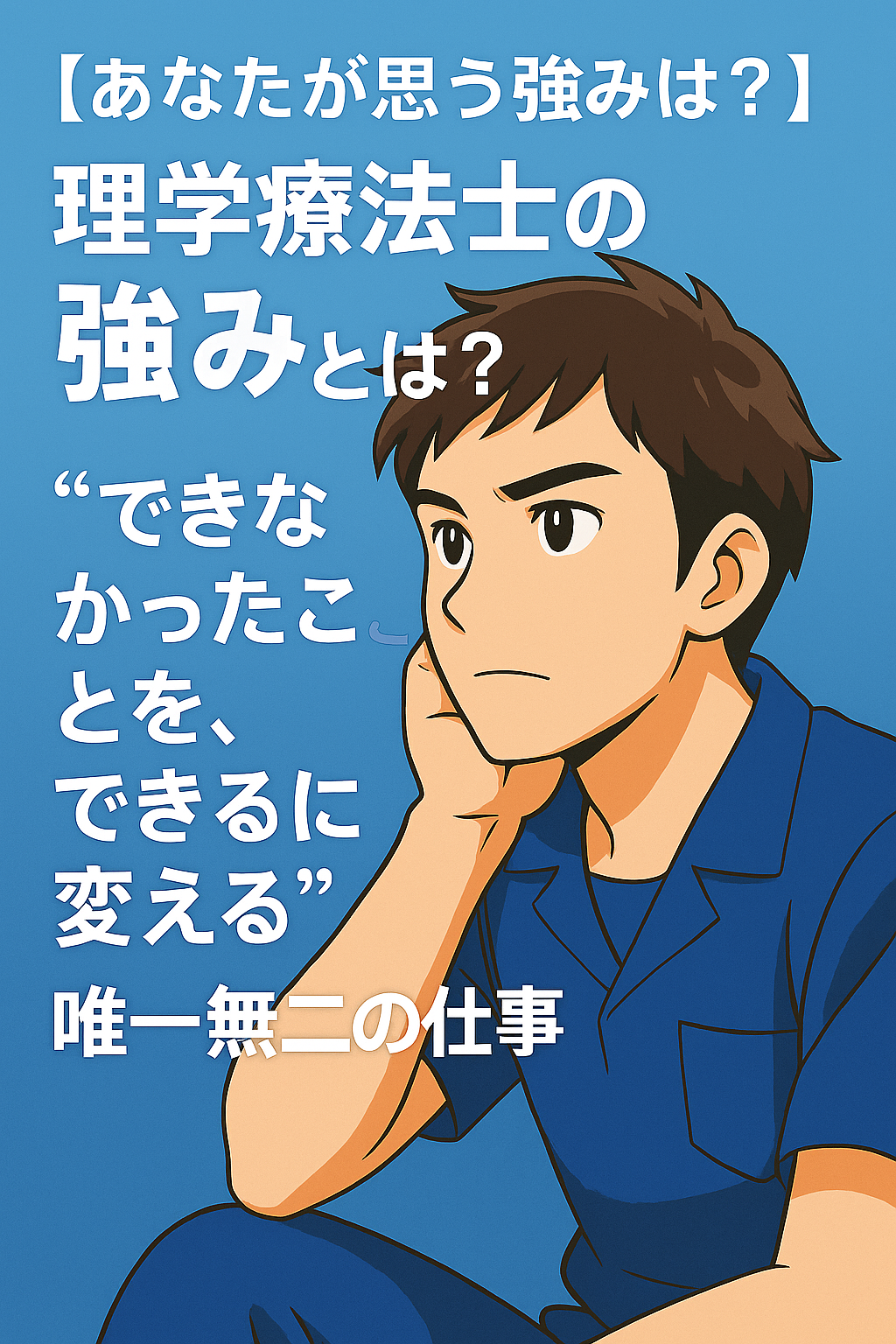理学療法士のみなさん
日々の臨床、お疲れ様です。数あるバランス評価の中で、皆さんが最もよく使うものは何でしょうか?
TUG、BBS、片脚立位時間…様々な評価がありますが、今回はその中でも特に手軽で奥が深い「ファンクショナルリーチテスト(Functional Reach Test: FRT)」に焦点を当てて、徹底的に解説していきます。
この記事を読めば、FRTの基礎知識から具体的な測定手順、臨床での応用方法、そして評価結果の解釈まで、解説します。若手セラピストはもちろん、指導する立場の先生方も知識の再確認にぜひご活用ください!
はじめに
なぜFRTをテーマにしたのか
ファンクショナルリーチテスト(FRT)は、メジャー1本と壁さえあれば、わずか1〜2分で実施できる非常にシンプルなバランス評価です。この手軽さから、急性期から在宅まで、あらゆる臨床現場で広く活用されています。
バランス評価の重要性
言うまでもなく、バランス能力はADL(日常生活活動)の遂行やQOL(生活の質)の維持に不可欠です。特に高齢者や脳卒中患者さんにとって、バランス能力の低下は**「転倒」**という大きなリスクに直結します。私たちセラピストは、この転倒リスクを正確に評価し、適切なアプローチを提供することで、患者さんの安全な生活を守る重要な役割を担っています。
現場での活用頻度と意義
FRTは、その簡便さゆえにスクリーニングテストとして非常に優れています。介入前後の効果測定にも使いやすく、患者さん自身も「前回より腕が伸びるようになった!」と変化を実感しやすいため、モチベーション向上にも繋がります。この記事では、そんなFRTのポテンシャルを最大限に引き出すための知識と視点をお伝えします。
ファンクショナルリーチテストとは?
FRTの概要
ファンクショナルリーチテスト(FRT)は、立位姿勢から、足を動かさずに前方へどれだけ手を伸ばせるかを測定することで、動的バランス能力を評価するテストです。非常にシンプルながら、信頼性と妥当性が多くの研究で証明されています。
開発の背景(Duncanらによる提唱)
FRTは、1990年にDuncanらによって、高齢者の転倒リスクを予測するための簡便な臨床ツールとして開発されました。重心を安定性の限界まで移動させる能力を測ることで、姿勢制御の安定性を評価することを目的としています。
主に何を評価する検査か(動的バランス)
FRTが評価するのは**「動的バランス(Dynamic Balance)」です。具体的には、支持基底面内で重心を前方へ移動させ、それを制御する能力、つまり「予測的姿勢制御(Anticipatory Postural Adjustments: APAs)」**を主に評価しています。リーチ動作の前に、体幹や下肢の筋が先行して活動することで、身体が前方へ倒れないように制御するメカニズムを反映しています。
実施方法と測定手順
正確な測定は、信頼性の高い評価の第一歩です。手順をしっかり確認しましょう。
用意するもの
- 壁
- 水平に固定されたメジャー(または専用の測定板)
- 目印をつけるためのテープやペン
姿勢・手の位置の基準
- 患者さんは壁際に、壁と平行になるように楽な足幅で立ちます。
- 壁側の腕を肩関節90度屈曲位、肘関節は伸展、手指は軽く握り拳を作ります。
- このとき、メジャーが肩の高さに来るように調整します。
測定時のポイント
- リーチ前の位置(開始位置):肩90度屈曲位での第3中手骨頭の位置をメジャー上で確認し、記録します(0cm地点)。
- 指示:「足は動かさずに、できるだけ遠くに手を伸ばしてください」と伝えます。
- リーチ最大位置:患者さんがバランスを崩さずに到達できた、最も遠い第3中手骨頭の位置を読み取ります。
- 測定値:「リーチ最大位置」から「開始位置」を引いた距離(cm)がFRTの記録となります。通常、3回測定し、平均値または最大値を採用します。
片手or両手リーチの違い
標準的な方法は**片手(非麻痺側または利き手)**でのリーチですが、臨床場面では両手でのリーチを試すこともあります。両手リーチは体幹の回旋を抑制し、純粋な前方へのリーチ能力を見たい場合に有効です。
⚠️安全管理の注意点
- 必ずセラピストは患者さんの斜め前方もしくは側方に立ち、いつでも支えられるように準備します。
- 転倒リスクが高い患者さんには、介助バーの近くや壁際で実施し、必要に応じて歩行ベルト(ゲイトベルト)を使用しましょう。
- 「無理しないでくださいね」と声かけをし、恐怖心を与えない配慮も重要です。
判定基準とカットオフ値
測定した数値が何を意味するのかを知ることが、臨床推論の鍵となります。
高齢者や脳卒中患者における基準値
FRTのカットオフ値は、対象者や研究によって多少異なりますが、一般的に広く使われている基準は以下の通りです。
| 測定値 | 転倒リスクの解釈 |
| 25.4cm (10インチ) 以上 | 転倒リスクは低い |
| 15cm~25.4cm | 転倒リスクは中等度(2倍) |
| 15cm (6インチ) 未満 | 転倒リスクは高い(4倍) |
特に**「15cm未満」**は、前方の安定性限界が著しく低下していることを示し、日常生活での転倒に繋がりやすい状態として注意が必要です。
研究で示されている基準値の紹介
- 地域在住高齢者:Duncanらの原著では、転倒歴のある高齢者は転倒歴のない高齢者に比べて有意にFRTの値が低いことが示されています。
- 脳卒中患者:麻痺側への荷重制限や体幹機能の低下により、健常高齢者よりも低い値を示す傾向があります。カットオフ値は研究により様々ですが、15cmが一つの目安とされています。
- パーキンソン病患者:姿勢変化や固縮の影響でリーチ距離が短縮しやすく、転倒リスクの指標として有用です。
臨床での活用方法と注意点
数値を測るだけでなく、その背景にある問題を考察することがセラピストの腕の見せ所です。
どのような対象に使うと効果的か
- 高齢者全般:転倒リスクのスクリーニングに。
- 脳卒中片麻痺患者:麻痺側・非麻痺側への重心移動能力、体幹制御能力の評価に。
- パーキンソン病患者:姿勢固縮や前方突進傾向の評価に。
- 整形外科疾患(下肢骨折術後など):荷重制限がある中でのバランス能力評価に。
体幹機能や姿勢制御能力との関連性
FRTの距離が短い場合、以下のような問題を推測できます。
- 足関節戦略の低下:足関節の背屈可動域制限や下腿三頭筋の機能不全。
- 股関節戦略の未熟:体幹を前傾させる際の股関節の屈曲が不十分。
- 体幹機能の低下:リーチに伴う腹筋群や背筋群の活動が不十分で、姿勢を保持できない。
- 恐怖心:転倒への恐怖から、無意識に重心移動を制限している。
⚠️結果の解釈で気をつけたい点(例:代償動作の見逃し)
距離だけを見ていると、重要な情報を見逃します。以下の代償動作がないか、必ず観察しましょう。
- リーチと同時に踵が浮く:足関節戦略が使えず、つま先で支えようとしている。
- 体幹の過度な屈曲や回旋:股関節戦略ではなく、体幹を曲げることで距離を稼ごうとしている。
- リーチと反対側への骨盤の後退:バランスを保つための代償戦略。
- 足を踏み出してしまう(ステッピング):安定性の限界を超えているサイン。
他の評価(TUGやBBSなど)との併用
FRTは前方向への動的バランスに特化しています。そのため、以下のような他の評価と組み合わせることで、患者さんのバランス能力を多角的に捉えることができます。
- TUG(Timed Up and Go Test):立ち上がりや方向転換を含む、より複合的な移動能力を評価。
- BBS(Berg Balance Scale):静的・動的バランスを14項目で幅広く評価。
- 片脚立位時間:静的な側方バランスを評価。
ケース紹介|このように使った!
実際にFRTを使った評価→アプローチ→再評価の例
- 対象:78歳女性、右大腿骨頸部骨折(術後)、屋内歩行自立レベル。退院に向けて調理動作など、より活動的なADLの獲得を目指している。
- 初回評価(Before)
- FRT:12cm。15cmを下回り、転倒リスクが高い状態。
- 動作観察:リーチ時に左(非荷重側)の踵が浮き、体幹を丸めて代償。右股関節への荷重を怖がっている様子が見られた。
- アプローチ
- 右下肢への段階的な荷重練習:セラピストの介助下で、徐々に荷重感覚を入力。
- 体幹と股関節を使ったリーチ練習:キッチンの棚に手を伸ばすなど、実践的な課題を設定。「おへそから前に出るように」と声かけをし、股関節戦略を促通。
- 足関節戦略の練習:壁に向かって立ち、ゆっくりと前後に身体を揺らす練習。
- 再評価(After / 2週間後)
- FRT:19cm。カットオフ値を上回り、改善が見られた。
- 動作観察:踵が浮かなくなり、体幹を過度に丸めることなくスムーズなリーチが可能に。本人からも「台所仕事で不安が減った」との声が聞かれた。
若手セラピストへのアドバイス
FRTは「距離」という分かりやすい結果が出ますが、**「なぜその距離しか伸びないのか?」**を考えることが最も重要です。代償動作や表情、声かけへの反応など、質的な情報を拾い上げる観察力を磨きましょう。
よくある質問Q&A
Q:FRTはどんな患者でも使えるの?
**A:**いいえ、限界はあります。立位保持が困難な方、重度の認知機能障害で指示理解が難しい方、リーチする側の肩に痛みや可動域制限がある方には適していません。安全に立位がとれることが前提となります。
Q:麻痺側のリーチはどう評価する?
**A:**標準法は非麻痺側ですが、麻痺側でのリーチを測定することも非常に有益です。麻痺側のリーチ能力は、更衣動作や日常生活での実用性を反映します。非麻痺側と比較することで、左右差や麻痺側の機能的な課題を明確にすることができます。ただし、転倒リスクは高まるため、安全管理はより一層徹底してください。
Q:BBSやMini-BESTestとの使い分けは?
**A:**以下のように考えると分かりやすいです。
- FRT:「動的バランスのスクリーニング」。短時間で前方への安定性を評価したいときに最適。
- BBS:「多角的なバランス能力の評価」。静的・動的バランスを幅広く網羅的に見たい場合に。ただし、歩行や反応的姿勢制御は含まれません。
- Mini-BESTest:「バランスシステムの詳細な評価」。予測的・反応的姿勢制御、感覚統合など、バランス障害の原因を深く探りたい場合に最も有用です。
まずはFRTでスクリーニングし、そこで見つかった課題をBBSやMini-BESTestで深掘りしていく、という流れが臨床的です。
まとめ
FRTの強みと限界
- 強み:短時間・省スペースで実施でき、動的バランスと転倒リスクを定量的に評価できる。
- 限界:評価するのは前方へのリーチのみ。側方や後方、反応的なバランス能力は評価できない。
シンプルな評価こそ“観察力”が大事
FRTはメジャーで距離を測るだけのシンプルなテストです。しかし、その短い時間の中に、患者さんの身体機能、運動戦略、心理状態など、膨大な情報が詰まっています。数値を記録するだけの「測定者」で終わるのではなく、その背景を読み解く**「評価者」**であることが、私たちセラピストには求められます。
今日から使える視点の再確認
- 数値だけでなく、動きの質(代償動作)を見る。
- なぜその動きになるのか、背景にある機能障害(可動域、筋力、協調性、恐怖心など)を考察する。
- 他の評価と組み合わせ、多角的な視点を持つ。
この視点を持つだけで、あなたのFRT評価は格段に深みを増すはずです。明日からの臨床に、ぜひ役立ててください!