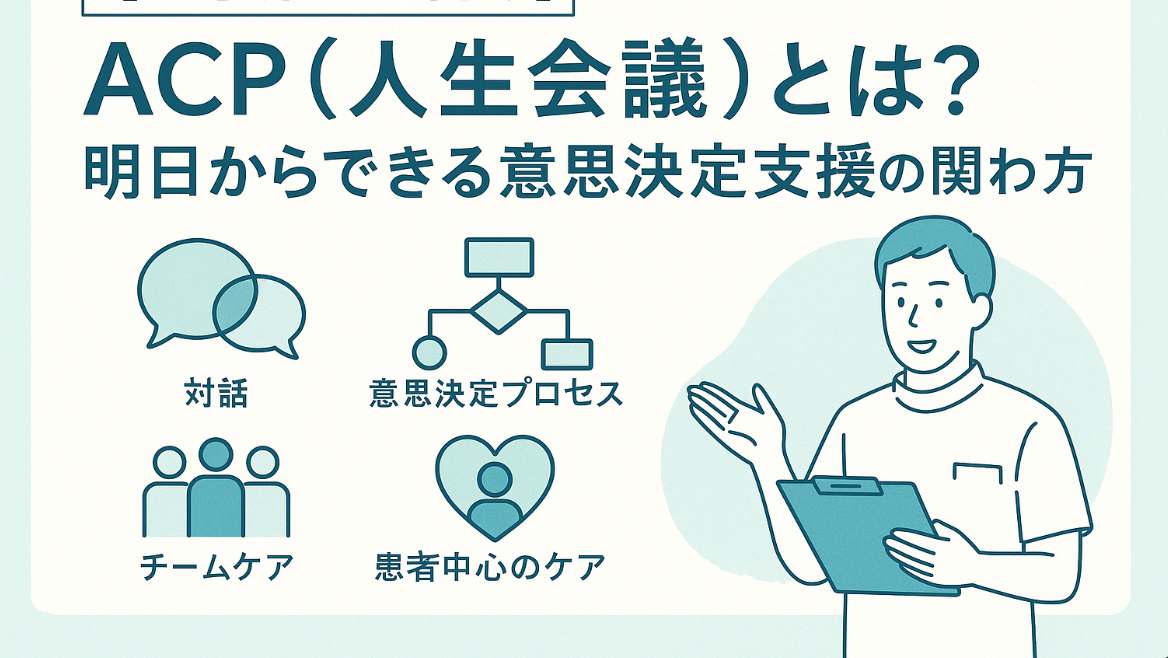「先生、もし歩けなくなったら、私はどうなりますか?」
「先生、リハビリを頑張れば、また歩いて家に帰れますか?」
「もし、このまま歩けなくなったら、私はどうなってしまうんでしょう…?」
リハビリ室で患者さんからふと投げかけられる、こうした言葉。
機能回復訓練に励む私たち理学療法士は、この切実な問いに、どう向き合えばよいのでしょうか。
日々の業務の中で、私たちはADL(日常生活動作)の向上を目指しています。しかし、その先にある患者さん自身の「人生」や「どう生きたいか」という想いに、どれだけ寄り添えているでしょうか。
この記事では、近年重要性が増しているACP(アドバナー・ケア・プランニング)、通称**「人生会議」**について、私たち理学療法士がどのように関わることができるのか、その役割と明日から実践できる具体的なステップを解説します。
臨床理学Labについて
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事

ACP(人生会議)とは?理学療法士が知るべき基本
まず、ACPとは何かを簡単におさらいしましょう。
**ACP(アドバンス・ケア・プランニング)**とは、将来の意思決定能力の低下に備えて、患者さん本人が家族や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、今後の医療やケアに関する価値観や希望を共有するプロセスのことです。
【ACPのポイント】
- 「延命治療」だけを決めるものではない: 「もしもの時」だけでなく、「これからどう生きたいか」「何を大切にしたいか」を話し合うことが本質です。
- 「プロセス」が重要: 一度決めたら終わりではなく、病状や心境の変化に合わせて、いつでも見直し、話し合いを重ねていくことが大切です。
- 本人の意思が中心: 主役はあくまで患者さん本人。私たちはその意思決定を支えるサポーターです。
ACPは、患者さんが最期までその人らしく生きるための、そして残された家族が後悔しないための、非常に重要な取り組みなのです。
なぜ理学療法士にACPへの関与が求められるのか?3つの強み
「ACPって、医師や看護師、相談員さんの役割じゃないの?」
そう思う方もいるかもしれません。しかし、私たち理学療法士には、ACPにおいて発揮できる独自の強みがあります。
生活に直結した視点を提示できる
私たちは、身体機能が「実際の生活」にどう影響するかを具体的にイメージできる専門家です。
- 「この筋力なら、自宅の5段の階段が昇れるだろうか」
- 「このバランス能力では、和式トイレでの立ち座りは難しいかもしれない」
- 「ここまで回復すれば、趣味の畑仕事が少しはできるかもしれない」
「家に帰りたい」という希望に対し、何ができて、何が難しく、どういう工夫や介助があれば実現できるのか。この具体的な生活像を提示できるのが、理学療法士の最大の強みです。
信頼関係を活かした本音の引き出し
理学療法士は、患者さんと1対1でリハビリを行う時間が長く、継続的に関わります。この密な時間の中で、自然と信頼関係が築かれます。
「先生だから言うけどね…」
そんな風に、リハビリ中の何気ない会話から、**医師や他のスタッフには言えない本音や、大切にしている価値観(人生観)**がポロリとこぼれることがあります。この関係性こそが、ACPの入り口になるのです。
希望と現実のギャップを“翻訳”できる
患者さんは「また歩きたい」という希望を持ち、私たちは機能予後という「現実」を把握しています。この二つの間には、時に大きなギャップがあります。
私たちの役割は、ただ厳しい現実を突きつけることではありません。

以前のようにスタスタ歩くのは難しいかもしれません。でも、杖を使えば、お庭の花を見に行くことができるぐらいは歩けるようになるかもしれません。
このように、希望を完全に断つのではなく、現実的な目標へと具体的に「翻訳」し、代替案を一緒に考えることができます。これは、患者さんの意思決定を支える上で非常に重要な役割です。
理学療法士がACPで発揮できる3つの強み
- 生活に直結した視点を提示できる
筋力やバランス能力などの機能評価をもとに、「自宅の階段を昇れるか」「トイレで立ち座りができるか」など、具体的な生活像を示せる。- 信頼関係を活かした本音の引き出し
リハビリ中の継続的な1対1の関わりを通して、患者さんから他職種には言えない本音や価値観を聞き出せる。- 希望と現実のギャップを“翻訳”できる
「また歩きたい」という希望に対し、現実的な機能予後を踏まえつつ、代替案や実現可能な目標へとつなげられる。
明日から実践!理学療法士のためのACP関わり方3ステップ
では、具体的にどう動けばいいのでしょうか。特別なことをする必要はありません。いつものリハビリに、少しだけ意識をプラスしてみましょう。
まずは、相手を知ることから。機能訓練をしながら、患者さんの「人となり」や「大切にしていること」に耳を傾けてみましょう。
【会話のきっかけになる質問例】
- 「退院したら、まず一番に何をしたいですか?」
- 「お休みの日は、いつも何をされているんですか?」
- 「昔、一番熱中したことって何ですか?」
- 「この中で、これだけは自分でやりたい、ということはありますか?」
ポイントは、すぐに答えを求めないこと。沈黙も大切なコミュニケーションです。患者さんの言葉の背景にある想いを想像しながら、じっくりと話を聴く姿勢が信頼関係を深めます。
患者さんの価値観が見えてきたら、次はその想いを実現するための方法を一緒に考えます。ここが理学療法士の腕の見せ所です。
- 予後の伝え方の工夫: 不確実なことは「断定」せず、「~という可能性があります」「もし~になれば、~できるかもしれません」と可能性の幅を持たせて伝えます。
- 複数の選択肢を提示: 「プランAが難しくても、プランBならこういう生活が送れますよ」と、最善のシナリオだけでなく、いくつかの選択肢を具体的に示すことで、患者さんは安心して自分の希望を考えられます。
- スモールステップの設定: 「まずはベッドから起き上がってみましょう」と、最終目標に向けた小さな成功体験を積んでもらうことで、希望を繋ぎます。
リハビリ室で聴き取った患者さんの貴重な想いを、自分の中だけで留めていては意味がありません。チームに共有し、繋ぐことが不可欠です。
- カルテへの記録: SOAPの「S(主観的情報)」に、「本人が『最期まで畳の上で寝たい』と発言あり」など、具体的な言葉をそのまま記載します。
- カンファレンスでの発言: 「理学療法士の視点から見ると、ご本人の『家に帰りたい』という希望は、この福祉用具とこの介助方法があれば実現の可能性があります」など、専門職としての根拠を添えて積極的に情報を発信しましょう。
あなたが繋いだその一言が、チーム全体のケアの方向性を決め、患者さんの「自分らしい生き方」を実現する大きな力になります。
【まとめ】理学療法士は、患者さんの「生き方」を支える専門家
ACPは、決して特別な業務ではありません。それは、私たちが毎日行っている患者さんとのコミュニケーションの延長線上にあります。
私たちは、関節の角度や筋力だけでなく、その方の人生の物語に寄り添うことができる素晴らしい仕事です。身体機能の回復を支援することはもちろん、患者さんが自らの意思で「どう生きたいか」を選び、その人らしい人生を最期まで歩んでいけるよう伴走すること。それもまた、理学療法士の大切な役割ではないでしょうか。
まずは、明日担当する患者さんに「退院したら楽しみなことは何ですか?」と聞いてみませんか。
その小さな一歩が、患者さんの未来を支えるACPの始まりです。