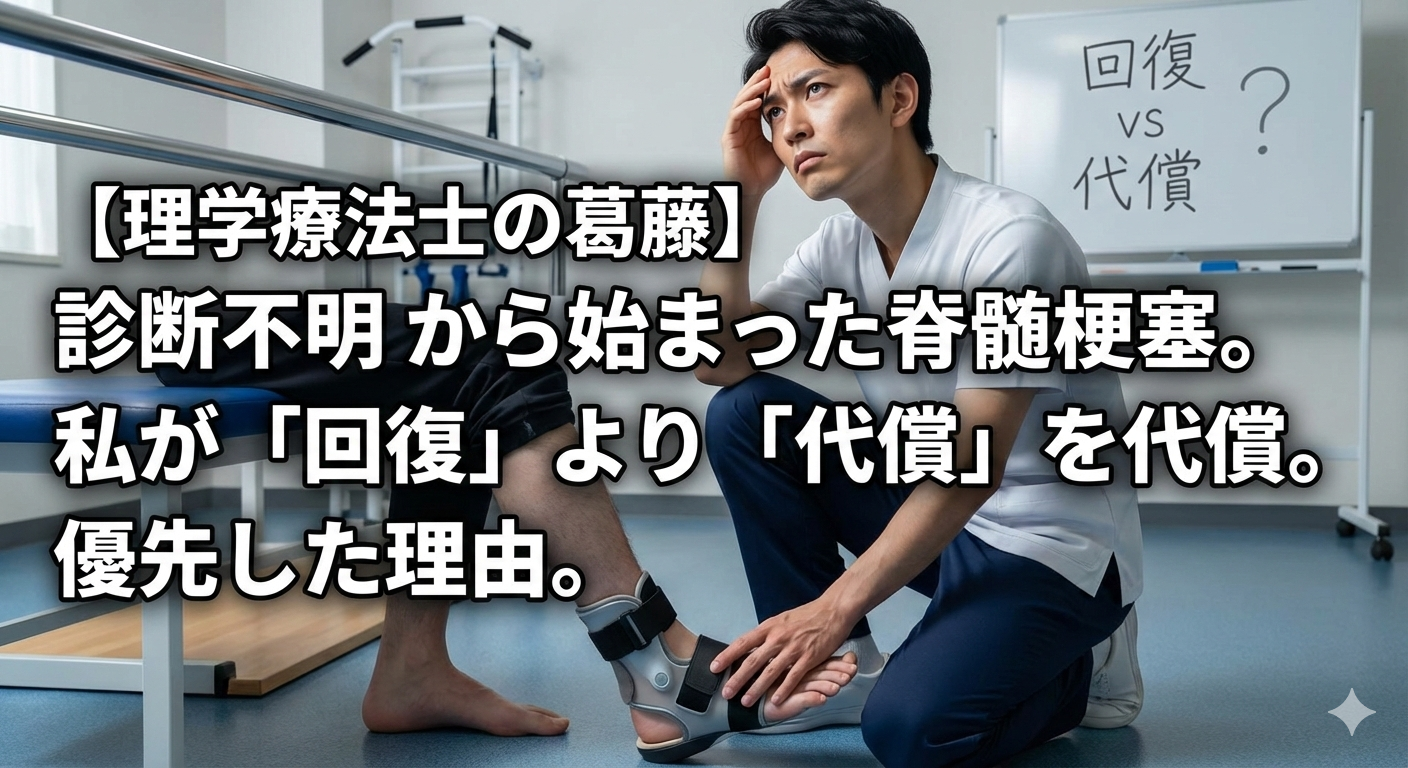はじめに
「教科書にはこう書いてあるけれど、目の前の患者さんには当てはまらない……」
そんな経験はありませんか?
理学療法士として臨床に出ていると、“病名 → 治療方針”というきれいな一本道ではない場面に何度も遭遇します。
今回の【ひとり症例検討会】では、私が経験した「結果的には脊髄梗塞だった症例」について、診断がはっきりしない中でどのように悩み、迷い、そして「代償を許容する」という決断に至ったのか。そのリアルな思考過程をさらけ出してみました。
「地図を持たない」状態でのスタート
その方は、60代の女性でした。
主訴は「左足が上がらず、歩きにくい」。
当初は腓骨神経障害が疑われていましたが、画像診断でも決め手に欠ける状況。それでも目の前には、著明な下垂足と「転びそうで怖い」という切実な不安がありました。
- 背屈MMT 1
- 歩行時の著しい直線偏倚(20mで88cmのズレ)
- 視線は常に足元、拭いきれない恐怖心
「まだ発症早期だから、機能回復を待つべきか?」
「いや、今のままでは転倒のリスクが高すぎる……」
私の頭の中では、常に2つの選択肢がぶつかり合っていました。
「代償」は妥協か、それとも戦略か
今回、私が最終的に選んだのは「早期の装具導入」と「代償を許容した安全性の確保」でした。
理学療法士として、「きれいな歩行(正常歩行)」を目指したい気持ちはもちろんありました。しかし、オルトップ(短下肢装具)を試着した瞬間、その方の歩行が劇的に安定したのです。
「この人に今必要なのは、きれいな歩き方より、安心して歩ける身体からもしれない。」
そう確信した瞬間でした。
神経生理学的な視点からも、不安定な状態での歩行は「誤学習」を招き、恐怖心は「運動抑制」を強めます。代償を“妥協”として捉えるのではなく、「次のステップに進むための適応的戦略」として位置づけることにしました。
脊髄梗塞と確定して見えたもの
介入から約3週間後、最終的に下された診断は「脊髄梗塞」でした。
機能回復には時間がかかるという現実を突きつけられましたが、その時すでに患者さんは装具を使いこなし、病棟内を自立して歩けるようになっていました。
もしあの時、「診断が出るまで」と介入を遅らせていたら。
もし、「正常歩行」に固執して装具を拒んでいたら。
今の彼女の笑顔はなかったかもしれません。
ひとり症例検討会で詳しく公開中
今回の記事のフルバージョンでは、さらに踏み込んだ「思考の裏側」をまとめています。
- 具体的な評価データ(10m歩行や偏倚の推移)
- 「安全を脅かす代償」と「安全を支える代償」の線引き基準
- 装具を“治療デバイス”としてどう活用したか
- 患者さんの自己効力感を高めたフィードバックのコツ
「目標設定に正解がなくて苦しい」「代償動作をどこまで許していいか迷う」
そんな悩みを持つセラピストの方にとって、一つのケーススタディとして参考にしていただける内容です。
▼記事の続きはこちらから▼
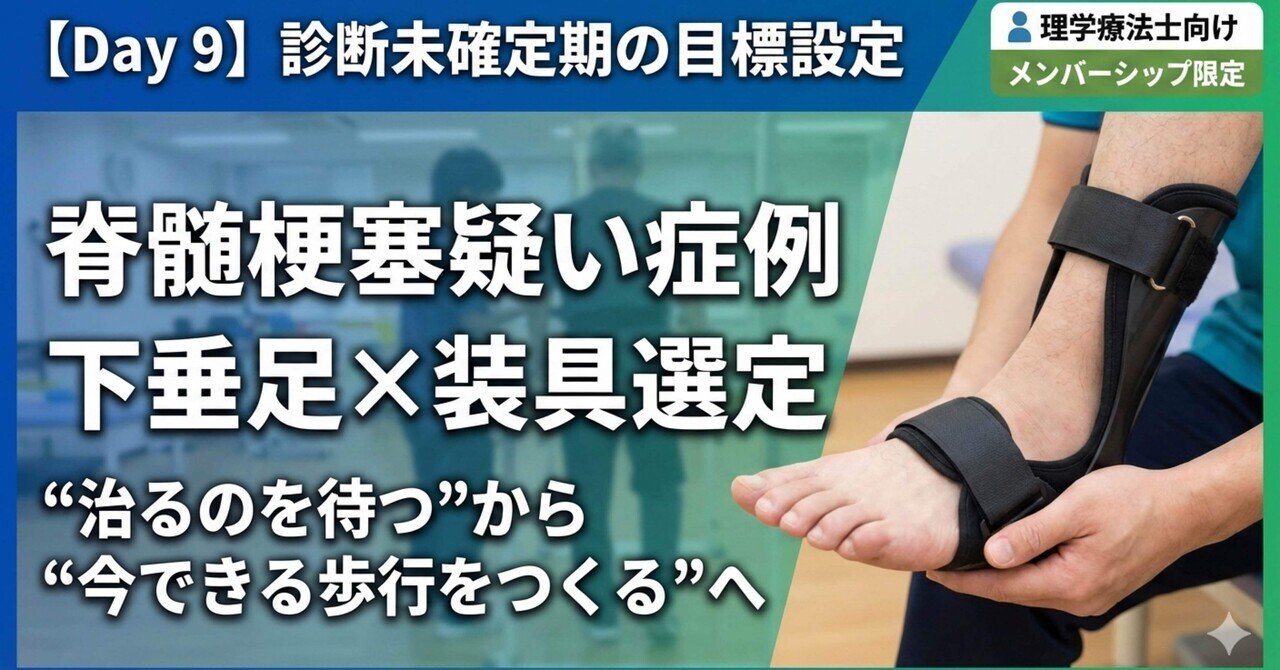

最後に
目標設定は、病名から決めるものではなく、「患者さんの生活の危険度と恐怖の大きさ」も大切な情報の一つ。今回の症例を通じて、私自身が一番学ばされたことかもしれません。
私のこの「迷い」が、どこかで同じように悩むあなたの臨床の一助になれば幸いです。