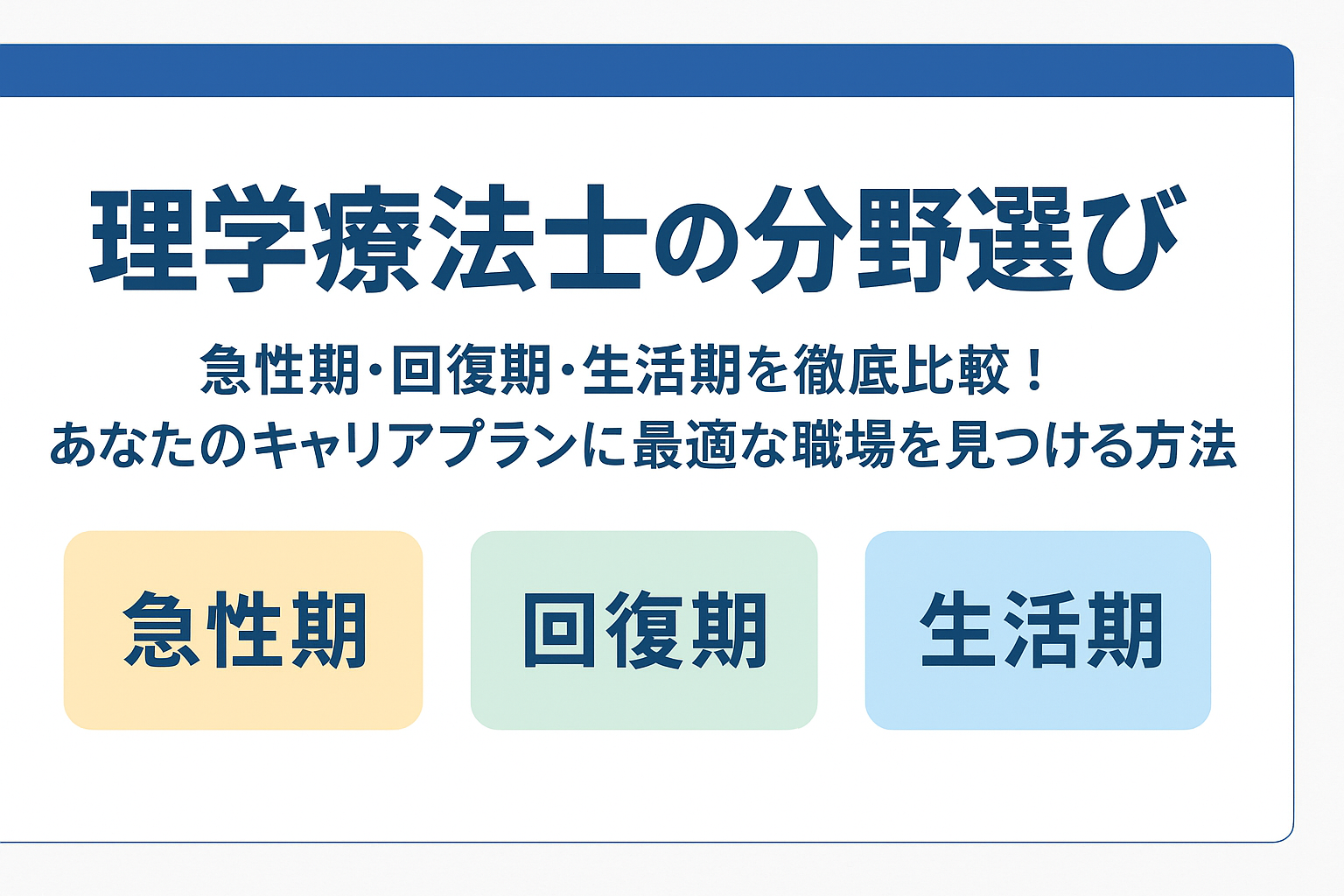理学療法士キャリアに悩むのあなたへ
「理学療法士として働き始めたけれど(来年から理学療法士として働く予定だけど)、どの分野が本当に自分に合っているのかわからない…」
「急性期、回復期、生活期…それぞれの違いはわかるけど、リアルな働き方や求められるスキルがイメージできない」
新人・若手の理学療法士なら、一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。
学生時代の実習だけでは掴みきれない各分野の特性や、日々の業務に追われて将来のキャリアプランをじっくり考える余裕がない、という方も多いかもしれません。
この記事では、理学療法士が活躍する主要な3つのステージ「急性期」「回復期」「生活期」について、以下の観点から徹底的に比較・解説します。
- 各分野の役割と目的
- 具体的な仕事内容と1日の流れ
- 働く上でのメリット・デメリット
- 求められるスキルと向いている人の特徴
この記事が漠然としていた各分野のイメージが明確になり、あなた自身の価値観や目標に合ったキャリアを考えるための「具体的なヒント」が見つかるきっかけになれば幸いです。
なお、これが全て、ではないのであくまで参考程度にしてみてください。^_^
お知らせ
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります!

【全体像を把握】病期で変わる理学療法士の役割と連携
まず、理学療法士が関わる3つのステージが、患者さんの状態変化の中でどのようにつながっているのかを理解しましょう。リハビリテーションは、それぞれの分野が独立しているのではなく、情報を引き継ぎながら連携していく「連続性」が非常に重要です。
- 急性期(Acute Phase)
- 患者さんの状態: 発症・受傷直後で、生命の危機にあり全身状態が不安定な時期。
- PTの主な役割: 全身状態のリスク管理を最優先しながら、廃用症候群(寝たきりによる筋力低下や関節拘縮など)の予防と、早期離床・早期回復を促すこと。
- 回復期(Recovery Phase)
- 患者さんの状態: 急性期を脱し、全身状態が安定。機能回復が最も期待できる時期。
- PTの主な役割: 集中的なリハビリテーションにより、失われた身体機能やADL(日常生活活動)能力を最大限に再獲得し、在宅復帰や社会復帰を目指すこと。
- 生活期(Maintenance Phase)
- 患者さんの状態: 退院後、自宅や施設など地域で生活を送る時期。
- PTの主な役割: 回復した機能の維持・向上、生活環境への適応、再発予防、QOL(生活の質)の向上を支援し、その人らしい生活が継続できるようサポートすること。
【分野別徹底比較】仕事内容・メリット・適性を知ろう
ここからは、各分野のリアルな働き方について、さらに詳しく掘り下げていきます。
【役割・目的】
リスク管理を徹底し、患者の生命維持をサポートしながら、二次的合併症を予防し、早期離床を実現すること。
- 対象疾患: 脳卒中、心筋梗塞、呼吸器疾患、外科手術後、多発外傷など多岐にわたる。
- 1日の流れ(例)
- 午前:情報収集(カルテ、画像、検査データ)、カンファレンス、ICU/CCUでの介入、術後患者の離床
- 午後:病棟でのリハビリ、他職種との情報共有、カルテ記録
- メリット・やりがい
- 最先端の医療知識や全身管理、リスク管理能力が身につく。
- 医師や看護師など他職種との密な連携が求められ、チーム医療の最前線を経験できる。
- 患者が危機的状況を脱していく過程に直接関われる。
- デメリット・大変なこと
- 常に緊張感が伴い、急な状態変化への対応力が求められる。
- 在院日数が短く、一人の患者とじっくり関わる時間は限られる。
- 医学的知識の継続的な学習が不可欠。
- こんな人におすすめ!
- 知的好奇心が旺盛で、医学的な知識を深めたい人
- 論理的思考力と冷静な判断力に自信がある人
- スピード感のある環境やチームでの連携にやりがいを感じる人
【役割・目的】
在宅復帰という明確なゴールに向け、患者の機能回復とADL能力向上を最大限に引き出すこと。
- 対象疾患: 脳血管疾患、大腿骨頸部骨折などの運動器疾患が中心。
- 1日の流れ(例)
- 午前:担当患者への個別リハビリ(1日2〜3単位)、ADL訓練
- 午後:個別リハビリ、多職種カンファレンス、家族指導、家屋調査、書類作成
- メリット・やりがい
- 患者の機能が劇的に改善していく過程を、時間をかけて見届けられる。
- 一人の患者と深く関わり、信頼関係を築きやすい。
- セラピストが主体となってリハビリ計画を立案・実行できる裁量が大きい。
- デメリット・大変なこと
- 対象疾患がある程度限定される傾向がある。
- 365日リハビリ提供体制の職場が多く、土日祝の出勤がある。
- 退院支援に向けた家族や他職種との調整業務が多い。
- こんな人におすすめ!
- 一人の患者とじっくり向き合い、目標達成の喜びを分かち合いたい人
- 目に見える成果や機能改善にやりがいを感じる人
- ゴールから逆算して計画を立て、実行するのが得意な人
生活期は働き方が多様です。ここでは代表的な「クリニック」「訪問リハビリ」を紹介します。
① クリニック(整形外科など)
- 役割・目的: 痛みや機能障害の原因を評価し、運動療法や徒手療法を用いて改善を図り、社会生活やスポーツへの復帰を支援すること。
- メリット
- 特定の分野(運動器、スポーツなど)の専門性を高められる。
- 外来中心のため、ワークライフバランスを取りやすい職場が多い。
- デメリット
- 医師の指示のもとで動く場面が多く、セラピストの裁量が限られる場合がある。
- 対象が運動器疾患に偏るため、幅広い疾患を経験したい人には不向き。
- こんな人におすすめ!
- 運動器疾患や徒手療法、スポーツリハビリを極めたい人
- 様々な年齢層の患者とコミュニケーションを取るのが好きな人
② 訪問リハビリ
- 役割・目的: 利用者の自宅に訪問し、実際の生活環境の中でADLの維持・向上や介助方法の指導、QOL向上を支援すること。
- メリット
- 利用者の「生活そのもの」に深く関わることができる。
- 一人で判断し、計画を立てて実行する場面が多く、自律性と応用力が身につく。
- デメリット
- 基本的に一人で対応するため、急なトラブルにも自分で対処する必要がある。
- 移動時間が長く、天候に左右される。
- こんな人におすすめ!
- マニュアル通りでなく、個々の状況に合わせて工夫するのが好きな人
- 自分で考えて行動し、責任を持って仕事を進めたい人
- 病院内では見えない、患者のリアルな生活を支えたい人
【自己分析】あなたの価値観に合う分野を見つける5つの質問
さて、ここまで各分野の特徴を見てきました。最後に、あなた自身の価値観と照らし合わせてみましょう。以下の質問に「A/B/C」で答えてみてください。
Q1. あなたが最もやりがいを感じるリハビリのゴールは?
A. 患者の生命が安定し、次のステージへつなげられた時
B. 歩けなかった患者が、目標だった自宅へ歩いて帰れた時
C. 利用者が住み慣れた家で、趣味や役割を続けられている時
Q2. 理想のチームでの働き方は?
A. 医師や看護師など多職種と常に連携し、チームで方針を決めていく
B. セラピスト同士で相談しながら、リハビリ計画を主体的に進めていく
C. ケアマネジャーなど地域の専門職と連携し、一人の専門家として関わる
Q3. 伸ばしていきたいスキルは?
A. 重篤な疾患に対するリスク管理能力と、全身状態を把握する力
B. 運動学・解剖学に基づいた詳細な機能評価と、集中的なアプローチ技術
C. 生活環境を評価し、福祉用具や住宅改修なども含めて提案する応用力
Q4. 仕事において重視することは?
A. 最新の医療知識に触れられる、刺激的でスピード感のある環境
B. 一つの目標に向かって、計画的にコツコツと成果を積み重ねること
C. 自分の裁量でスケジュールを調整し、柔軟に働けること
Q5. 患者・利用者との理想的な関わり方は?
A. 短期間で密に状態を把握し、安全を確保しながら関わる
B. 数ヶ月単位で深く関わり、二人三脚でゴールを目指す
C. 長期的な視点で寄り添い、生活の変化に合わせてサポートする
【簡易診断】
- 「A」が多かったあなた → 急性期の適性があるかもしれません。
- 「B」が多かったあなた → 回復期で大きなやりがいを感じられそうです。
- 「C」が多かったあなた → 生活期(訪問や施設など)が向いている可能性があります。
※これはあくまで目安です。自分の興味や価値観を整理するきっかけにしてください。
【まとめ】どの経験も、あなたの未来につながる
急性期、回復期、生活期、それぞれの分野に異なる役割と魅力があります。
大切なのは、「どこで働くか」と同時に「その場所で何を学びたいか」という視点を持つことです。どの分野での経験も、あなたの理学療法士としての知識、技術、そして人間性を豊かにしてくれます。
もし今、自分のキャリアに迷っているなら、まずは興味を持った分野の先輩に話を聞いたり、見学に行ってみることから始めてみてはいかがでしょうか。
この記事が、あなたのキャリアプランを描く上での確かな一歩となることを願っています。