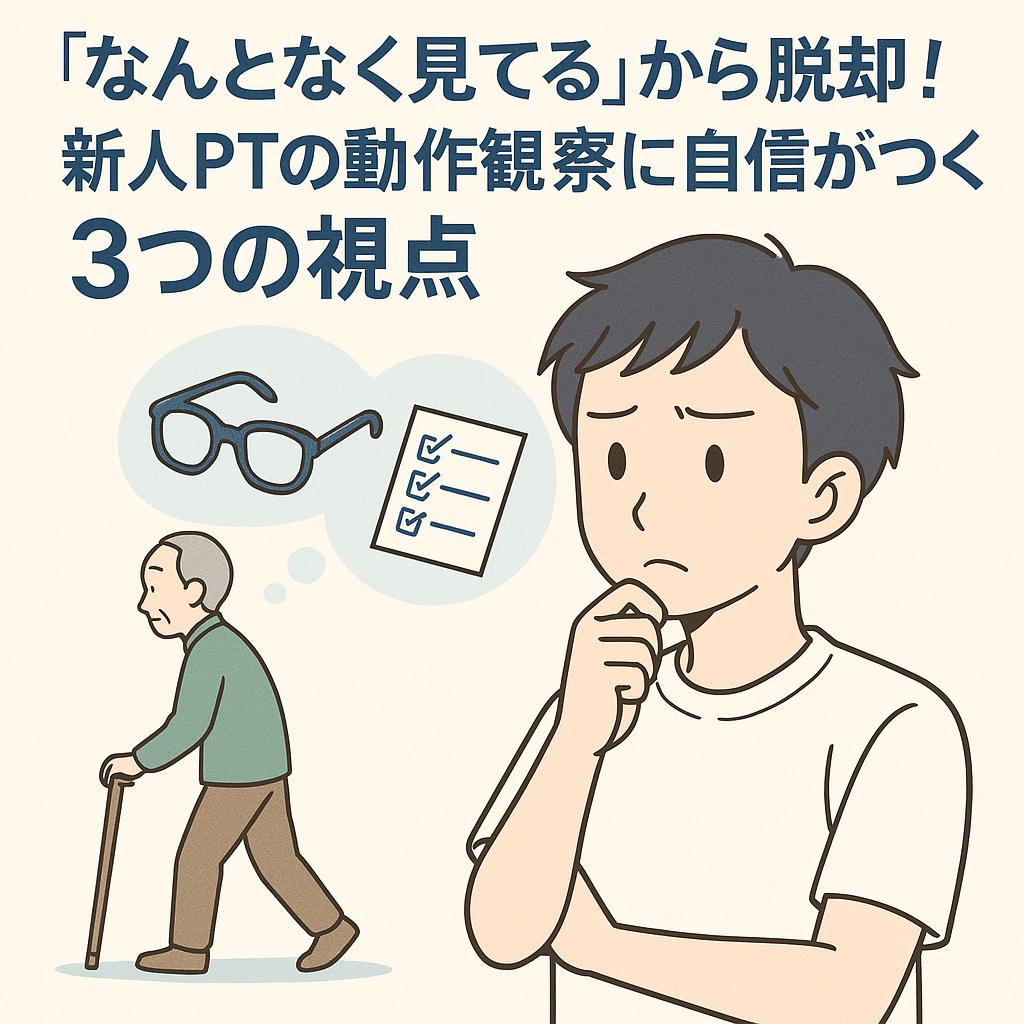はじめに|“なんとなく見てる”体幹評価から脱却しよう
「先生、この患者さんの座位バランスはどうですか?」
先輩や医師からこう聞かれて、返答に困った経験はありませんか?
「うーん、まあまあ座れています」「少しふらつきますね…」といった、曖昧な返答しかできず、もどかしい思いをしたことがあるセラピストは少なくないはずです。
体幹機能は、寝返りや起き上がり、歩行といった全身の動きの土台となる、非常に重要な要素です。しかし、その機能を客観的に捉え、的確に言葉で説明するのは意外と難しいものです。
そんな「なんとなく」の評価から脱却し、“体幹の質”をしっかりと見抜くために役立つのが、今回ご紹介する「FACT(ファクト)」、正式名称 Functional Assessment for Control of Trunk です。
この記事を読めば、FACTの基本概念から具体的な評価方法、そして評価結果をどのようにリハビリテーションに活かすかまで、網羅的に理解できます。明日からの臨床がもっと面白くなる、新しい視点を手に入れましょう!
\FACTを活用したケーススタディ記事を確認/

FACTとは?|評価の基本情報と開発の背景
まずは、FACTがどのような評価バッテリーなのか、基本的な情報から押さえていきましょう。
- 正式名称:Functional Assessment for Control of Trunk(臨床的体幹機能検査)
- 主な対象:脳卒中をはじめとする中枢神経疾患の患者さんや、その他体幹機能低下が疑われる症例
- 開発目的:体幹のコントロール能力を、「静的」「動的」「反応性」の3つの側面から客観的に評価すること。
- 開発者・初出論文:日本の藤原俊之先生らによって開発され、2003年に学術誌『American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation』で発表されました。(Fujiwara T, et al. Am J Phys Med Rehabil. 2003)
FACTは、単に「座れるかどうか」だけでなく、「どのように体幹を使っているか」という質的な部分にまで踏み込んで評価できるのが大きな特徴です。その信頼性と妥当性から、多くの臨床現場や研究で用いられています。
【表で完全解説】FACTの全10評価項目・採点基準
ここからは、FACTの具体的な評価項目と方法を解説します。多くの教科書や論文で「表」として紹介されていることが多い、FACTの全10項目を一つずつ見ていきましょう。
【準備するもの】
- ストップウォッチ
- プラットホームまたはベッド(患者が端座位になり、足底が床につく高さ)
- (必要に応じて)介助者
【基本姿勢】
両足を床につけた端座位。両手は体側に置くか、膝の上に軽く置きます。
カテゴリー1:静的座位保持 (Static Sitting Balance)
重力下で姿勢を安定させる基本的な能力を評価します。ADLでは、座位での食事や整容動作の土台となります。
| 項目 | 実施方法 | 採点基準 |
| 1. 静的座位保持 | 両足を床につけた端座位で、30秒間姿勢を保持するよう指示する。 | 2点: 30秒間、安定して保持できる。 1点: 30秒未満しか保持できない、または手で支持が必要。 0点: 介助なしでは座位保持ができない。 |
| 2. 非麻痺側への重心移動 | 麻痺側の坐骨をベッドから持ち上げ、非麻痺側へ重心を移動させた状態で5秒間姿勢を保持するよう指示する。 | 2点: 5秒間、安定して保持できる。 1点: 5秒未満しか保持できない。< 0点: 坐骨を持ち上げられない、または持ち上げた途端にバランスを崩す。 |
| 3. 麻痺側への重心移動 | 非麻痺側の坐骨をベッドから持ち上げ、麻痺側へ重心を移動させた状態で5秒間姿勢を保持するよう指示する。 | 2点: 5秒間、安定して保持できる。 1点: 5秒未満しか保持できない。 0点: 坐骨を持ち上げられない、または持ち上げた途端にバランスを崩す。 |
《臨床ワンポイント》
項目2・3は、体幹側屈筋群の遠心性・求心性収縮の能力を反映します。例えば、麻痺側への重心移動(項目3)が困難な場合、麻痺側の体幹で体重を支える能力(求心性)と、非麻痺側の体幹を伸長させる能力(遠心性)の両方に課題がある可能性が考えられます。
カテゴリー2:動的体幹運動 (Dynamic Sitting Balance)
*体幹を意図的に、かつ選択的に動かす能力を評価します。リーチ動作や寝返りなど、より複雑な動きに不可欠な**分離運動(ディソシエーション)*の能力を見ています。
| 項目 | 実施方法 | 採点基準 |
| 4. 体幹の前方リーチ | 肩の高さで前方に置かれた目標物に、骨盤を後傾させずにリーチするよう指示する。 | 3点: 骨盤を後傾させずに、スムーズにリーチできる。 2点: 骨盤を後傾させて代償するが、リーチは可能。 1点: リーチが不十分。<br>0点: リーチできない。 |
| 5. 体幹の側方リーチ | 体の横(肩の高さ)に置かれた目標物に、反対側の坐骨を浮かせずにリーチするよう指示する。(左右実施) | 3点: 反対側の坐骨を浮かせずに、スムーズにリーチできる。 2点: 反対側の坐骨が浮いてしまう(代償)が、リーチは可能。 1点: リーチが不十分。 0点: リーチできない。 ※左右で点数が低い方を採用 |
| 6. 体幹の選択的屈曲 | 「おへそを覗き込むように、背中を丸めてください」と指示し、骨盤を後傾させずに胸椎・腰椎を屈曲させる。 | 2点: 骨盤を後傾させずに、選択的な屈曲ができる。 1点: 骨盤の後傾を伴う(代償)。 0点: できない。 |
| 7. 体幹の選択的回旋 | 「骨盤は正面を向けたまま、上半身だけを捻ってください」と指示し、体幹を回旋させる。(左右実施) | 2点: 骨盤を固定したまま、選択的な回旋ができる。 1点: 骨盤も一緒に回ってしまう(代償)。 0点: できない。 ※左右で点数が低い方を採用 |
《臨床ワンポイント》
体幹と骨盤がひと塊でしか動かせない(分離できていない)場合、歩行時の骨盤回旋や上肢の自由な操作がぎこちなくなり、エネルギー効率の悪い動きになります。代償動作の有無を観察することが、質の評価に繋がります。
カテゴリー3:反応的制御 (Trunk Control in Reaction to External Stimuli)
*予測不能な外力(外乱)に対して姿勢を立て直す、自動的なバランス反応を評価します。転倒予防に直結する重要な能力です。実施には最大限の安全配慮が必要です。 *
| 項目 | 実施方法 | 採点基準 |
| 8. 前方への外乱反応 | 患者に予告なく、背中(肩甲骨の間)を前方に軽く、素早く押す。いつでも支えられる準備をする。 | 2点: 最小限の動揺で、すぐに姿勢を立て直せる。 1点: 大きく動揺するが、立て直せる。 0点: バランスを崩し、介助が必要。 |
| 9. 後方への外乱反応 | 患者に予告なく、胸骨(乳頭の高さ)を後方に軽く、素早く押す。いつでも支えられる準備をする。 | 2点: 最小限の動揺で、すぐに姿勢を立て直せる。 1点: 大きく動揺するが、立て直せる。 0点: バランスを崩し、介助が必要。 |
| 10. 側方への外乱反応 | 患者に予告なく、肩を側方に軽く、素早く押す。(左右実施)いつでも支えられる準備をする。 | 2点: 最小限の動揺で、すぐに姿勢を立て直せる。 1点: 大きく動揺するが、立て直せる。 0点: バランスを崩し、介助が必要。 ※左右で点数が低い方を採用 |
《臨床ワンポイント》
この反応は、足関節戦略や股関節戦略といった姿勢制御戦略が、座位でどのように働いているかを示唆します。ここでの得点が低い患者さんは、人混みや不整地での活動にリスクを伴う可能性があり、具体的な転倒予防指導の根拠となります。
他の体幹評価との違いと使い分け
体幹の評価法には、FACT以外にも有名なものがあります。ここでは代表的な2つと比較し、FACTの強みを探ります。
| 評価法 | FACT<br>(Functional Assessment for Control of Trunk) | TIS<br>(Trunk Impairment Scale) | FIST<br>(Function in Sitting Test) |
| 特徴 | 静的・動的・反応性の3側面から評価。特に選択的な運動や反応性の質的評価に強い。 | 静的・動的・協調性を評価。寝返りや起き上がりなど、ベッド上動作に近い項目が多い。 | 座位での機能的活動(リーチ、 scooting等)に焦点。ADLに直結した能力を評価。 |
| こんな時に | 体幹の質的な問題(例:分離運動ができない)や転倒リスク(反応性の低下)を詳しく見たい時。 | 離床初期の患者さんで、基本的な体幹機能やベッド上ADLの能力を評価したい時。 | 座位でのADL能力(更衣、食事など)がなぜ向上しないのか、具体的な課題を探りたい時。 |
【FACTが特に優れている場面】
TISやFISTも素晴らしい評価法ですが、FACTは特に**「なぜ上手く動けないのか?」という運動学的・神経生理学的な原因を探る**のに長けています。例えば、「リーチ動作で体が流れてしまう」という現象に対し、FACTを使えば「体幹の選択的な側屈が苦手だからだ」といった、より詳細な仮説を立てやすくなります。
臨床での活用例|“評価がアプローチに変わる”瞬間
評価は、点数をつけて終わりではありません。その結果をどう解釈し、具体的なアプローチに繋げるかが最も重要です。
【活用例①】座位で麻痺側へ崩れてしまう片麻痺患者さん
- 評価(FACT):
- 項目3(麻痺側への重心移動)が0点。
- 項目5(側方リーチ)で麻痺側へのリーチが困難。
- 解釈:
- 麻痺側の体幹側屈筋群の活動不全と、非麻痺側の過緊張による固定が考えられる。
- 介入:
- セラピストが骨盤を安定させた状態で、非麻痺側への体幹側屈運動を促通し、麻痺側の遠心性収縮を学習。
- 麻痺側へのリーチ練習で、麻痺側体幹の求心性収縮を促す。
- 再評価:
- 介入後、FACTの該当項目が改善。座位での安定性が向上し、ズボン操作もスムーズになった。
【活用例②】ADL訓練が伸び悩んでいた高次脳機能障害を合併した患者さん
- 評価(FACT):
- 静的・動的項目は比較的良好。
- 項目9(後方への外乱反応)が0点。過剰に体幹を屈曲させてしまい、前に倒れそうになる。
- 解釈:
- 外的な刺激に対する適切な姿勢応答プログラムが働いていない。転倒への恐怖心から過剰な代償反応が出ている可能性。
- 介入:
- 予測可能な範囲で、ゆっくりとした外乱刺激から開始。「押しますよ」と声かけをし、適切な筋収縮を学習する練習を実施。徐々に刺激の速度や方向を変化させる。
- 再評価:
- FACTの反応的制御が改善。歩行中に人とぶつかりそうになった際も、パニックにならずに立ち直れるようになった。
FACTを使う際の注意点とコツ
FACTを臨床で安全かつ効果的に使うために、いくつかポイントがあります。
- 安全確保を最優先に:特に反応的制御の項目では、患者さんが転倒しないよう、いつでも支えられる位置で実施しましょう。介助者と2人で行うのも有効です。
- 患者さんへの丁寧な説明:何をするのか事前にしっかり説明し、不安を取り除くことが大切です。特に動的体幹運動は、患者さんが動きをイメージしやすいように、セラピストが一度やって見せる(モデリング)と良いでしょう。
- 他の評価との併用:FACTは体幹機能に特化した評価です。ADL全体の能力を見る**FIM(機能的自立度評価法)**や、他の動作観察(歩行分析など)と組み合わせることで、患者さんの全体像をより深く理解できます。
まとめ|FACTを使えば体幹が“見える”ようになる
今回は、脳卒中リハビリにおける臨床的体幹機能検査「FACT」について、その基本から臨床での活用法までを解説しました。
- FACTは「静的・動的・反応性」の3つの側面から体幹の“質”を評価できる客観的評価法である。
- 具体的な全10項目と採点基準により、体幹のどの機能に課題があるかを特定しやすい。
- 評価結果を解釈し、分離運動や姿勢応答といった具体的な課題に対する介入に繋げることが重要である。
- 安全管理と丁寧な説明を心がけることが、信頼性の高い評価を実施する上でのコツである。
「なんとなく」で見ていた体幹機能が、FACTというツールを使うことで**「見える化」**されます。この「見える化」は、患者さん自身や多職種へ状態を説明する際の共通言語となり、リハビリの精度と納得感を大きく向上させてくれるはずです。
ぜひ、FACTをあなたの臨床の引き出しに加え、体幹に焦点を当てた質の高いリハビリテーションを展開してください。