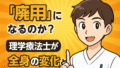そのSOAP、ただの「作業」になっていませんか?
「大腿骨頚部骨折の患者さんを担当したけど、毎日のSOAPの書き方で手が止まってしまう…」
「S(主観的情報)とO(客観的情報)は書けるけど、一番大事なA(評価・考察)に何を書けばいいか分からない…」
「先輩から『もっと臨床推論を深めて』と言われるけど、具体的にどうすれば…?」
新人・若手の理学療法士(PT)なら、一度はこんな悩みにぶつかったことがあるのではないでしょうか。
この記事では、そんなお悩みを解決するために、大腿骨頚部骨折リハビリにおけるSOAPの書き方の基本から、明日からすぐに使える時期別の具体的な例文までを解説します。
この記事が、SOAPが単なる記録作業ではなく、あなたの臨床推論を整理し、治療の質を高めるための最強のツールのひとつとなれば幸いです。
\臨床理学Labで臨床推論の練習をしませんか?/
現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。
• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈
• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える
• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事
全コンテンツが読み放題になります。

まずはおさらい!大腿骨頚部骨折リハで押さえるべきSOAPの基本
SOAPは、患者さんの状態を多角的に捉え、論理的なリハビリ計画を立てるためのフレームワークです。まず、各項目の役割と、大腿骨頚部骨折リハビリで特に着目すべきポイントを再確認しましょう。
- S (Subjective): 患者さんの「声」
- 何を聴くか: 疼痛(NRS/VAS)、転倒への恐怖感、不安、退院後の生活の目標、家族の意向など。患者さんの言葉の裏にある感情やニーズを汲み取ることが重要です。
- O (Objective): 客観的な「事実」
- 何を見るか: 術式(BHA/THA/骨接合術など)、禁忌肢位、荷重制限、バイタルサイン、創部状態、ROM、MMT、感覚、ADL(寝返り、起き上がり、移乗、歩行)の遂行状況と介助量、歩行観察、高次脳機能(特にせん妄や認知機能)など。
- A (Assessment): SとOを結びつけ「なぜ?」を考える
- 何を考察するか: ここが臨床推論の核心です。S情報とO情報を統合し、患者さんの問題点の根本原因は何か、なぜその動作ができないのかを分析・考察します。予後予測や、他の問題点との関連性も記述します。
- P (Plan): Aに基づいた「次の一手」
- 何を計画するか: Aで導き出した考察に基づき、具体的な治療計画を立てます。短期目標(Short-term goal)、長期目標(Long-term goal)、具体的な運動療法(To Do)、多職種との連携計画などを記載します。
【Point!】大腿骨頚部骨折リハで特に重要な視点
- 術式の理解: BHA/THA(人工骨頭置換術)なら後方アプローチによる**脱臼肢位(屈曲・内転・内旋)**の禁忌、骨接合術なら偽関節や骨頭壊死のリスクなど、術式ごとの注意点を必ず把握しましょう。
- リスク管理: 深部静脈血栓症(DVT)、せん妄、肺炎、褥瘡といった術後合併症の兆候を見逃さない視点が不可欠です。


【時期別】実践!大腿骨頚部骨折リハのSOAP例文集
ここからは、具体的な患者さんを想定し、急性期・回復期・生活期それぞれのSOAP例文を「悪い例」と「良い例」を比較しながら見ていきましょう。
《共通の患者像》
- 氏名: 大腿 花子 様
- 年齢: 82歳 女性
- 診断名: 右大腿骨頚部骨折(Garden stage Ⅳ)
- 術式: 人工骨頭置換術(BHA)後方アプローチ
- 既往歴: 高血圧、軽度の認知症
- 生活歴: 独居。近所に娘家族が在住。術前は室内T-cane歩行自立。
【Part1】急性期(術後3日目):テーマ「リスク管理と早期離床」
この時期の目標は、合併症を予防しつつ、安全にベッドから離れることです。
❌ 悪い例
S: 痛い。O: 車椅子移乗、一部介助。A: 疼痛のため移乗に介助要す。P: 移乗練習継続。
これでは、何が問題で、どう改善すべきかが全く分かりません。
⭕️ 良い例
S: 「起き上がる時にお尻がズキッと痛む(NRS 5/10)。また転ぶんじゃないか怖くて力が入らない…」と不安げな表情で訴えあり。
O:・BHA術後3日目。後方アプローチ(脱臼肢位に注意)。・Dr指示:翌日より1/2荷重開始予定。・バイタルサイン安定。DVT兆候(Homan’s sign)なし。・ROM: 右股関節屈曲80°(疼痛↓)、外転20°・MMT: 右膝伸展3、右股外転2+・端座位30分可能(ふらつきなし)。・ベッド⇔車椅子移乗:立位時に疼痛と恐怖心から患側への荷重不十分となり、中等度介助を要す。
A: 術後疼痛および転倒への恐怖心が、患側への荷重を妨げ、移乗動作自立の最大の阻害因子となっている。加えて、右股外転筋・膝伸展筋の筋力低下も荷重の不安定性に関与。ただし、離床への意欲はあり、指示理解は良好なため、疼痛コントロールと成功体験による心理的サポートが有効と推察する。まずは、安心・安全な環境下で患側荷重への信頼感を再獲得することが最優先課題である。
P:
- Short-term goal (1週間): 軽介助にて安定した車椅子移乗が行える。疼痛NRS 3/10以下で離床が行える。
- To Do:
- 疼痛管理: 移乗30分前の鎮痛薬使用について看護師と情報共有。運動前にホットパックで筋緊張緩和。
- 運動療法: 非荷重位での右下肢自動運動(足関節底背屈、SLR)。健側下肢の筋力強化(ブリッジなど)。
- 動作指導: 脱臼に注意しつつ、患側への荷重を促す声かけと、痛みや恐怖心の少ない動作方法(健側下肢を軸に立ち上がるなど)を反復練習し、成功体験を積む。
【Part2】回復期(術後1ヶ月):テーマ「ADL向上と歩行獲得」
この時期は、より実用的なADLの自立と、歩行能力の向上を目指します。
❌ 悪い例
S: トイレに行きたい。O: 歩行器で50m歩けた。A: 歩行能力が向上した。P: 歩行練習継続。
これでは、退院後の生活が見えてきません。
⭕️ 良い例
S: 「トイレまで一人で行けるようになりたい。でも、歩行器だと家の狭い廊下は曲がれないかもしれない」と退院後の生活に不安あり。
O:・平行棒内歩行20m監視レベル。歩行中、右立脚中期に著明な骨盤沈下(Trendelenburg sign +)あり。・歩行器にて病棟廊下50m自立。方向転換はやや不安定。・トイレ動作(ズボンの上げ下ろし)は手すり使用し見守りレベル。・MMT: 右股外転筋3+
A: 右中殿筋の筋力低下に起因するトレンデレンブルグ徴候が、歩行時の安定性低下と非効率な歩容の主因である。現在の歩行器歩行能力では、S情報にある家屋環境(狭い廊下)への適応は困難と予測される。在宅復帰を達成するためには、①中殿筋機能の向上による歩行安定化、②よりコンパクトな歩行補助具(T-cane)への移行、③狭い空間での方向転換・トイレ動作の自立、が課題である。
P:
- Short-term goal (2週間): T-caneにて病棟内30mを監視レベルで歩行可能となる。トイレ動作が自立する。
- To Do:
- 運動療法: 中殿筋の選択的強化(側臥位での股関節外転、立位での患側荷重練習)。
- 歩行練習: 平行棒内で骨盤帯を徒手的に制動し、正しい歩行パターンを学習。その後、T-cane歩行練習へ移行。
- ADL練習: 模擬家屋設備を利用し、トイレでの方向転換やズボン操作を反復練習。
- 多職種連携: MSW(医療ソーシャルワーカー)に家屋情報の詳細な聴取と、必要に応じて家屋調査の検討を依頼。
【Part3】生活期(退院後外来):テーマ「社会参加と再転倒予防」
退院後は、より活動範囲を広げ、QOL(生活の質)の向上と再転倒予防が目標です。
❌ 悪い例
S: 買い物に行きたい。O: TUG 15秒。A: 転倒リスクあり。P: バランス練習。
目標達成のために、何が足りないのかが不明確です。
⭕️ 良い例
S: 「近くのスーパーまで買い物に行きたいけど、途中の坂道と、横断歩道を渡り切れるかが不安。町内会の集まりにもまた顔を出したいんだけど…」と社会参加への意欲と不安を吐露。
O:・T-caneにて屋外歩行500m可能。軽度の坂道で歩行速度低下、体幹の側方動揺増大あり。・Timed Up and Go Test (TUG): 15秒(転倒リスク中等度)。・Functional Reach Test: 22cm(平均以下)。・自宅での転倒歴はなし。
A: 基本的な移動能力は獲得したが、不整地や坂道といった環境負荷の高い状況下での動的バランス能力と持久力に課題が残る。これがS情報にある屋外活動への不安に直結し、社会参加を制限している要因と考えられる。TUG 14秒以上は転倒リスクが高いという基準からも、地域で安全に生活するためには、応用的なバランス能力と持久力の向上が不可欠である。
P:
- Long-term goal (3ヶ月): 自信を持って近所のスーパーへ買い物に行き、月1回の町内会に復帰できる。
- To Do:
- 運動療法: バランスディスクや段差昇降など、より不安定な状況下でのバランストレーニング。坂道や砂利道などを想定した応用歩行練習。インターバル速歩による持久力向上。
- 環境設定の助言: 買い物時にシルバーカーやショッピングカートを利用するなど、安全性を高める代償手段の活用を提案。
- 自主トレ指導: 自宅で安全に行えるバランストレーニング(タンデム立位、片脚立位)と筋力強化メニューを写真付きの用紙で提供し、継続を促す。
SOAPの質を爆上げする!「ICFモデル」活用術
「A(考察)」がどうしても浅くなってしまう…という方は、**ICF(国際生活機能分類)**の視点を取り入れてみましょう。
ICFは、人の「生活機能」を「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の3つの次元と、それらに影響を与える「環境因子」「個人因子」で捉える考え方です。
(ここにICFモデルの簡単な図を挿入すると非常に分かりやすくなります)
先ほどの花子さんの例をICFで整理すると、思考がクリアになります。
- 健康状態: 右大腿骨頚部骨折(BHA後)
- 心身機能・構造: 股関節痛、右下肢筋力低下、バランス能力低下、BHAという身体構造の変化
- 活動: 歩行困難、移乗制限、トイレ動作制限
- 参加: 買い物に行けない、町内会に参加できない
- 環境因子(促進/阻害): (阻害)独居、家の廊下が狭い、近所に坂道がある (促進)近隣に娘家族、手すりの設置
- 個人因子: 82歳女性、軽度認知症、転倒への恐怖心、社会参加への意欲
このように整理すると、**「中殿筋の筋力低下(心身機能)が、歩行(活動)を不安定にし、その結果、買い物(参加)に行けないという不安(個人因子)を生んでいる」**といったように、各要素のつながりが見えてきます。
このつながりこそが、あなたの「A(考察)」を深め、患者さんを全人的に捉えたリハビリ計画(P)につながるのです。
まとめ:SOAPは最高の「臨床推論トレーニング」ツールです
今回は、大腿骨頚部骨折リハビリにおけるSOAPの書き方と例文を解説しました。
- ✅ SOAPは時期ごとの目標とリスクを意識して書く
- ✅ 「A」ではSとOを結びつけ、「なぜ?」と「今後どうなる?」を考察する
- ✅ ICFの視点を持つと、考察が多角的になり、深みが出る
SOAPは義務的な作業ではありません。患者さん一人ひとりと向き合い、その人らしい生活を取り戻すための道筋を描く、理学療法士にとって最高の「臨床推論トレーニング」ツールです。
まずは今日の担当患者さんのSOAPで、「A」に考察をもう一文だけ付け加えることから始めてみませんか?その小さな一歩が、あなたをデキるセラピストへと成長させてくれます。