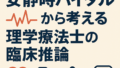はじめに
こんにちは!
理学療法士として日々の臨床に携わっていると、「患者さんに説明しているのに、うまく伝わらない」と感じる場面はありませんか?
私自身、新人の頃は説明が長くなってしまったり、専門用語を使ってしまい、患者さんの反応がいまいち…ということがよくありました。
それもそのはず。理学療法の説明は、専門知識と患者目線のバランスが求められる難しいスキルです。
しかし、ちょっとした工夫で、説明はぐんと分かりやすく、相手に届きやすくなります。
この記事では、「理学療法 説明の仕方 コツ」というテーマで、臨床現場で実際に使える5つの工夫をわかりやすく解説します。
患者さんとの信頼関係を築き、治療効果を高めたいと考えている方にとって、きっと役立つ内容になると思います。
⸻
なぜ説明力が大切なのか?
理学療法士は、ただ運動や施術を提供するだけでなく、
「なぜこのリハビリが必要か」
「どんな効果が期待できるか」
を患者さんに伝える役割も担っています。
説明力が求められる理由は大きく3つあります。
患者のモチベーション向上につながる
→ 自分のためになるとわかれば、やる気が出ます。逆に、「何のためにやっているのかわからない」と、取り組みが消極的になります。
治療の継続性や信頼関係に直結する
→ 十分に説明されることで、安心感が生まれ、納得してリハビリに取り組むようになります。
説明が不十分だと、不信感や誤解から離脱の原因にもなりかねません。
医療安全・リスク管理の観点でも重要
→ 患者さんにしっかり説明することで、誤った認識や無理な動作を防ぐことができます。リスクを避ける上でも説明は不可欠です。
このように、説明力は「治療効果」「患者満足度」「安全性」にも関わる、非常に大事なスキルです。
⸻
説明がうまくなる!5つのコツ
専門用語をやさしい言葉に置き換える
理学療法士が日常的に使っている言葉の多くは、患者さんにとって馴染みのない専門用語です。
例えば、「体幹の安定性」「荷重」「関節可動域」「筋緊張」など、私たちにとっては当たり前でも、患者さんにとっては難解です。
| 専門用語 | 優しい言い換え例 |
| 体幹の安定性 | お腹と腰の力がしっかりしている状態 |
| 荷重 | 足に体重をかけること |
| 関節可動域 | どこまで関節が動くかの広さ |
| 筋緊張 | 筋肉の硬さや力の入り具合 |
コツは、「小学生にも伝わる言葉」のような気持ちを意識すること。
患者さんの表情を見ながら、伝わっていないと感じたらすぐに言い方を変える柔軟性も大切です。
⸻
患者さんの生活に結びつける
抽象的な説明だけでは、患者さんにはイメージしにくいものです。
例えば、「大腿四頭筋を鍛えましょう」では、どんなメリットがあるかが伝わりません。
→ より伝わる言い方に変えると…

この太ももの筋肉を鍛えると、トイレやベッドから立ち上がるときにふらつかずに、スムーズに動けるになることに繋がります。
このように、日常生活の具体的な動作に落とし込んで伝えると、患者さんは「自分にとって必要な運動なんだ」と納得しやすくなります。
特に高齢者や退院後の生活を想定した患者さんには、生活場面に即した説明が効果的です。
⸻
図・写真・実演を使って視覚的に伝える
言葉だけの説明では限界があります。特に身体の構造や動きに関する内容は、視覚的なサポートがあると伝わりやすくなります。
• 関節や筋肉の働きを説明するときは、筋骨格模型やアプリの図を使う
• 複雑な動作は、実際に理学療法士がやって見せる
• ホワイトボードやタブレットを使って図に描きながら説明する
また、写真やイラスト入りの運動指導用紙を使うと、自宅でも復習ができ、継続率も高まります。
「見せる」「見ながら説明する」だけで、理解のスピードが格段に上がります。
⸻
「問いかけ」を交えて会話形式で進める
説明が一方通行になると、患者さんは受け身になってしまい、内容を覚えてくれないことがあります。
だからこそ、会話形式での説明が重要です。
• 「階段でふらつくことはありますか?」
• 「この動き、痛みや違和感はありましたか?」
• 「この運動ご自宅でもできそうですか?」
こうした問いかけを交えることで、患者さん自身が自分の体について考えたり、リハビリの必要性を実感するきっかけになります。
さらに、対話の中で患者さんの価値観や希望を引き出すことができ、個別性の高いリハビリ設計にもつながります。
⸻
説明のあとは「理解度の確認」を忘れずに
一生懸命に説明しても、相手にきちんと伝わっているかは分かりません。
説明したあとに「理解できているかどうか」を確認する一言を入れるだけで、理解度や反応を知ることができます。
• 「わかりにくいところはありませんでしたか?」
• 「今日の内容を、ご家族に説明するとしたら、どんなふうに伝えますか?」
• 「じゃあこの運動、どんな目的があったか覚えていますか?」
このように確認の機会を設けることで、必要に応じて再説明できるほか、患者さん自身の理解を深めることにもつながります。
⸻
説明上手は一日にしてならず。少しずつ実践を!
ここまで読んで、「自分はうまく説明できていないかもしれない…」と思った方も安心してください。
説明の上達に必要なのは、“意識”と“経験”の積み重ねです。
今日からできることを、ひとつずつ意識して実践するだけで、患者さんの反応は少しずつ変わっていきます。
「なるほど、わかりやすい」と言ってもらえたときの喜びは、理学療法士としてのやりがいにもつながります。
⸻
まとめ:説明は「伝える」ではなく「伝わる」が大事!
今回のまとめ:患者さんに伝わる説明のコツ5選
1. 専門用語は小学生でもわかる言葉に置き換える
2. 日常生活の動作と結びつけて具体的に説明する
3. 図や実演を使って視覚的に伝える工夫をする
4. 一方通行ではなく、問いかけを交えた会話形式にする
5. 説明のあとは必ず理解度の確認を行う
説明力は「知識」や「技術」と同じくらい大切なスキルです。
今日から、あなたの言葉で患者さんの気持ちを動かしてみませんか?
臨床理学Labについて
「臨床理学Lab」ではより専門的な記事を作成しています。
ここでは全ての有料記事を読むことができます。
ここは、単なる情報提供の場ではありません。
あなたの疑問や悩みを共有し、共に考え、共に成長できる場です。
単なる知識の提供ではなく、臨床で使える「考え方」を身につけることを重視していきたいと思います。
「この評価の結果から、次に何をすべきか?」
「この患者にはどんなアプローチが適切なのか?」
といった問いに対し、論理的に答えを導き出せるようになることを目標としています。
臨床推論を深め、評価力・判断力を向上させるために、一緒に学んでいきましょう!
👇