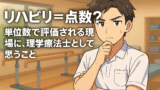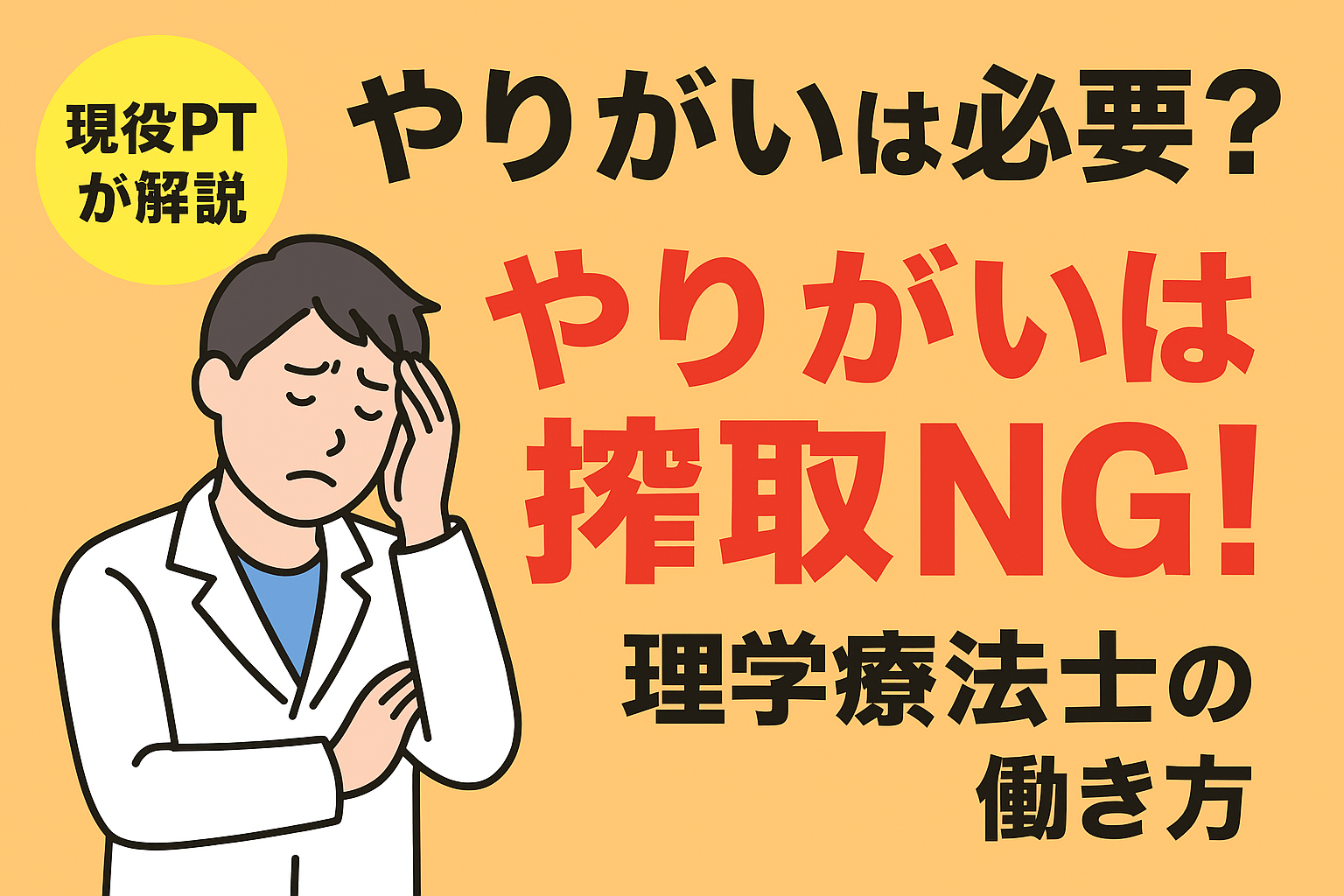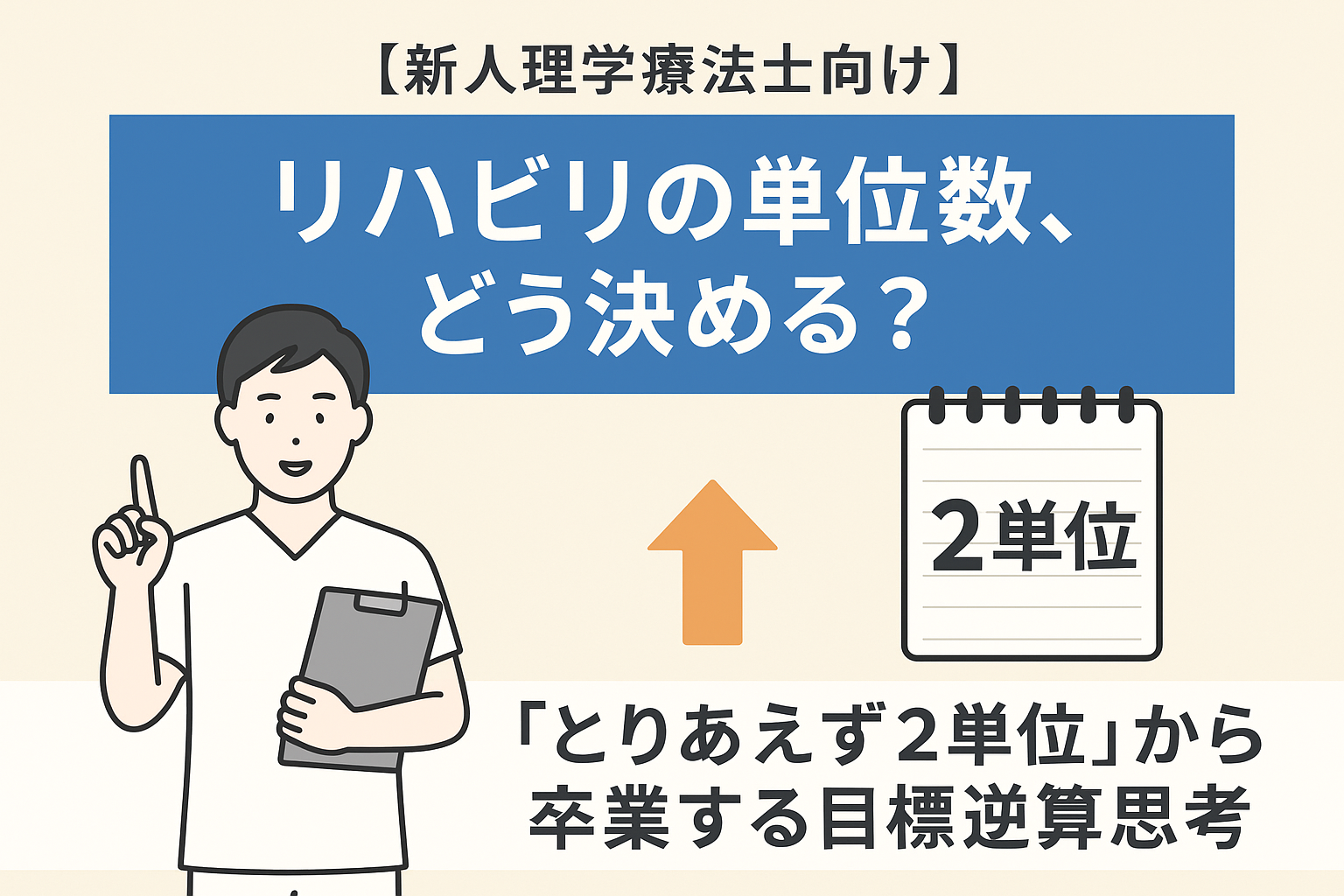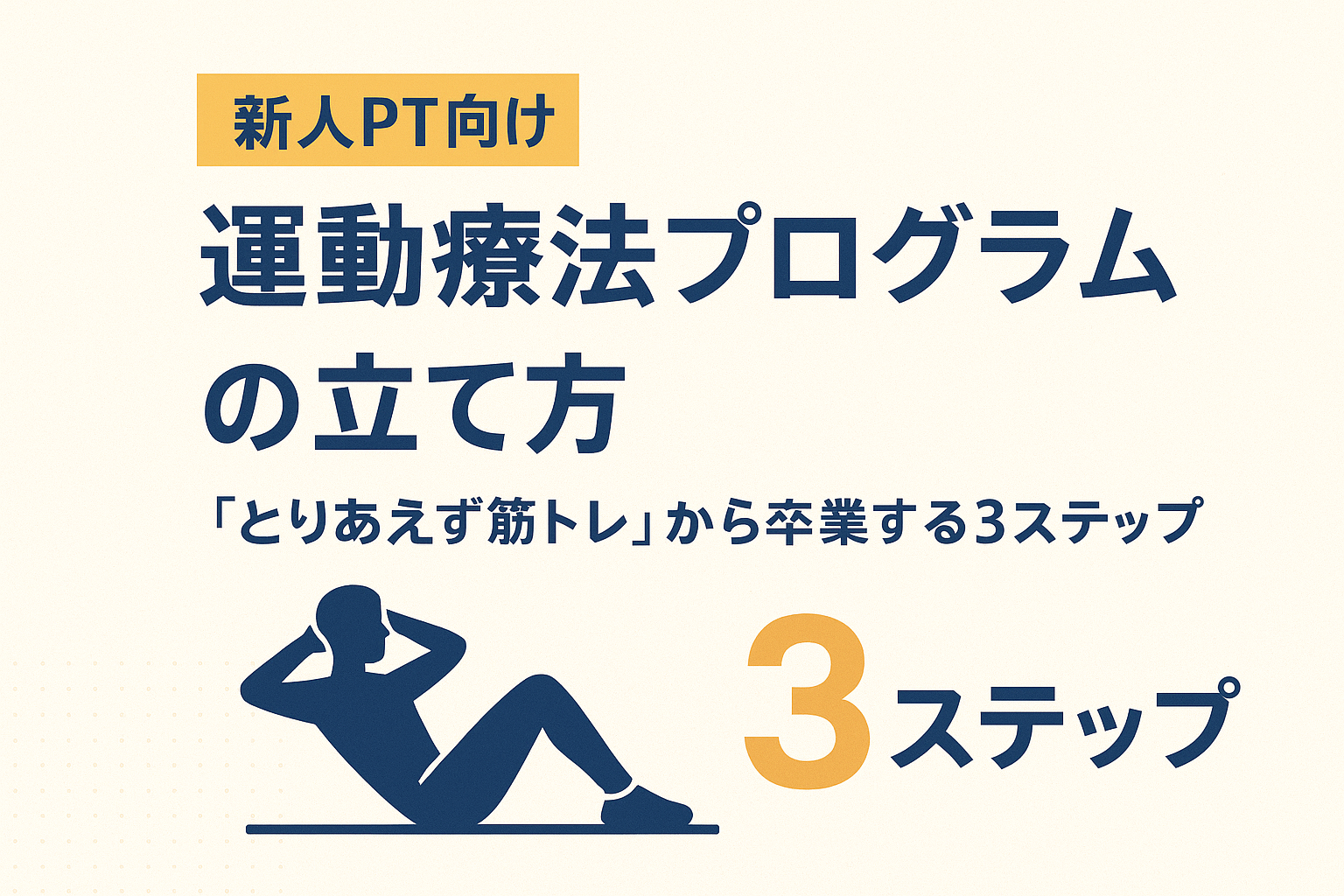何単位にするか悩んでいませんか?
「今日の〇〇さんのリハビリ、何単位で組もうかな…」
「先輩の真似をしてとりあえず2単位で組んでいるけど、これで本当にいいんだろうか…」
「先輩になんで2単位必要なの?と聞かれて上手く答えることができなかった…」
臨床に出たばかりの新人理学療法士(PT)の皆さん、毎日こんな風に悩んでいませんか?
特に急性期病院では1単位でリハビリを行わなければならない状況が少なからずあります。もちろん必要に応じて2単位3単位と設定し対応していく能力が必要です。僕も新人時代、リハビリの単位数を決めるのに毎回頭を悩ませていました。
でも、ある「モノサシ」を持ってから、自信を持って単位数を決められるようになりました。
単位数、リハビリ時間を決めるのには様々な要因が絡み合い一概にコレがいい!と言い切ることはできませんが、今回記事では、僕が実践しているうちの一つ、「患者さんの目標から逆算してリハビリ単位数を決める方法」を、具体的なケースを交えて解説します。
この記事が、あなたも「なんとなく」から卒業し、根拠を持って患者さん一人ひとりに最適なリハビリを提供できるようになる一助となれば幸いです。
僕の結論:リハビリ単位数は「目標までの距離」で決める
いきなり結論からお伝えします。
僕がリハビリの単位数を決めるときに最も大切にしているモノサシ。それは、「患者さんの目標達成まで、今どれくらいの距離があるか?」です。
- 目標までの距離が遠い → しっかり時間を確保して介入(例:2〜3単位)
- 目標までの距離が近い → 課題を絞って短時間で集中(例:1単位)
リハビリの単位数は、私たちの都合で決めるものではありません。あくまで、患者さんが目標を達成するための「手段」です。
患者さんの「今いる場所」と「目指すゴール」を正確に把握し、その道のりを最短で、かつ最も効果的に進むための時間をデザインする。これが、僕たちの専門性だと考えています。
もちろん、目標設定以外の要因で単位数が1単位、ないし2単位となる場合もあります。例えば、全身状態が不良な方は2単位でリハビリをするには難しいです。色んな視点から単位数を決めれるとさらに良いと言えます。
【ケースで解説】「自宅退院」を目標とする2人の単位数の決め方
言葉だけでは分かりにくいので、同じ「独居での自宅退院」を目標にしている2人の患者さんを例に、僕の単位数の決め方を見ていきましょう。
ケースA:目標までが”遠い”Aさん(発症直後で、まだ座る・立つことも難しい)
- 目標: 自宅に一人で帰り、身の回りのことができるようになる。
- 現状: ベッドから起き上がる、座る、立つといった基本的な動作(ADL)に全介助が必要。体力も低下している。
- 目標までの課題:
- まずはベッド上で安全に体を動かす練習
- 安定して座る練習(座位保持)
- 安全に立ち上がる練習(起立練習)
- 基本的な筋力や持久力の向上
- 安全に配慮した訓練が必須
- 単位数の考え方:【2〜3単位】
Aさんの場合、目標達成までにクリアすべき課題が山積みです。一つひとつの動作練習に時間がかかりますし、疲労を考慮して休憩を挟みながら、質の高いリハビリを提供する必要があります。そのため、しっかりと時間を確保できる2〜3単位で介入計画を立てます。
ケースB:目標までが”近い”Bさん(病棟内のADLはほぼ自立)
- 目標: 自宅に一人で帰り、身の回りのことができるようになる。
- 現状: 病棟内の歩行やトイレ動作は、手すりを使えば一人で可能。身の回りのことはほぼ自立している。
- 目標までの課題:
- 退院後の生活を想定した応用的な動作練習(例:自宅の段差、屋外歩行、調理動作など)
- 自主トレーニングの指導と習慣化
- 福祉用具や住宅改修の相談
- 単位数の考え方:【1単位】
Bさんの場合、基本的な動作は獲得できています。リハビリ室で長時間ダラダラと歩行練習をするよりも、「今日は退院後を想定して、お風呂の入り方を練習しましょう」「この自主トレを完璧に覚えましょう」と目的を絞って、短時間で集中して行う方がはるかに効果的です。
この場合、戦略的に1単位を選択します。リハビリ以外の時間を、患者さん自身が病棟で実践練習する「自主性」を促すことにも繋がります。
「1単位」で組む勇気と、チームへの「説明責任」
新人セラピストが躊躇するのが「1単位で組むこと」ではないでしょうか。(僕の周りのスタッフでの話にはなりますが。)
「楽をしていると思われないか…」
「リハビリ時間が短いとクレームが来ないか…」
その気持ち、よく分かります。しかし、先ほどのBさんのように、目的が明確であれば1単位は「手抜き」ではなく、患者さんのための立派な「戦略」です。
ここで重要になるのが「説明責任」です。なぜその単位数にしたのか、根拠を説明できるようにしておきましょう。
- 患者さんへ:「Bさん、もう歩くのは上手なので、今日は退院後に困らないように、ご自宅の玄関を想定した段差の練習を20分集中してやりましょう!」
- 看護師さんへ: 「Bさんは日中の活動量を上げたいので、リハビリは午前に集中して行い、午後は病棟の廊下を2往復するのを目標にしてもらう計画です。」
このように、目的と計画をチームで共有できれば、誰もあなたのリハビリを「手抜き」だとは思いません。むしろ、患者さんのことをしっかり考えている、頼れるセラピストだと信頼されるはずです。
【まとめ】あなただけの「モノサシ」で、最適なリハビリを届けよう
今回は、僕が実践しているリハビリ単位数の決め方についてお話ししました。
- 単位数に迷ったら、まず「患者さんの目標」と「現在地」を再確認する。
- その「距離(道のり)」に応じて、最適な介入時間(単位数)をデザインする。
- なぜその単位数なのか、自信を持って患者さんやチームに説明できるようにする。
もちろん、患者さんのその日の体調や集中力、他のリハビリとの兼ね合いなど、考慮すべき点は他にもたくさんあります。
ですが、まずは「目標からの逆算」というモノサシを持つだけで、日々の臨床での迷いは格段に減るはずです。
「とりあえず2単位」から卒業し、あなたなりの根拠に基づいた「オーダーメイドのリハビリ」を患者さんに届けていきましょう。応援しています!