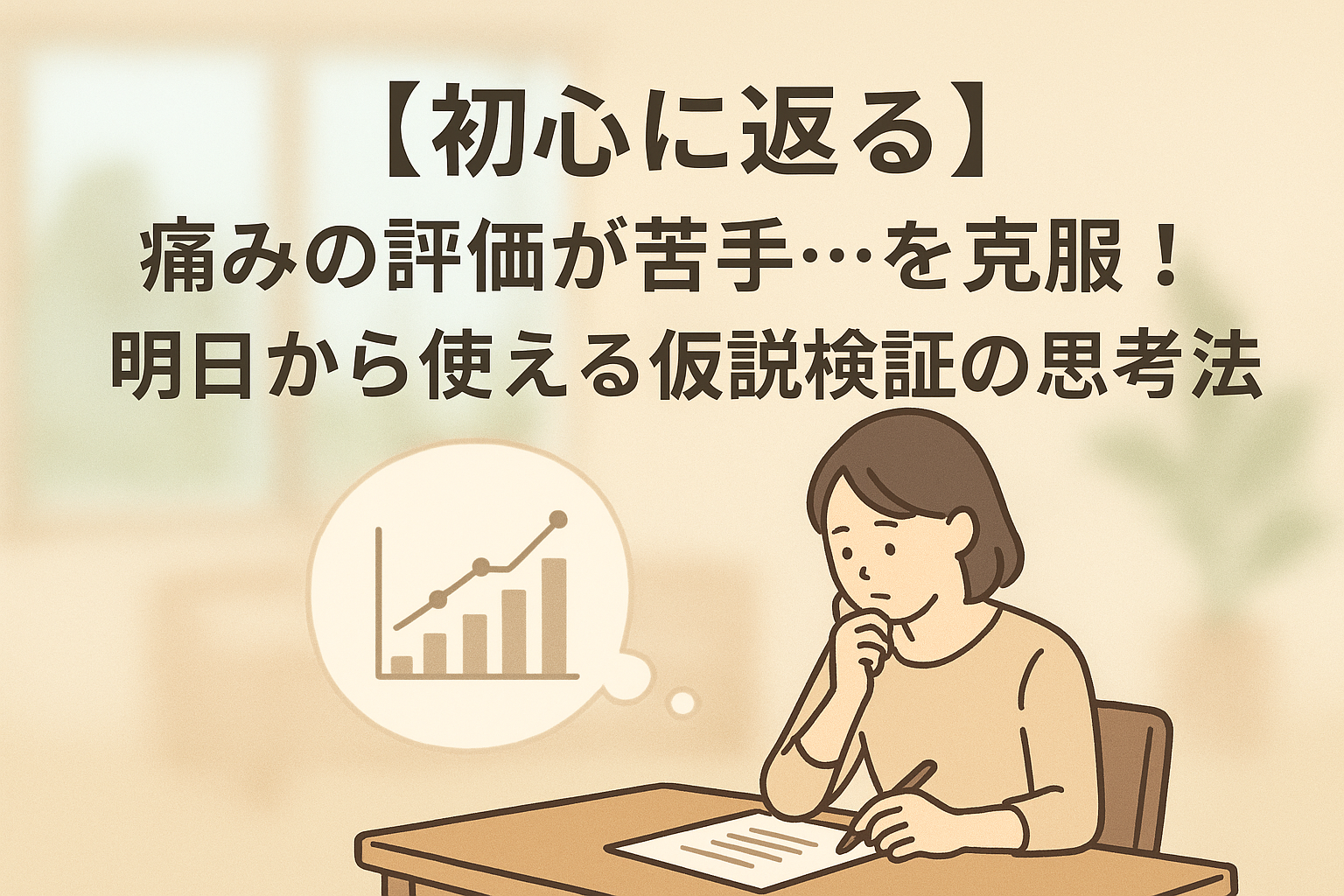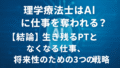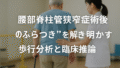痛みの評価が苦手ではないですか?
「先輩から『この痛みの原因は?』と聞かれても、自信を持って答えられない…」
「問診で何を聞けばいいのか、いつも同じ質問ばかりで深掘りできない…」
「動作を見てはいるけど、それが痛みにどう繋がっているのか説明できない…」
若手の理学療法士・セラピストなら、一度はこんな壁にぶつかったことがあるのではないでしょうか。
患者さんの「痛み」と向き合うことは、私たちの仕事の根幹です。しかし、その評価はあまりに複雑で、どこから手をつけていいか分からなくなりがちですよね。
もしあなたが、
- 痛みの評価に苦手意識がある
- 自分の評価と治療に自信が持てない
- 評価の「思考プロセス」を体系的に学びたい
そう感じているなら、この記事はきっとあなたの助けになります。
この記事では、複雑な痛みの評価をシンプルに捉え、臨床での実践に繋げるための「思考の軸」をご紹介します。
なぜ、あなたの「痛み評価」は上手くいかないのか?
多くのセラピストが痛みの評価でつまずくのには、共通した原因があります。それは、知識が断片的で、「仮説と検証」という一連の流れになっていないからです。
- 痛みの分類は知っているけど、問診でどう活かせばいいか分からない。
- 問診はしているけど、ただの質問リストになっていて仮説が立てられない。
- 動作は見ているけど、それが仮説の検証になっていない。
この悪循環から抜け出すために、まずはすべての基本となる「痛みの分類」から思考を整理していきましょう。
評価の第一歩!すべての基本となる「痛みの3大分類」
痛みの評価で最初にやるべきことは、目の前の患者さんの痛みが、どの種類に分類される可能性が高いかを考えることです。痛みは、その発生原因によって大きく3つに分けられます。
① 侵害受容性疼痛
組織の損傷によって生じる、いわゆる「ケガの痛み」です。関節や筋肉、靭帯などが傷つくことで発生します。私たちの介入で最も対象となることが多い痛みです。
【臨床のヒント】「機械的ストレス」を考えよう!侵害受容性疼痛の多くは、身体の組織に加わる物理的な力、つまり「機械的ストレス」が原因です。評価では、**「どの動きが、どの組織に、どんなストレス(引っ張り、圧縮など)をかけているのか?」**を考えることが、原因究明の最大の鍵になります。
② 神経因性疼痛
神経そのものが傷ついたり、圧迫されたりして生じる痛みです。「ビリビリ」「ジンジン」「焼けるような」といった特殊な表現をされることが多く、坐骨神経痛などが代表例です。
③ 心因性疼痛
身体的な異常が見つからない、あるいは身体的な異常だけでは説明がつかない痛みを指します。心理的・社会的なストレスが複雑に関与しているケースです。
まずはこの3つの視点を持つだけで、患者さんの話を聞くときのアンテナの張り方が変わってくるはずです。

でも、分類が分かっても、そこからどうやって具体的な原因を探ればいいの?
そう思いませんでしたか?
その通りです。分類はあくまでスタート地点。臨床で本当に重要なのは、ここから「問診で仮説を立て、動作分析で検証する」という一連の思考プロセスを実践することです。
この、多くのセラピストが最も苦手とする「仮説検証サイクル」を、誰でも実践できるように体系的にまとめたのが、今回ご紹介するnoteの記事です。
あなたの臨床を変える「痛みの評価ガイド」のご案内
この記事では、あなたが明日から臨床で自信を持って痛みの評価に臨めるようになるための、具体的な思考プロセスと実践的なツール(フローチャート)を入れてみました。
▼ この記事で、あなたは以下の全てを手に入れられます ▼
- Point 1:もう迷わない!明日から使える「問診14のチェックリスト」とその臨床的解釈法
→ ただ聞くだけでなく、「なぜそれを聞くのか」「得た情報から何を考えるべきか」まで徹底解説します。 - Point 2:見る目が変わる!股関節痛・肩関節痛で学ぶ「動作分析の具体例」
→ 「なぜその動きで痛むのか?」を運動学・運動力学的に分析し、仮説を検証する具体的な手順がわかります。 - Point 3:思考が整理できる!「臨床実践フローチャート」で評価プロセスを完全視覚化
→ 評価の流れが一目でわかるフローチャートで、あなたの頭の中をクリアに整理。もう評価で迷子になることはありません。
この記事を読めば、あなたは…
✅ 先輩への報告やカンファレンスで、論理的に評価結果を説明できるようになります。
✅ 患者さんに対して、痛みの原因を自信を持って説明できるようになります。
✅ 評価に基づいた、的確な治療プログラムを立案できるようになります。
あなたの臨床家としての成長を、この記事が全力でサポートします。
2つのプランから、あなたに合った学び方を選べます
プランA:まずはこの記事だけ試したいあなたへ
【記事を単体で購入する】
今すぐ痛みの評価の悩みを解決したい!という方は、こちらの記事を単体でご購入ください。評価の基本が詰まった、永続的にあなたの参考書となる一本です。
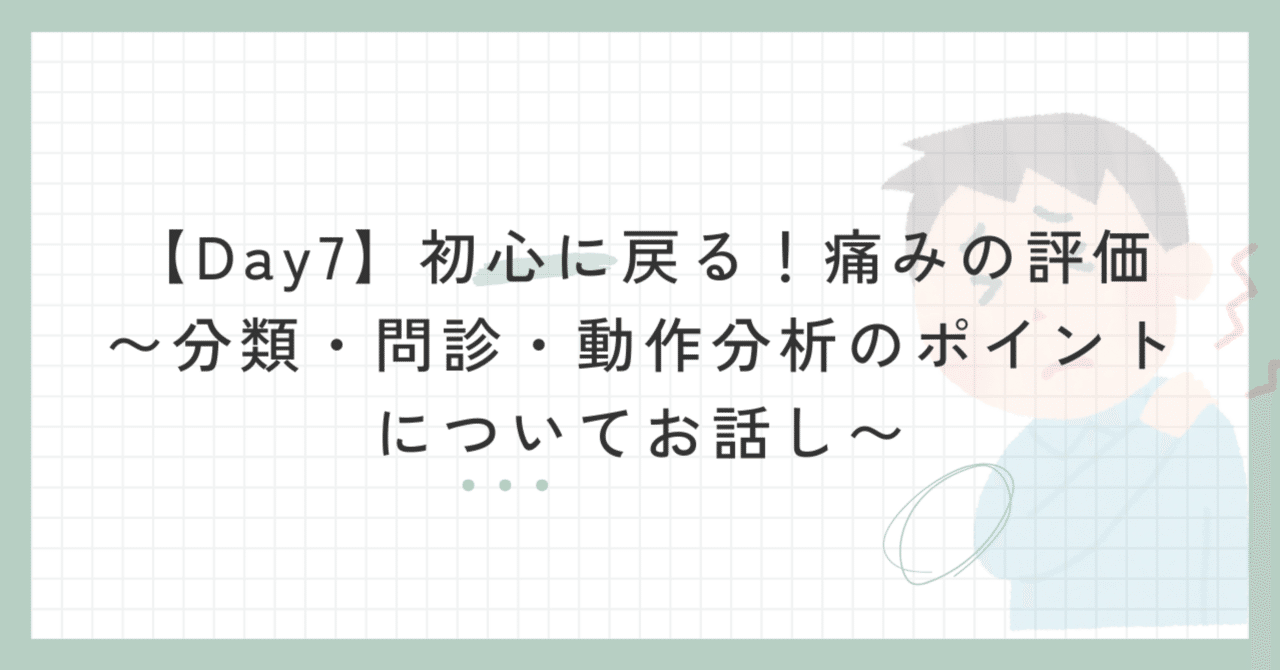
プランB:継続的に学んで、もっと成長したいあなたへ
【お得なメンバーシップに参加する】
この記事だけでなく、過去の有料記事もすべて読み放題!今後追加される記事も、もちろん読み放題です。臨床の知識を継続的に学び、周りのセラピストと差をつけたい向上心のあるあなたに最適なプランです。

最後に
痛みの評価は、確かに簡単ではありません。しかし、正しい「思考の型」を身につければ、誰でも必ず上達できます。
今日の小さな学びへの投資が、あなたの臨床家としての未来を大きく変えるかもしれません。
まずは一歩、踏み出してみませんか?